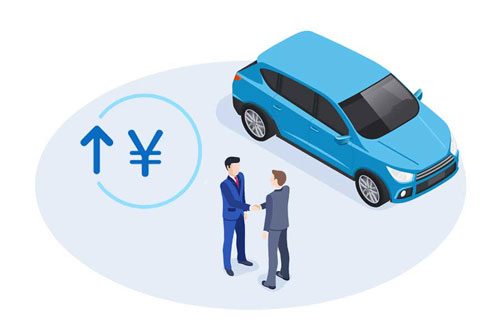毎年4月から5月に納付しなければならない税金に自動車税があります。金融機関やコンビニの窓口で支払ったあとに受け取る受領書は、どのように処理したらよいのでしょうか。
保管しておかなければならないと聞いていても、何のために、いつまで保管すれば良いのか分からない方も少なくないでしょう。
この記事では、自動車税の支払い後に受け取る納税証明書の取り扱いについて、必要なシーンや紛失時の再発行の方法について紹介します。
自動車税の納税証明書は必ず保管しておきましょう

納税証明書は車検の時や車を手放す時などに必要な書類であり、紛失してしまうと必要な手続きを進められなくなってしまいます。この証明書は、納税通知書に添付されており、自動車税や軽自動車税を納付すると受領書として受け取れます。
車に関連する手続きを進める際に重要な書類であるため、紛失しないように保管しておかなければなりません。多くの人は車検証入れの中に、車検証とともに保管しています。必ずその場所に保管しなければならないわけではありませんが、なくさないような工夫が重要です。
自動車税の納税証明書とは?
自動車税の納税証明書は自動車税や軽自動車税といった、車の所有者に課される地方税を納付した後に受け取れる、税金を納めたことを証明する公的書類です。
令和元年10月から施行された税制改正によって、自動車税と軽自動車税の名称が、それぞれ「自動車税(種別割)」と「軽自動車税(種別割)」に変更されました。
その結果、正式名称は「自動車税(種別割)納税証明書」と「軽自動車税(種別割)納税証明書」になっています。
ここからは自動車税に関する、納付書の届く時期や届かない場合の確認方法といった基本的な事項について紹介します。
自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している人に納税の義務が課されます。そのため、支払いに必要な納付書は所有者に向けて5月をめどに送付されます。
納付する方法は、金融機関やコンビニの窓口にて現金支払いする以外にも、パソコンやスマートフォンから納付できます。
現金払いのメリットは、支払いが完了した後に、すぐ納税証明書を入手できる点です。提示した納付書に領収印が押されれば、それがそのまま証明書になるためです。
一方で、電子決済を利用した場合、納税証明書は発行されません。そのため、納税証明書が必要な場合は自動車税事務所や都道府県、市町村の役所窓口で交付請求しましょう。
もし、納付書が届かない場合、引っ越し前の住所へ納付書が送付されているかもしれません。
引っ越しの時に住民票を変更しますが、自動車税に関しては自動車の登録住所も変更しなければなりません。住所変更は運輸局にて手続きしてください。
納付書の送付に気づかず、滞納してしまうと車の維持管理に悪影響を及ぼします。登録住所の変更はつい忘れがちな項目だからこそ、注意して対応しましょう。
普通自動車の場合、自動車税の管轄は都道府県です。そのため、都道府県の税事務所や自動車税管理事務所で手続きしてもらわなければなりません。
一方で、軽自動車税の管轄は市町村です。再発行の手続きは市町村役場へ依頼しましょう。
車の売り時はいつ?タイミングを誤ると損することも!
自動車税の支払い方法

ここからは、自動車税の支払い方法について紹介します。
現金支払いやクレジットカードを利用して支払える一方で、アプリの支払い機能を経由できるようになるなど、年々手段が拡大しています。納付漏れしないことが重要であるため、自分にとって支払いしやすい方法を選ぶようにしましょう。
特に、24時間どこからでも支払える方法を知っておけば、1日が落ち着いたタイミングの遅い時間であっても、期限ぎりぎりに思い出したとしても支払えます。
1つ目の方法は、送付された納付書をコンビニへ持ち込んで支払う方法です。店舗が普及しているコンビニはアクセスしやすく、ちょっとした外出のついでに納付できるため、利便性の高い方法の一つと言えます。
とはいえ、自動車税に限らず都道府県に納める税金額が30万円を超える場合はコンビニを利用して納付できません。自動車税でそのような金額にはなりにくいですが、金額があまりにも大きすぎる場合、コンビニでは対処できないようです。
また、次のようなポイントに注意しましょう。
- 納付書に印字されたバーコードが汚損している場合
- 納付書の支払金額を修正している場合
- 納付書および領収済通知書にある納付期限を過ぎた場合
特に納付期限切れは油断していると起きやすい事象です。期限内に支払えるように対応しましょう。
2つ目の方法はネットを経由したクレジットカード決済です。いつでもどこでも支払える利便性の高さがメリットです。また、実際に支払ったタイミングとカードの利用代金の支払いタイミングがずれることが多く、まとまった金額の支出を先送りできる点も魅力の一つでしょう。
支払い方法は一括払いの他、分割払いやリボ払いも利用できます。インターネットにアクセスし、必要事項を入力すれば、いつでも支払いを済ませられるため、いつも忙しい人にとっておすすめの方法です。
ただし、決済手数料がかかる点には注意しましょう。支払いが簡単であるからこそ、複数の支払いがある場合は1件ずつ加算されます。
また、自治体によっては、税額によって手数料が段階的に変わるところもあります。計算してみるとコンビニを利用した方が安く済むケースもあるため、検討している人は事前に手数料の金額を確かめておくと良いでしょう。
3つ目の方法は銀行系アプリの支払い機能を活用することです。最近は顧客の利便性を向上させるために各銀行とも専用アプリのリリースが盛んです。アプリを経由し、QRコードやバーコードを利用すると、簡単で便利に納付できるでしょう。
使い方はアプリごとによって異なりますが、取引画面の支払い機能を利用する方法が一般的です。支払い方法も、事前に引き落とし口座を指定しておけば、クレジットカードの登録も不要かつ、納税による金額の動きがアプリで一元管理できるようになります。
4つ目の方法はスマートフォン用決済アプリの利用です。利用可能なアプリは次のようなものがあり、決済手数料が不要な点が魅力です。
- au Pay
- d払い
- J-Coin Pay
- LINE Pay
- PayPay
- モバイルレジ
これらはバーコードの読み取り機能を搭載しているため、納付書に印字されたバーコードをそのまま利用でき、便利です。
とはいえ、自治体によって利用できないアプリもあるため注意しましょう。納付通知書の裏側に利用可能な支払いサービスが記載されています。自分が住んでいる自治体で利用できる支払い方法を事前に確かめておけば、支払いに困ることもなくなるでしょう。
納税情報はインターネットで確認できる

支払った納税情報の確認方法は、現金支払いした際の納税証明書だけではありません。平成27年4月よりはじまった納税情報のデジタル化によって、インターネットを経由して確認できるようになりました。
利用するシステムは「納税確認システム」と呼ばれています。税務署や市町村がインターネットを通じて税金の納付状況を確認する為に用いられており、次のような車検証に記載された情報さえあればリアルタイムに確かめられる点がメリットです。
- 自動車の登録番号
- 車台番号の下4桁
ネット環境さえあればシステムにアクセスできるため、外出中であってもタブレットやスマートフォンから確認できます。24時間アクセスできるため、必要に応じて活用してみましょう。
コンビニなど、窓口で納付する場合、基本的に現金支払いであり、提示した納付通知書へ領収印が押印されるため入手できます。一方で、クレジットカードを利用するようなネットを経由した支払い方法の場合、領収印を押印することがないため、証明書を受け取れません。
もし、納税証明書が必要になれば、別途再発行の手続きを進めましょう。
自動車税納税証明書が必要なシーン

税金を納付することで受け取れる納税証明書は、どのようなタイミングで必要になるのでしょうか。
納付状況の確認がデジタル化されたタイミングから、支払い方法によっては証明書を受け取れません。基本的には提示不要のケースが多いものの、もしもの時には提示を求められます。
必要なタイミングが分かっていれば、事前に対策や準備ができるため、以下で紹介するパターンを必ず覚えておきましょう。
以前は車検を受ける際に納税証明書を提示しなければなりませんでしたが、前述の通り納付状況をオンラインで確認できるようになってからは、原則不要となっています。しかし、タイミングによっては証明書を準備しておかなければならない点に注意しましょう。
例えば、車検のタイミングが6月ごろに控えている場合です。5月末までの納付期限に対して、期限間際に支払った場合は車検時にオンラインで確認できないかもしれません。
納付後、システムで確認できるようになるまで数日を要します。支払い直後であれば状況がアップデートされていない可能性があるため、念のために納税証明書を入手しておきましょう。
自動車を売却する場合においても、提示を求められるケースが少なくありません。
そもそも、車の売却時に納税証明書の提示義務はありません。しかしながら、売却後に納税できていなければ、本来支払わなければならない前の所有者の義務分を業者もしくは購入者が負担するトラブルに発展する可能性があります。
業者としても、そのようなトラブルを回避するために、提示を求めてくる可能性があるため、提出できるように準備しておきましょう。
マイカーローンなどを利用して車を購入した場合、ローン完済後の所有権解除手続きにおいて、納税証明書の提出が必要なケースがあります。
所有権解除手続きとは、車検証に記載されている所有者を信販会社やディーラーから自分へ移す手続きです。返済期間中はディーラーやローン会社が所有者に該当するため、このような状況になります。
手続きを進めるにあたって、車検証や印鑑証明書、完済証明書の他に納税証明書の原本またはコピーの提示を必要とするケースが少なくありません。
必要書類については、信販会社から提供されるため、準備しておきましょう。
車の売り時はいつ?タイミングを誤ると損することも!
運輸支局に納税情報が共有されるまでの期間
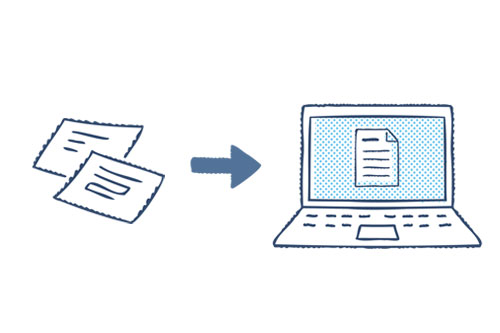
税金の納付状況は車検に大きな影響を与えます。未納の場合、車検を受けられません。そのため、運輸支局にて納税できているか確かめられる状況であることが重要です。
とはいえ、情報共有は支払い方法によって多少異なっています。納付後にあまり期間を開けずに車検を受ける場合、これから紹介する所要期間を参考に納付計画を立てましょう。
- 自動車税事務所や都道府県税事務所の窓口…納付から2営業日
- 市町村役場の窓口…約2ヶ月
- 金融機関や郵便局の窓口…約2週間
- コンビニエンスストア…約1週間
- スマートフォン決済…約1週間
- クレジットカード…約2週間
- ペイジー…約1週間
自動車税の納税証明書を受け取るタイミング

車に関連する各種手続きを進めるうえで納税証明書は重要な書類であることが分かりました。そのため、証明書を受け取るタイミングを正しく認識しておくことが重要です。
ここからは具体的なタイミングについて、納税方法別に詳しく解説します。
金融機関やコンビニで納税した場合、自動車税納税証明書は速やかに受け取れます。
支払い時に納付通知書を窓口へ提示しますが、納付通知書に証明書が合わさっており、支払いが完了すると店員さんから領収済員が押印されることで証明書を受け取れるようになります。
ただし、押印漏れがあると証明書として有効ではありません。支払い後、返却されたら速やかに押印の有無を確認しましょう。
コンビニや金融機関で支払わなかった場合、自治体によっては納税証明書を自宅へ郵送してもらえます。
一方で、一部のキャッシュレス決済で納税した場合は、基本的に証明書は発行されません。そのため、証明書が必要な場合は発行手続きを申し出ましょう。
証明書が発行されないケースのあるキャッシュレス決済方法は次の通りです。
- インターネットでのクレジットカード決済
- Pay-easy(ペイジー)納付
- スマホ決済(PayPay・LINE Payなど)
とはいえ、自治体によって納付方法は異なるため、事前に確かめておくとよいでしょう。
毎年4月末から5月にかけて郵送される納税通知書に支払期限が明記されています。納付漏れを避けることはもちろんですが、納付直後に車検が控えている場合、納付状況の共有に時間を要するため、車検時に確認できないケースも少なくないようです。納付証明書をその場で提示できるように準備しておくと良いでしょう。
自動車税の納税証明書の請求方法

納税証明書が納税後に自宅に郵送されない場合、もしくは誤って紛失してしまった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。具体的には、「窓口で請求する方法」と「郵送で請求する方法」の2種類があります。
ここからは、それぞれの方法について詳しく紹介します。不測の事態にも対応できるように知識を身につけましょう。
普通自動車を所有している場合は都道府県が管轄している税事務所の窓口へ、軽自動車を所有している場合は市町村役場の窓口へ証明書の発行を請求しましょう。
請求時に必要な書類は次の通りです。
- 自動車のナンバープレートの番号
- 自動車の車台番号
- 登録名義人の住所、氏名
ただし、納付後10日以内に請求など、支払い直後に手続きを進める場合、領収書の提示を求められる場合があります。請求するタイミングによって準備する書類が異なる点に注意しましょう。
郵送で請求する場合においても、請求先は窓口で依頼する場合と変わりません。また、基本的に準備しなければならない情報についても同様です。
ただし、連絡が取れる連絡先や発行事由を記載した書類が別途必要な点に注意してください。また、返信用封筒と切手が必要です。準備に必要な費用は請求する本人が負担しなければなりません。