軽自動車は、普通自動車と比較して購入や維持にかかる費用が安いため、手軽に利用できる車として男女や年齢層を問わず人気があります。
しかし、税金の仕組みは少々複雑で、特に自動車重量税について詳しく知らないという方も多いようです。
この記事では、軽自動車の自動車重量税の概要を説明し、その金額や支払いのタイミングを中心に、軽自動車税や環境性能割との違いや納付の仕組みまで幅広く解説します。
軽自動車の購入を検討している方や、維持費を見直したい方はぜひ参考にしてください。
軽自動車にも重量税が発生する

軽自動車には、普通自動車と同様に重量税を支払う義務があるのですが、これから軽自動車を購入するという方の中には、この税金がかかることを知らない方もいるようです。
普通自動車と比較して軽自動車の維持費は安いため、重量税がかからないと誤解している方も少なくありません。軽自動車にも重量税が課されることを理解しておくことで、軽自動車を購入する際の予算管理に役立ちます。
重量税は、新車購入時や車検の際にかかる税金ですが、エコカー減税対象車の場合は軽減される場合があるため、車を購入する際には減税の対象となっている車を選ぶという視点を持つのも良いでしょう。
軽自動車の自動車重量税とは?
自動車重量税はもともと道路の維持や新設に必要な費用を賄うために使われていましたが、現在は医療や教育などに関する公共事業に使われる税金となっています。
普通自動車の場合、自動車重量税は車両の重量に応じて課税されるのですが、軽自動車の場合は重量によらず一定額が課されることが特徴です。
重量税は、車検の有効期間に応じて課税されるため、車検が3年か2年かによって金額が異なる点に注意が必要です。新車を購入した場合は次の車検までの期間が3年であるため、初回の車検証交付時に3年分をまとめて納付します。また、車検の継続検査時には2年分をまとめて納付します。
エコカー減税対象車の場合は、燃費性能に応じて税額が軽減されることも押さえておきましょう。

軽自動車税と自動車重量税は混同されやすく、明確に違いを説明できないことが多い税金であると言えます。どちらも軽自動車にかかる税金ですが、税法上の分類と支払いのタイミングが異なるため注意が必要です。
軽自動車税は、4月1日時点で車を所有している人に納税義務が発生します。地方税であるため、納付先は居住している地域の市区町村です。税額は自家用・事業用や新車登録時期によって異なります。また、登録から13年経過した車は増額されます。
自動車重量税は、車両重量に応じた国税です。しかし、軽自動車の場合は重量に関わらず、定額で新車購入時や車検時にまとめ支払うのが特徴です。また、重量税はエコカー減税により大幅に軽減される可能性があるため、購入する車がエコカー減税の対象になっているか、その軽減率は何%なのか、しっかりと把握しておきましょう。

環境性能割は自動車の購入時にかかる、自動車取得税に代わる形で2019年10月から導入された税金です。重量税とは異なり、車を購入した時に1回だけ支払います。
環境性能割は、車両の取得価格をもとに計算され、その車の燃費性能に応じて税率が変動するのが特徴です。燃費性能が良い車であるほど税率が低くなり、軽自動車では取得価格の0〜2%が課税されます。燃費性能が良ければ非課税になるため、購入する車の環境性能をよく把握しておくことが大切です。
重量税は軽自動車では定額ですが、エコカー減税の適用条件を満たした車両では軽減されるため、環境性能割と同様に燃費性能に優れた車は税負担が軽くなると考えられます。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車の重量税を支払うタイミング

軽自動車の重量税は、車両を所有している人に対して1年ごとに課税されますが、実際の納付は車検の際にまとめて行います。
車検の際には、ディーラーや自動車整備工場に車を預けるケースが多いですが、その場合は重量税の手続きをディーラーや整備工場が代行してくれるため、所有者が直接手続きをする必要はありません。
ただし、ユーザー車検を利用する場合は、運輸支局に出向いて自分で重量税を納付する必要があります。
車検は新車登録から3年後、それ以降は2年ごとに受ける必要があるため、重量税もそのタイミングに合わせて行われることを覚えておきましょう。具体的には、以下のようなタイミングで支払います。
新車を購入した場合は、そのときに3年分の重量税を支払います。
購入から3年後の車検時に2年分の重量税を支払います。
再び車検を受け、2年分の重量税を支払います。
以降は車検のたびに、同じように支払うことになります。
軽自動車の重量税の金額

軽自動車の重量税は車検の際にまとめて支払う税金で、その金額は新車登録から経過した年数やエコカー減税の適用などによって変動します。
車検の期間によって、2年分または3年分の税金をまとめて支払うため、事前に金額を確認しておくことが重要です。
また、新車登録から13年以上経過すると税額が上がるため、長く乗っている車の重量税ではそれを考慮する必要もあります。
ここからは、軽自動車の重量税の金額を紹介していきます。
軽自動車の重量税を2年分支払う場合の金額は、車両が新規登録から何年経過しているかによって変動します。
重量税とは言っても、普通自動車と異なり、軽自動車の場合には車両の重量によって税額が変わることはありません。
軽自動車の税額は、新規検査からどれくらいの年数が経過したかによって変動します。車両の分類と新規検査からの経過年数に応じた税額は以下の通りです。
- 13年未満:6,600円
- 13年以上18年未満:8,200円
- 18年以上:8,800円
- 13年未満:5,200円
- 13年以上18年未満:5,400円
- 18年以上:5,600円
支払うタイミングは車検時で、ディーラーや整備工場が代行してくれるのが一般的であるため、自分で運輸局まで支払いに行くケースは稀です。
車検期間が3年ある場合は、3年分の重量税を支払う必要があります。3年分の重量税は2年分の税額に1年分を追加した金額になります。金額は以下の通りです。
- 13年未満:9,900円
- 13年以上18年未満:12,300円
- 18年以上:13,200円
- 13年未満:7,800円
- 13年以上18年未満:8,100円
- 18年以上:8,400円
エコカー減税対象車とは、燃費性能や排出ガスを抑える性能が一定基準を満たす車のことです。
基準を満たす車は、25%・50%・75%・100%の4段階の減税率が設定され、軽自動車税が減額されます。エコカー減税は、環境性能が高いほど減税額が大きくなるのが特徴です。
エコカー減税の対象となる車には、以下のようなものが挙げられます。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車
- ハイブリッド車
- プラグインハイブリッド車
- クリーンディーゼル車
- ガソリン車やLPG車も燃費基準により軽減あり
例えば、新規検査から3年分の税金は、エコカー減税対象外の場合は本則税率が適用され9,900円です。この税金が、エコカー減税が適用されると次の金額になります。
- 75%減税:1,800円
- 50%減税:3,700円
- 25%減税:5,600円
エコカー減税の適用期間が終了すると、通常の税率や経年による重課が適用される場合があるため、税額を確認することが重要です。
軽自動車の重量税を納付する方法
軽自動車の重量税はどのように納付するのでしょうか。重量税は車検の際に支払う義務がありますが、車検の方法により納付のやり方が変わることを覚えておきましょう。
車検を通す場合は、自ら陸運局で手続きをするユーザー車検と、ディーラーや整備向上に依頼する方法があります。どちらの方法で車検を受けるかによって、重量税の納付方法が異なるため、それぞれの方法について詳しく解説します。
自動車の所有者が、自分で車の点検・整備をして軽自動車検査協会に持ち込んで検査を受ける方法が「ユーザー車検」です。
ユーザー車検を利用する場合、軽自動車の重量税は陸運局や軽自動車検査協会で直接支払うことになります。検査の日に軽自動車検査協会の窓口で重量税の納付書をもらい、必要事項を記載した後で印紙を貼って申請します。
手続きに必要な書類は、車検証や自賠責保険の証明書などです。納付書は、軽自動車検査協会のサイトからダウンロードもできます。
ユーザー車検は、専門的な知識と技術が必要で手間もかかりますが、車検にかかる費用を抑えられる点が大きなメリットです。
車検を受ける際には、ディーラーや整備工場に依頼するという方が多数派ではないでしょうか。車の整備に関するプロにお任せすることで、車検にかかる手間を無くしてスムーズに進行できる点がメリットです。
ディーラーや整備工場に車検を依頼すると、軽自動車の重量税を業者が代行して納付してくれるため、書類作成や申請、支払いにかかる手間を極限まで減らせます。重量税を納付し忘れることもなく、時間の取れない方や手続きに不安のある方などにおすすめです。
ただし、ユーザー車検よりも費用が余計にかかることはデメリットに感じられるかもしれません。複数の業者で見積もりを取り、おおよその相場を把握しておくことが重要です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車の重量税を還付してもらえる制度がある

一定の条件を満たすことにより、残っている車検の期間に応じて納付済みの重量税が還付される仕組みがあることをご存じでしょうか。
自動車重量税還付制度と呼ばれる、この制度の適用対象となるためには、使用済みの軽自動車を適切に解体し、「解体返納」または「解体届出」を行う必要があります。
還付額は、納付済みの重量税額に、車検の有効期間に対する車検の残存期間の割合を掛けることで算出可能です。
例えば、納付済みの重量税が6,600円、車検有効期間2年(24ヶ月)に対して車検残存期間6ヶ月の場合、6,600円に4分の1(24ヶ月分の6ヶ月)を掛け、1,650円が還付金額となります。
ただし、普通自動車の一時抹消登録にあたる、軽自動車の「自動車検査証返納届」のように一時的な使用停止では還付対象外となるため注意してください。
抹消登録をすると重量税の支払い義務がなくなる
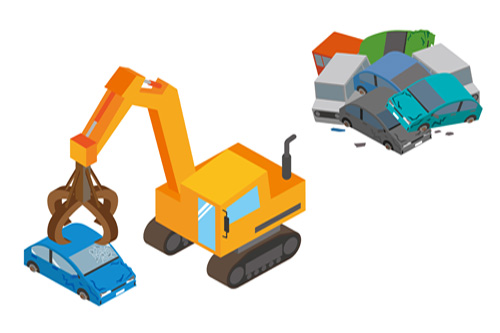
抹消登録とは、軽自動車の使用を中止または終了する際に行う手続きで、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。
一時抹消登録は、何らかの理由で一時的に車の使用を中止する場合に用いられ、永久抹消登録は廃車や自動車の解体の際に行われる手続きです。
これらの手続きを行うと、軽自動車の重量税や自動車税の支払い義務がなくなります。
軽自動車の使用を一時的に停止する場合には、一時抹消登録(自動車検査証返納届)の手続きを行います。
この登録をすることにより自動車税や重量税の支払いを止められます。また、再登録の手続きを行うことで再び車を使用することができます。
長期の海外赴任や病気・ケガなどの理由により、長期間にわたって車に乗らないのであれば、その期間の税金を節約するために一時抹消登録をしておくのが良いでしょう。
永久抹消登録は、軽自動車を解体処分した際に行う手続きで、車両情報が完全に抹消されるため軽自動車税や重量税の支払い義務も免除されます。
永久抹消登録には、事故や経年劣化により使用できない状態の車を解体し、管轄の軽自動車検査協会での手続きが必要です。
一度、永久抹消登録をした車は再登録ができないため、解体や廃棄によって、もうその車を使わないことが確定した場合にのみ手続きするようにしましょう。
13年経過した軽自動車におけるリスク

お気に入りの車を長い間にわたって愛用し続けるのは素晴らしいことです。大切に乗っている軽自動車は、10年でも20年でも走り続けてくれるでしょう。
しかし、年式が古くなり13年以上も使い続けていると、いくつかのリスクも生じてしまいます。そのため、リスクをしっかりと理解した上で適切に対応することが大切です。
ここからは、13年経過した軽自動車に生じる可能性のあるリスクについて見ていきましょう。
どんな車でも、経年劣化により次第に故障やメンテナンスの頻度が高くなることは避けられません。
13年以上使い続けている車は、エンジンやサスペンション、ブレーキといった重要な部品の摩耗や故障のリスクが高まっており、車検時に交換が必要な部品も増えているため、整備や修理に多くの費用がかかる可能性があります。
したがって、長い間使っている軽自動車を維持するには定期的な点検やメンテナンスが重要であり、思い切って新しい車への買い替えも検討する必要があるでしょう。
一般的に車両の価値は、年式が新しいほど需要が高く、古い車両はリセールバリューが低下する傾向にあります。経年による外観や内装の劣化は避けられず、買取の際に非常に低い価格しか、つかないことも珍しくありません。
このような車両価値の低下を極力抑えるためには、定期的にメンテナンスを行い、できるだけ良い車両の状態を保つことが重要です。
また、売却のタイミングを見極めることも大切で、価値が下がる前に売却を検討することをおすすめします。








