軽自動車は、普通自動車に比べて高速料金が安くなります。では、いわゆる有料道路や自動車専用道路、都市高速道路などの場合はどうでしょう?
ここでは、混同されがちなこれらの道路の種類とそれぞれにおける軽自動車の走行料金、そもそも軽自動車だとなぜ高速料金が安くなるのかについてまとめました。
さらに、高速道路を走行する際の注意点と、費用を節約する方法も解説します。軽自動車ドライバーの方は、ぜひ参考にしてください。
軽自動車の高速料金は安い!
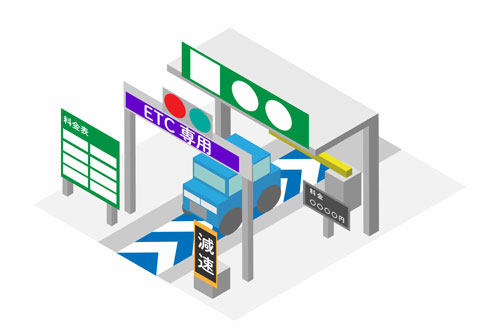
軽自動車の高速料金がどれくらい安いかは、普通自動車の場合と比較すると分かりやすいでしょう。軽自動車はその構造上、普通車と比べると高速道路を利用するメリットが少ないため料金も安くなっています。
高速料金は車両ごとに1kmあたりの料金が決まっていますが、軽自動車は普通自動車の8割に設定されています。この料金が、長距離割引、ETC割引、プラスされる固定額などで調整されて実際の料金が算出されるわけです。
なお、高速料金が徴収されるのは道路を造った時の借金を返済するためなので、その借金が精算されれば、将来的に高速道路というのは無料になるとされています。しかし、現時点ではそれがいつになるかは決まっていません。
高速道路とは?有料道路の種類について

ひとくちに高速料金と言っても、いわゆる「高速道路」はさらに細かく分類することができます。また、分類したそれぞれの道路に俗称と法律上の正式名称があったり、サイトによっては名称が混乱して使われていたりと、かなりややこしいです。
混同して使われやすいものに、「有料道路」「一般有料道路」「自動車専用道路」「都市高速道路」などがあります。
今回説明している「高速料金」が何を指すのか、一度ここで確認しておきましょう。
有料道路は有料の道路全般を指す言葉です。そのため、高速道路、有料の自動車専用道路、都市高速道路、有料の渡し船なども全て含みます。
これらの管理者は地方自治体や高速道路各社で、管理者もそうした公共機関です。
基本的に有料道路は道路法の管轄になりますが、企業などが管理する有料道路は管轄が異なることもあります。箱根ターンパイクや富士スバルラインなどの観光道路などが、そうしたケースにあたります。
一般有料道路は先述した有料道路の一種で、高速道路によって構成される交通ネットワークを補完する役割を負っています。ローカルエリアに密着した道路や観光用の道路などが、これに該当します。
具体例を挙げると、日光宇都宮道路、箱根スカイライン、東京湾アクアライン、京葉道路、仙台東部道路などです。
一般有料道路は地方公共団体によって管理され(企業が所有しているものもあります)建設時に借り入れた工事費を返済するため有料としており、返済が終われば無料になるケースも多くあります。
私たちが「高速道路」と呼んでいる道路の正式名称は高規格幹線道路です。これはさらに国が運営している「高速自動車国道」と、地方自治体が一部の費用を負担している「自動車専用道路(正式には一般国道自動車専用道路)」の2つに大別されます。
高速自動車国道は、都道府県をまたがる全規模の道路ネットワークを構成しています。「~自動車道」「~高速道路」という名称のものがこれに該当し、「A路線」と呼ばれることもあります。
自動車専用道路は、一つの地域内でのスムーズな自動車交通を目的に造られた道路です。よって、前者の高速自動車国道と比べると距離は短めです。
さらにこの自動車専用道路は、「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A路線)」と「一般国道の自動車専用道路(B路線)」に分類できます。
都市高速道路は名前に高速道路とついているものの、全国ネットワークを構成している高速自動車国道とは別物で、分類上は自動車専用道路(一般国道自動車専用道路)にあたります。
都市高速道路は、それのみで一つの道路ネットワークを構成しているのが特徴で、都市機能の維持と増進を目的として建設されています。
道路法上は、私たちが日常生活で使う「都道府県道」「市道」にあたるのですが、いわゆる高速道路としての役割を持っている点や、料金の徴収が行われる点などが独特です。
都市高速道路の類型に当てはまるものに、首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、広島高速道路、福岡北九州高速道路があります。
バイパスと呼ばれる道路は混雑する旧来の道路を避けて通行できるように造られたもので、渋滞の緩和などが目的です。
無料の一般道のみならず、カテゴリーとしては有料道路も含まれることがあり、有料無料を問わず「旧道を迂回できる」という機能面に対して付つけられる名称だと言えます。
例えば新東名高速道路は、東名高速道路のバイパスと考えることもできますし、名阪国道も名神高速道路のバイパスにあたります。本道である「国道〇号」に対して「国道〇号バイパス」と名付けられることもよくあります。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車が安くなる道路とならない道路がある

いわゆる「高速料金」は軽自動車の場合、安価に設定されています。
しかし、先に説明した「高速道路」「一般有料道路」「都市高速道路」などそれぞれの有料道路のカテゴリーで見た場合、全てにおいて必ず安い料金で走行できるとは限りません。
では、道路の種類ごとの料金設定を見た時、確実に安いのはどの道路なのでしょう?
まず狭義の高速道路、すなわち先に説明した「高規格幹線道路」の一種である「高速自動車国道」は、軽自動車の走行料金が安く設定されています。
また、同じく「高規格幹線道路」のうちの「自動車専用道路」の一種である「都市高速道路」も、やはり軽自動車で利用した場合は安めの料金で済むように設定されてます。
今のところ道路の種類ごとに見た場合、確実に軽自動車が安く走行できると言えるのはこの2つだけです。それ以外の有料道路は道路ごとに料金設定が異なり、安価な場合もあれば普通自動車と変わりない場合があります。
高速自動車国道と都市高速道路以外の有料道路は、どのような料金設定になっているのでしょう?
この2つを除く有料道路の中には、高速料金が普通自動車と同じ設定のところもあります。
有料道路の料金設定は、NEXCO3社など管理する事業主体によって異なっています。例えば、各地方公共団体の道路公社によって管理運営されている箱根スカイラインや、企業によって運営されている万座ハイウェイは、軽自動車と普通自動車の料金が同じです。
高速自動車国道と都市高速道路を除く有料道路は、どの道路なら安くなると一概には言うことはできません。軽自動車が普通自動車と同じケースもあれば、安くなるケースもあります。
地域別の高速料金の計算例

ここまでは、有料道路の種類とぞれぞれの道路の定義を説明してきました。
では、もう少し具体的に軽自動車が実際に高速道路を走行すると高速料金はどのくらい安いものなのかを見てみましょう。
以下では北海道から九州までの地域で、それぞれの一部区間を走行した場合のETC料金をまとめました。旅行をするときなどの参考にしてみてください。
北海道は土地面積も広く、広大な風景を眺めながらのドライブが楽しめます。
例えば、札幌~旭川鷹栖までの間の高速道路を軽自動車で走行するとしましょう。この場合、普通自動車が3,380円なのに対し、軽自動車は2,740円と640円も安くなります。
また、ETCの深夜や休日の割り引きに該当すると、さらに割り引かれます。
東名高速道路は、東京都~東海地方を通る日本の輸送・流通の大動脈です。1日に約40万台以上の利用数があるとされています。
ここも軽自動車ならお得に移動することができ、東京~名古屋間の料金は5,890円で、普通車よりも約1,400円安くなります。
また、ETCによる休日・深夜の割り引きに該当すれば4,120円になります。
名古屋と神戸を結ぶ名神高速道路は、日本初の本格的な高速道路で、東名高速道路にも接続しています。
名神高速道路を軽自動車で走ると、名古屋~京都南では高速料金が3,420円です。この料金は、普通車よりも800円ほど安い金額です。
さらにETCを使った各種割引に該当すれば、900円ほど割り引かれて2,400円になります。
四国地方は、高速道路の高松中央~松山間を軽自動車で走行した場合、3,160円で走行できる計算になります。普通自動車の場合が3,910円なので、これと比べると750円安くなります。
また、この場合もETCを搭載して休日・深夜の割り引きに該当すればさらに950円安くなり、2,210円になります。
九州地方の場合は、高速道路の福岡~鹿児島間を軽自動車で走行したとすると5,100円で走れる計算です。普通自動車の場合が6,330円なので、これと比べると約1,200円の差があります。
また、この場合もETCを搭載して休日・深夜の割引に該当すればさらに1,500円程安くなり、3,570円となります。
なぜ軽自動車の高速料金は安いのか
 車ごとの高速料金が決まる基準は3つあります。
車ごとの高速料金が決まる基準は3つあります。
- 車両が道路に与える負担・影響の大きさ
- 道路上でその車が時間・空間的に占める割合の大きさ
- 高速道路を利用するメリットの大きさ
この3つの基準に照らし合わせた結果として、軽自動車の高速料金は安く設定されています。それは軽自動車の特徴とも大きく関わっています。
普通の道路もそうですが、高速道路も多くの車が走れば走るほど表面が傷んで劣化していくため、車が安全に走行し続けるためには定期的なメンテナンスが必要です。
高速料金を支払うことで、メンテナンス費用を利用者が負担する形になっています。
そこで軽自動車の場合ですが、これは普通自動車と比べて車体が小さく、軽いため、道路に及ぼすダメージも少ないと考えられます。
このことから、軽自動車の所有者は高速道路に対するメンテナンス費用の割り当てが少なめで済んでおり、それが高速料金に反映されているのです。
軽自動車にもさまざまなボディタイプがありますが、車体の長さと幅は全て統一されており、普通自動車と比べてひと回り小さくなっています。よって道路に占める割合も小さいと考えられていることが、軽自動車の高速料金が安く設定されている2つめの理由です。
サイズの大きい車は、車体が道路内で占める割合が時間・空間的にも大きくなり、それだけ道路に負担をかけているとみなされます。その割合が、最終的には道路の維持管理のためのコストに関わってくることから、サイズが小さい軽自動車は高速料金も安く済んでいます。
軽自動車は、普通自動車と比べてエンジンが小さいためスピードが出にくく、時間短縮という点で普通車に劣ります。よって、高速道路を使うことで得られるメリットも少ないと考えられています。これが、軽自動車の高速料金が安い3つめの理由です。
そもそも軽自動車は街の中を走ることを前提に設計されており、高速道路は不向きとされています。もちろん、ターボ搭載の軽自動車を使ったり、エンジンを全開にして走ったりすれば時間は短縮できます。
しかし、軽自動車をそのように使うと燃費が大変悪くなり、結局デメリットの方が大きくなるでしょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
さらにお得に高速道路を利用する方法

このように、軽自動車は全国的に高速料金が安く設定されています。では、軽自動車や普通自動車に限らず、高速料金をさらに節約する方法はあるのでしょうか?
考えられるものとしては、インターネットによる経路案内や料金の早見表で安くなるルートを選択したり、ETCによる割引サービスをフルに活用したりする方法が挙げられます。
高速道路を使う前に、Webページで自分に合った経路を検索することができます。
最短ルートがいいのか、それとも最安ルートがいいのかという目的に合わせて、NEXCO3社のサイトで確認しましょう。
サイト内では、普通自動車の場合と軽自動車の場合とで切り替えることもできるので、きめ細かに調べることができます。
また、PDFで見ることができる早見表も便利です。いちいち検索せずとも一目で高速料金を調べられます。
料金所のスムーズな通過や支払いの利便性から、高速道路でETCを利用する方も多いでしょう。
ETCには専用の車載器とカードさえあれば適用される割引サービスもあります。このETC割引は、対象となる高速道路で条件を満たした状態で通行すれば自動で適用されます。
それはNEXCO3社が管理する道路のみ有効で、東京と大阪の郊外は対象外です。
具体的な割引サービスは、以下の4つがあります。
土曜・日曜・祝日と1月の2・3日は、普通車と軽自動車のみ、割引対象の高速道路の料金が30%割引となります。
毎日0時~4時の間に、割引対象の高速道路や一部の有料道路を使用すると30%割引となります。
対象となる高速道路を走行すると、通行料金と利用回数に応じてETCマイレージサービスとして還元されます。ただしマイレージサービスに登録しなければならないなどの条件があります。
圏央道などを対象に、ETC2.0を搭載した自動車が受けられる割引制度です。
この他、首都高速と東京高速の出入口を利用すると適用される「外環道迂回利用回割引」があります。
安くても高速道路の利用は無理をしない

軽自動車だと通行料金が安いとはいえ、高速道路の無理な利用は禁物です。
軽自動車で高速道路を走行する際の、5つの注意点を紹介します。
本来、軽自動車は高速道路での走行が前提とされていません。よって走行に時間がかかるため疲労がたまりやすく、こまめな休息が必要です。
「軽さ」が特徴の軽自動車は風圧に弱く、高速道路での移動時はなおさら風の影響を受けます。長い橋での走行や追い越された際などは要注意です。
軽自動車は小さいので大型車などから見えにくいため、十分な車間距離と安全速度が必要です。
タイヤ直径が小さいため、軽自動車は速度が上がるほど安定性が低下します。急なカーブや距離の長いカーブではスリップや横転の危険性が増します。
軽自動車は市街地を走行することを前提として造られているので、高速道路では無理がかかり燃費が悪くなります。給油のタイミングに気を付けましょう。








