車を購入するとなると、定期的に車検を受けることが義務付けられます。車検切れの車を公道で運転することは違法行為です。
車検は、お店に預ける方法や自分で検査を行う方法など、いろいろとあります。また、車検を受けるにあたって手続きの流れがあります。
いざ検査を受ける時にあたふたしないように、車検のやり方についてここで詳しく見ていきましょう。
車検の受け方の基本

まずは車検の基本的なことについて見ていきます。
車検には有効期限が設けられているため、期限切れの車を保有しているとどうなるか気になるでしょう。また、車検の有効期限は自分で確認することも可能です。
車検の有効期限についてと確認方法について見ていきましょう。
車検の有効期限をうっかり忘れた、実はこれだけで何らかの処罰を受けることはありません。問題なのは、車検切れの車を公道で運転することです。
もし車検切れのままで車を運転すると、無車検車運行で道路運送車両法違反の行為になります。行政罰で違反点数6点、さらに6か月以下の懲役もしくは300,000円以下の罰金と重たい罪です。
たとえ車検を通すため、ディーラーや整備工場に持ち込む際に車の運転をしても、違法行為になります。
車検切れの車を車検に通すためにはレッカーで移動するか、仮ナンバーを取得するかのいずれかで対処しなければなりません。手続き的にも面倒になるので、車検切れになる前に検査の申し込みをすべきです。

自家用車の場合、ほとんどの方が最初が3年後、それ以降は2年に一回のペースで車検を受けます。
ある程度の期間を置くので、愛車の車検の有効期限がわからなくなる方もいるかもしれません。車検の有効期限は自分で簡単に確認できます。
それは車検証で確認する方法です。車検証を見ると、「有効期間の満了する日」という項目があります。こちらに車検の有効期限の満了日が掲載されているはずです。
車検証は、車内で保管することが義務付けられています。車を使用する時など、運転する前に車検証で確認しておくといいでしょう。
また、ディーラーや整備工場で車検を通した場合、お店から有効期限が近づくと車検案内の通知が届くので、それで気付くというケースもあります。
車検を受けれる場所
車検の受付ですが、いろいろな場所が想定されます。そこで、ここでは主な車検を受けられる場所について紹介していきます。
それぞれ異なる特色があり、かかる費用も違ってきます。地理的な条件も加味して、自分にとってどこで車検を受けるのがベストか、検討してみましょう。

新車などをディーラーで購入した場合、こちらで車検を通すという方は多いです。
ディーラー車検の場合、メーカーの車を知り尽くしたメカニックが担当してくれます。たとえ部品が劣化していたとしても、純正パーツがあるのでしっかり交換してもらえます。
ディーラーの場合、メーカー保証もついてくるので車検後何か車に不具合が起きても、無償で修理してもらえるのもメリットです。
至れり尽くせりの丁寧なサービスが受けられる分、費用はかかってしまいます。それはディーラーによって変わってきますが、中には100,000円以上かかるケースも見られます。
他の車検を受け付けているところと比較して、数万円単位で高くなるでしょう。お金をかけてもいいので、しっかり整備してほしい方向けです。
自宅の近くに「○○整備」や「○○モータース」といったお店があるのを見たことがあるという方もいるでしょう。これがいわゆる整備工場で、車検の受付を行っているところも少なくありません。
整備工場で車検をお願いする場合、ディーラーと比較して費用を安くできるのがメリットです。
部品を交換する場合、ディーラーは純正の新品を使用するのに対し、整備工場はリサイクルのパーツを使用するなどコスト圧縮を行っています。
また、整備士の中には経験豊富なスタッフがいるかもしれません。ディーラーや大手のカー用品店で仕事をして、のちに独立している経営者もいます。
ただし、整備工場によって点検・整備の質はピンキリなので、しっかり見極めないといけません。少人数で回している場合、混んでいて思い通りに予約が取れないといった事態も想定できます。

カー用品店で日本全国にチェーン展開している大手を中心に、車検の受付を行っているところも少なくありません。
カー用品店の場合、部品が劣化していてもスムーズに交換できるのが強みです。お店の性格上、必要なパーツのストックを保有しています。中にはアフターサービスなどほかのサポートも充実しているお店が多いのも、メリットの一つといえます。
ただし、すべてのカー用品店が点検できる工場を完備しているわけではありません。自前の工場を持っていない場合、提携している工場に車を持ち込むため検査に時間がかかります。
また、整備士の技術力について整備工場同様、ピンキリなところも見受けられます。実績のある整備士が在籍しているか、事前にチェックしておくことが大事です。
ユーザー車検はお店に代行してもらうのではなく、自分で車を持ち込む検査方法です。運輸支局などに車を持ち込んで、所定の流れで検査をします。
自分で検査を行うので整備費用がかからず、ほかの車検のやり方と比較して低コストに抑えられます。
ただし、ユーザー車検はあくまでも検査を行うだけです。整備やメンテナンスは自分で行わないといけません。また、不合格だった場合は必要な整備をし直さないといけない点にも注意が必要です。
車好きで、日頃から車のメンテナンスをこまめに行っていて車検費用を安くしたいという方にはおすすめです。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検の受け方の流れ
初めて車検を受ける際、どんな流れで進められるのか不安に感じる方もいるでしょう。
上で紹介したように、車検を受けられる場所はいろいろとあります。細かな流れは若干お店によって変わります。
しかし、大まかな流れについては基本どこも一緒なので、車検のやり方についてここで紹介します。また、車検を受けるにあたって必要書類がいくつかあるので併せて確認していきましょう。
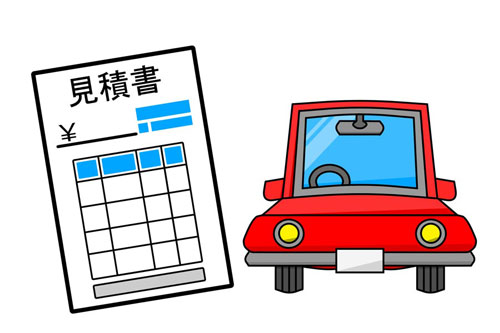
車検は検査を受ける車両や整備内容などによって、個々で費用が変わってきます。そこで自分の愛車の場合いくらかかるのか、まずは見積もりを取りましょう。
見積もりは、お店に車両を持ち込む他に、インターネットや電話でおおよその費用は把握できます。大半のお店で見積作成だけなら無料です。
もし自宅の周辺で車検を受けられるお店がいくつかあれば、複数のところで見積もりを取るのがおすすめです。お店によって同じ車両でも、車検費用は異なります。
複数で見積書を取って、その内容を比較します。料金や車検の内容など総合的に比較して、どこに検査をお願いするか決めましょう。

見積もりをして依頼する業者が決まったら、予約を入れます。
中には、お店が空いている時期など、当日いきなりお店に車両を持ち込んで車検を受けられるケースもあります。しかし、基本的にどの業者でも車検は事前予約となっているので手続きは済ませておくようにしましょう。
ちなみにユーザー車検の場合、事前予約は必須です。
繁忙期の際には、自分の思っている日付で予約が取れないかもしれません。そこで複数の希望日を設定して、第一希望がダメなら第二希望とスムーズに予約が取れるように準備しておいてください。
予約可能な期間はお店によって異なるので、事前確認しておくことをおすすめします。希望する日付の1か月くらい前から予約を受け付けているお店が多いようです。

予約が取れたら、車検を受ける際には必要書類がいくつかあるので準備しておきましょう。
車検を受ける際には以下の持ち物が必要です。
- 車検証
- 自賠責保険証
- 自動車税納税証明書
- 印鑑
もしこの中で紛失して見つからなければ、再発行手続きが必要になります。予約が取れたら、必要書類がきちんとあるか早めに確認しておくようにしてください。
また多くのお店で、車検費用は前払い方式をとっています。整備費用は後払いでも法定費用は前払いというところも多いので、必要なお金を用意しておきましょう。
法定費用の支払いは、基本的には現金払いですが、中にはクレジットカード払いに対応しているところもあります。現金が手元にない場合、クレジット決済ができるかどうか確認しておくと安心です。
車検を受けるにあたって必要な書類ですが、どこで受ける場合でも3つの書類は必須です。
まずは車検証です。正式名称は自動車検査証といって、車両の大きさや重量、排気量、所有者などの情報が記載されています。
車検証は「車の中で保管すること」と書かれているので、車内のダッシュボードなどに入っていることが多いです。
車検を受けて問題なく合格できれば、新しい車検証が発行されます。この車検証も引き続き、車内でしっかり保管しておきましょう。
もし車検証を紛失してしまったら、再発行手続きが必要です。再発行手続きは運輸支局で行えますので、速やかに申請をしてください。
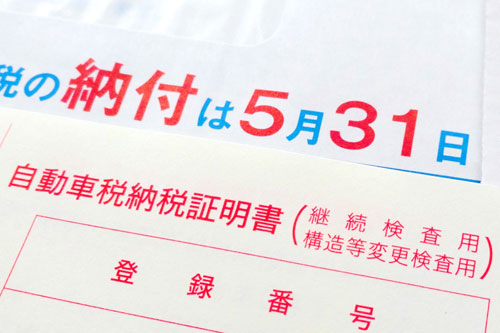
自動車を保有していると、毎年納税義務があるのが自動車税です。
毎年5月ごろに自動車税の通知書が自宅に届きます。その通知書を銀行やコンビニに持っていって納税すると、ハンコの押された半券が戻ってくるはずです。この半券が自動車税納税証明書です。
自動車税納税証明書は、車検の際に提出が義務付けられていました。しかし、平成27年から納税確認が電子化できたため、納税証明書の提出を省略できる場合もあります。
納税証明書の提出を省略できるのは、普通自動車のみです。
ただし、車検の時期が自動車税の納付時期の5月だとデータの繁栄に時間がかかる場合がありますので、証明書を用意しておいた方が安心です。
また、軽自動車は省略できないので、軽自動車をマイカーにしている人は注意が必要です。
自動車を運転するにあたって、自賠責保険への加入は必須です。「強制保険」とも呼ばれ、自賠責保険に入っていない状態で運転すると違法行為になります。
車検を受けるにあたって、自賠責保険に加入していることを証明する保険証の提出が義務付けられています。
ちなみに自賠責保険証も車で保管するよう義務付けられているので、車内にあるはずです。
もし自賠責保険証が見つからなければ、こちらも再発行手続きが必要です。加入している保険会社、もしくはその営業所で再発行手続きが行えます。
中には、どこの自賠責保険に入っているかよくわからないという方もいるかもしれません。その場合、たいていはその車を購入したディーラーや販売店で手続きしているはずなので、お店に問い合わせて確認しましょう。

必要書類が準備できたら、予約した日にちにお店に車を持ち込みます。この時、必要書類をお店の担当者に提出し、代金の支払いを済ませます。
お店に入庫できれば、あとはお店のスタッフのほうで検査や必要な整備をしてくれます。
いつ納車されるかは前もって言われるので、その日付に愛車の引き取りにお店に向かってください。
車のほかに新しい車検証と車検ステッカー、自賠責保険証も渡されるはずです。これらは速やかに車内に保管し、ステッカーは所定の位置に貼り付けておきましょう。
車検を土日で依頼した場合、車検証とステッカーは「後日お渡し」となる場合があります。
ディーラーや整備工場などお店に持ち込むと、引き取る際に車の状態について説明してくれるかもしれません。今後どんなところに注意して車を扱えばいいか、参考にしてみてください。
ユーザー車検のやり方
できるだけ車検の費用を安く抑えたければ、法定費用だけで済むユーザー車検がおすすめです。
ユーザー車検は自分で検査を行う方式なので、お店に預けるのと少しやり方が異なります。そこで、ここでは初めてユーザー車検を受ける方のために、大まかな流れについてみていきます。
ユーザー車検の場合、必要書類も異なりますので注意が必要です!

お店に車を預けて車検を通す場合、空いているタイミングであればいきなり持ち込んでも受け付けてもらえる場合もあります。
しかし、原則事前予約が必須です。ユーザー車検を受けるのであれば、まずは予約をしましょう。
普通自動車の場合は、「自動車検査インターネットシステム」というサイトで手続きができます。自動車検査インターネット予約システムで、ユーザー車検を希望する日付と場所を入力します。
ユーザー車検は運輸支局で行っているので、最寄りの支局を調べておいてください。また、運輸支局は平日のみ営業しているので、土日祝日はユーザー車検は行えません。
軽自動車の場合は、「軽自動車予約システム」の方で手続きを行います。
ユーザー車検を受ける際にも提出が必要な書類があるので、準備しておいてください。
- 車検証
- 自動車税納税証明書
- 自賠責保険証(新/旧)
- 印鑑
- 自動車検査票
- 自動車税重量税納付書
- 継続検査申請書
- 定期点検整備記録簿
ユーザー車検の場合、通常の車検とは違って「自動車検査票」「自動車税重量税納付書」「継続検査申請書」「定期点検整備記録簿」がプラスで必要になります。
自動車検査票と自動車重量税納付書と継続検査申請書は、当日運輸支局でもらえますし、ホームページからダウンロードすることも可能です。
また、自賠責保険証は自分で更新手続きを行わないといけません。そのため、新旧2枚提出しなければならないので、注意しましょう。
自賠責保険証の更新手続きは、保険会社のほかにも代書屋で手続きできます。代書屋は運輸支局の中や周辺にありますので、こちらで手続きしておいてください。

ユーザー車検の場合、当日まずは必要な事務手続きを行います。
自動車検査票と自動車重量税納付書、継続検査申請書を受け取り、必要事項を記入します。記入方法ですが、運輸支局内に見本があるはずです。見本を確認しながら作成すれば、まず問題なく進められるでしょう。
自動車重量税と検査手数料の支払いも済ませておきます。運輸支局場内に印紙・証紙販売窓口があるので、こちらで手続きをします。
自賠責保険の継続加入の手続きも済ませておきます。代書屋で手続きをする際には、今の自賠責保険証と車検証を持参するのを忘れないください。
自動車税納税証明書を、自動車税事務所などにある納税確認窓口に提示します。ここまでの手続きが完了すると、車検の受付が可能です。
ユーザー車検の場合、自動車に乗って所定の検査コースに従って受検します。案内に従って手続きを進め、電光表示器に「○」が点けば合格です。
もし初めてユーザー車検を受ける際には、その旨を受付の時に伝えることをおすすめします。係員がサポートしてくれたり、アドバイスをくれたりするところもあるようです。
検査コースに入る前に一つ注意点があります。タイヤのホイールキャップ、センターキャップは事前に取り外しておきましょう。
もしすべての項目で合格できれば、新しい車検証の交付を受けます。車検証交付窓口に書類一式を提出して、しばらくすれば車検証が交付されます。








