自賠責保険は、法律で公道を走行する全ての車やバイクが加入しなければならないと定められています。
通常は車やバイク購入時に加入し、車検時に更新しています。そのため、加入や更新手続きについて知っておくと役に立つでしょう。
また車の名義が変われば自賠責保険も名義変更手続きをしておいたほう良いと言えます。その他にも住所変更や改姓手続き、車を廃車にした場合の解約手続きなど様々な手続きがあるので、詳しい内容や手続きの仕方を紹介します。
自賠責保険は加入義務がある保険

自賠責保険は自動車損害賠償補償法という法律で、加入が義務づけられている自動車保険です。車を公道で走行させるためには必須です。
もし未加入のままの車を走行させると罰則が科される上に、交通違反で行政処分を受けることになり、1年以上の懲役もしくは50万円以下の罰金が科され、違反点数6点で免許停止処分となります。
自賠責保険には期限が設定されており、期限が近付くと更新手続きが必要です。更新しないまま放置すると保険の契約期限が切れて、保険自体が無効となってしまいます。
保険の期限切れの車は、たとえ過去に自賠責保険に加入していた事実があったとしても、未加入と同じ状態になってしまうので注意しましょう。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することを目的とした保険です。
自賠責保険がカバーする範囲は対人賠償に限定されており、事故によって被害を受けた人々に対する補償が行われます。自動車事故で被害者が死亡したり、負傷したりした場合に、自賠責保険で保険金が支払われるのです。
また、事故時に同乗していた人が被害を受けた場合も、被害者として保険の対象となる場合があります。
自賠責保険では、物損事故は一切補償の対象外となります。自賠責保険が対象とするのは、あくまでも人身事故による対人損害です。事故によって他人の車や建物などに損害を与えた場合、その修理費用や賠償金は自賠責保険から支払われることはありません。
物損事故についても保険でカバーされると思いがちですが、自賠責保険ではそのようなケースには対応していない点に注意しましょう。物損事故に備えるためには、任意保険に加入する必要があります。任意保険では、物損事故に対する補償を追加できるため、万が一に備えて加入しておくことが推奨されます。
交通事故でけがを負った場合、自賠責保険では医療費や治療費、休業損害、慰謝料などが補償されます。具体的には、診察や手術、入院などの治療に要した費用が全額補償され、さらに入院中の看護料や入院中の雑費、通院にかかる交通費なども実費で補償。
また、事故によって仕事を休む必要が生じた場合は、休業損害として1日あたり6,100円が支払われます。収入の減少がこの金額を超える場合は、証明書の提出により最大19,000円までの実額が補償されます。
事故によって精神的な苦痛を受けた場合には慰謝料も支払われる場合があるようです。1日あたり4,300円が基本額とされており、治療期間や実際の治療日数を考慮して補償額が決定されます。
自動車事故で後遺障害が残った場合、その障害の程度に応じて自賠責保険から補償が行われます。後遺障害が神経系統や臓器におよび、介護が必要な場合には、高額な補償が用意されているようです。
例えば、常に介護を要するような重度の後遺障害が残った場合、最高で4,000万円までが補償されます。一方、随時介護が必要な場合は3,000万円が限度額です。
その他の後遺障害に関しても、障害等級に応じて1級から14級までの基準が設けられており、最高で3,000万円から最低で75万円が補償されます。
後遺障害が原因で収入が減少した場合には、逸失利益としてその分も補償。障害の等級に応じて、労働能力喪失率と喪失期間に基づいて計算されます。
また、後遺障害による精神的な苦痛に対しても慰謝料が支払われ、最も重度の後遺障害である第1級の場合、1,650万円が支給されます。第2級では1,203万円となり、これに加えて初期費用として第1級で500万円、第2級で205万円が加算。その他の等級でも、等級ごとに定められた慰謝料が支払われる点を把握しておきましょう。
もしも交通事故の被害者が死亡してしまった場合には、葬儀費用や遺族への慰謝料、逸失利益が自賠責保険から支払われます。死亡による補償の限度額は3,000万円であり、これに基づいて各種費用が支給されます。
葬儀費用としては、通夜や祭壇、火葬、墓石などにかかる費用が100万円まで補償。さらに、被害者が将来的に得るはずであった収入が考慮され、逸失利益として支払われます。遺族に対しても慰謝料が支給され、請求者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円が支給されます。また、被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。
自賠責保険は事故の被害者やその遺族に対して重要な補償を提供する役割を果たしていますが、その補償内容や限度額には制限があるため、より大きな事故や損害に備えるためには任意保険への加入が必要です。
そもそも自賠責保険の加入対象車両は、自動車損害賠償補償法で道路運送車両法に規定された全ての自動車だと明記されています。
つまり、農業用に供する小型特殊自動車を除き、軽自動車や普通車はもちろん、大型バイクから原付まで大きさに関係なく二輪車も含まれます。
自賠責保険の保険料は車種によって異なりますが、離島などを除いて全国一律です。自賠責保険を扱う損害保険会社はいくつかありますが、どの保険会社を選んでも保険料に違いはないのでわかりやすいと言えるでしょう。
自賠責保険(正式には「自動車損害賠償責任保険」)は、すべての車両所有者に対して加入が義務づけられている保険です。自賠責保険は、万が一の交通事故の際に、被害者に対する最低限の補償を行うためのものであり、法律でその加入が義務付けられています。自賠責保険に加入していない、あるいは契約期限が切れたまま運転を続けると「無保険運転」とされ、重大な法的違反行為です。
まず、自賠責保険に未加入、もしくは契約の有効期限が切れた状態で車を運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。刑事罰に相当し、単なる行政処分ではありません。また、無保険運転を行った場合には、違反点数が6点加算され、自動的に免許停止処分(免停)となります。無保険運転は大変重い処罰が伴う行為であり、交通違反の中でも特に重大なものとされているのです。
さらに、無保険運転が発覚した場合、前科がつくこともあります。刑事罰の対象となるため、前科がつけばその後の生活に大きな影響をおよぼす可能性が高まるでしょう。就職や転職の際に影響を受けることもあるため、社会的な信用を失うリスクが非常に大きいのです。そのため、自賠責保険の更新時期には細心の注意を払い、保険の契約が切れないようにすることが大切です。
また、自賠責保険に加入している場合でも、証明書である「自賠責証明書」を携帯していない場合、別途罰則が科される可能性があります。自賠責証明書不携帯の状態で車を運転した場合、「30万円以下の罰金」が科されることが法律で定められています。自賠責証明書は、車検証と同様に常に車内に備えておきましょう。もし運転中に証明書を携帯していないことが発覚すれば、罰金だけでなく、警察官による指導を受ける可能性もあります。自賠責保険は加入だけでなく、証明書の管理も忘れずに行うことが大切です。
自賠責保険は、交通事故の際に被害者を救済するための最低限の補償を提供するものです。万が一、自賠責保険に加入していない状態で事故を起こした場合、被害者に対する補償ができなくなり、加害者として重い経済的負担を負うことに。被害者への補償は、自賠責保険がない場合、全額加害者が負担しなければならなくなるため、そのリスクを避けるためにも、自賠責保険への加入を怠ってはいけません。

自賠責保険の新規加入手続きは、簡単なので短時間でできます。
加入手続きは、自賠責保険を扱う損害保険会社の営業所や支店窓口で行います。他にもバイクや車の販売店、ディーラーやカー用品店、修理工場なども保険代理店となっているので、加入手続きが可能です。
必要書類を持参して加入申請を行えば即日に手続きが終わり、加入を証明する自賠責保険証明書が発行されます。
ただし、ガソリンスタンドの場合は自賠責保険証明書が即日発行できず、後日渡しになることもあるので事前に確認しておいてください。
また発行された自賠責保険証明書は車に携帯して運転しなければならないと法律で規定されています。不携帯の場合は30万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。無くさないように車検証と一緒に入れて、車内に保管しておきましょう。
普通車や軽自動車と250㏄を超えるバイクの自賠責保険は、1ヶ月から加入ができます。
自賠責保険は通常、購入時に3年間の保険期間で加入し、車検時に2年間の保険期間で更新します。購入から初回車検までは3年、2回目以降は2年ごとに車検を受けなければなりません。
自賠責保険は基本的に車検時に更新することになっているので、車検に合わせた保険期間となっています。
ただし、車検は期限の日付が変わるまで、すなわち24時まで有効です。一方で自賠責保険は期限の正午、12時を過ぎると無効です。すると12時間のタイムラグが生じるので、3年間や2年間より1ヶ月長い25ヶ月、37ヶ月で自賠責保険に加入し、更新する場合もあります。
自賠責保険の保険料は一部地域を除いて、車種ごとに決まっています。全国どこの保険会社で加入しても、保険料は変わりません。

自賠責保険の加入に必要な書類は、以下です。
- 契約対象車両の車検証
また既に自賠責保険に加入しており、自賠責保険が満期を迎えるので更新をしたい場合は、今現在契約している自賠責保険証明書も必要となります。
保険料に関しては車種によって異なるので、所有する車が該当する保険料がいくらくらいかを予め調べておくと、お金も準備しやすいでしょう。
小型バイクの自賠責保険申込方法

125㏄を超え250㏄以下の小型バイクや125㏄以下の原付も、車や大型バイクと同様に公道を走行するには自賠責保険の加入が必要となります。同じように未加入だと法律で罰せられる上に、交通違反で検挙されて免許停止処分が下ります。
125㏄を超え250㏄以下の小型バイクや125㏄以下の原付も、自賠責保険は同様に保険会社の営業所窓口やバイク販売店、修理工場やバイク用品店などで加入手続きが可能です。
ただし、125㏄を超え250㏄以下の小型バイクや125㏄以下の原付に限っては、車検がないのでコンビニでも加入手続きができます。
セブンイレブンでは店舗内のマルチコピー機、ローソンとミニストップはLoppi端末、ファミリーマートはFamiポートを使って加入手続きをします。
セブンイレブンやファミリーマートで手続きする場合は、事前にネットで予約すればスムーズに手続きできるでしょう。店舗で保険標章(ステッカー)や自賠責保険証明書がもらえるのでとても効率的です。
バイクの場合は、ステッカーをナンバープレートの指定場所に貼らなければなりません。自賠責保険の保険期限が記載されているので、ナンバープレートを確認すればいつ自賠責保険が切れるかをチェックできるので便利です。
原動機付自転車や250cc以下の軽二輪自動車に関しては、自賠責保険の加入手続きを手軽に行うことが可能です。
これらの車両は、24時間365日対応可能なコンビニエンスストアやインターネットを利用して、いつでも自賠責保険に加入できます。
インターネットから自賠責保険に加入する手順は簡単で、スマートフォンやパソコンを使用して完結できます。手続きの流れは以下の通りです。
1.スマートフォンやパソコンで事前申込みをする
まず、保険会社のウェブサイトにアクセスし、自賠責保険の申込フォームに必要事項を入力します。車体番号や住所、氏名、生年月日などの基本情報を入力し、申込みを完了します。
2.事前申込み完了メールを確認する
申込みが完了すると、指定したメールアドレスに「申込み完了メール」が届きます。このメールには、保険手続きを進めるためのURLや、コンビニで手続きをする際に必要な申込券印刷コード、もしくはQRコードが記載されています。
3.申込券印刷コードをコンビニで使用する
コンビニに設置されたマルチコピー機にて、事前に送付された申込券印刷コードを入力するか、QRコードを読み込ませて申込券(払込票)を発行します。
4.レジで支払い、ステッカーを受け取る
発行された申込券をコンビニのレジで提示し、保険料を支払います。その場でステッカーが渡されます。同時にマルチコピー機で保険証明書も印刷しておくことが重要です。
なお、スマートフォンからの申し込みの場合、完了メールに記載されたバーコードをコンビニのレジで提示するだけで手続きが完了します。この方法では、マルチコピー機での申込書の印刷は不要で、よりスムーズな手続きを行うことが可能です。
コンビニで直接自賠責保険に加入する場合も、簡単な手続きで利用可能です。ただし、注意点として、マルチコピー機が設置されている店舗に限られる点を理解しておく必要があります。以下は、コンビニでの加入手続きの手順です。
1.コンビニのマルチコピー機で直接申し込む
インターネットで事前手続きを行わない場合、コンビニに設置されているマルチコピー機を使用して手続きを進めます。マルチコピー機のメニュー画面から「バイク自賠責保険」の加入ページを選択し、画面の指示に従って情報を入力します。
2.申込券(払込票)を発行する
マルチコピー機の操作が完了すると、申込券(払込票)が発行されます。申込券を持ってレジに向かいます。
3.レジで支払い、ステッカーを受け取る
申込券をレジで提示し、保険料を支払います。その際に、自賠責保険のステッカー(保険標章)を受け取ります。また、マルチコピー機で保険証明書を印刷する必要があるため、忘れずに行いましょう。
コンビニで直接申し込む場合、手続きに時間がかかる可能性があるため、スマートフォンやパソコンを使って事前に手続きを済ませておくと、マルチコピー機での操作が少なく済み、スムーズに保険加入が完了します。
原付や軽二輪の自賠責保険は、インターネットやコンビニのマルチコピー機を利用することで、簡単に手続きを完了できます。忙しい日常の中でも手軽に保険加入を済ませられるため、利用者にとって大変便利な方法といえるでしょう。
125㏄を超え250㏄以下の小型バイクや125㏄以下の原付の自賠責保険の保険期間は、1ヶ月単位での加入はできません。最短でも12ヶ月からの加入になります。
車や250㏄を超えるバイクは車検を通す関係で、短期の自賠責保険に加入しなければならない場合もあります。しかし、125㏄を超え250㏄以下の小型バイクや125㏄以下の原付は車検がないので、1ヶ月からの自賠責保険は特別必要ありません。
また、最長保険期間は車や250㏄を超えるバイクより長い、60ヶ月を設定することも可能です。
車検がないとどうしても更新するのを忘れがちなので、保険期間を長めに設定しておけば当分更新しなくても良いので効率的だと言えるでしょう。

125㏄を超え250㏄以下の小型バイクの自賠責保険に加入する際は、以下の持ち物が必要です。
- 軽自動車届出済証
- 既に自賠責保険に加入していれば今の自賠責保険証明書
原付の自賠責保険に加入する際は、以下の持ち物が必要です。
- 標識交付証明書
- 既に自賠責保険に加入していれば現在の自賠責保険証明書
また保険期間をどのくらいにするかを決め、予め保険料を調べて準備しておくと良いでしょう。

車検のある車や250㏄を超えるバイクの場合、自賠責保険の更新は車検時に一緒に行うのが一般的です。
まずは車購入時に自賠責保険に加入します。その際に自賠責保険の保険契約期間はちょうど初回の車検の時期、つまり3年後に合わせて設定されているはずです。
初回の車検時に2回目の車検となる2年後に自賠責保険も満期を迎えるように、保険契約は2年更新になっているでしょう。
ただし、車検の場合は整備不良により1回で検査に通らないことがあります。そうなると整備をやり直してから再度車検を受けることになるので、その間に自賠責保険が期限切れとなってしまうかもしれません。そうなると自賠責保険だけ更新か、再加入という面倒な手続きをしなければならなくなります。
その手間を省くために、自賠責保険は通常1ヶ月ほど保険期間に余裕を持たせている場合が多いです。2年だと24ヶ月ではなく25ヶ月、3年だと36ヶ月ではなく37ヶ月で保険期間が設定されているでしょう。
125㏄を超え250㏄以下の小型バイクには車検がありません。
車などは車検のタイミングで自賠責保険も期限が切れるように設定されているので、車検を受ければ自賠責保険も更新できます。ディーラーなどから車検の案内などが郵送されてくるので車検は忘れにくいものです。
しかし、車検がないと自分で自賠責保険の有効期限がいつまでかを覚えておかなければいけません。有効期限をうっかり忘れて自賠責保険が期限切れのまま公道を走行すると、法律違反で罰則と行政処分が科されます。その上、交通事故を起こしてしまっても補償されず保険金も下りません。
小型バイクは自賠責保険に加入すると、有効期限が表示された保険標章というステッカーを発行され、ナンバープレートに貼ることになっています。ステッカーを時々確認しながら、保険期限をチェックしておくと良いでしょう。
車を譲渡、売買したら自賠責保険は名義変更手続きを

車を譲渡したり、売却したりすると車自体の名義が変わります。車の名義変更を行うのと一緒に、自賠責保険も名義変更手続きをしておいてください。
自賠責保険は車を識別する車台番号をもとに、保険を適用するかを判断します。いわば車に付随する保険です。
そのため保険契約者と実際に運転者が違った場合でも、交通事故により自賠責保険で対応できる損害が発生したら保険金は下ります。それなら名義変更手続きをしなくても問題ないのでは?と思われがちです。
確かに法律的にも問題なく、保険も適用されますが色々とトラブルが起きる可能性があります。
例えば自賠責保険の更新の通知が前の契約者の住所地へ郵送されるので、更新をうっかり忘れるリスクがあります。また、交通事故を起こした際に保険は適用されますが、保険契約者と運転者が異なると手続きがスムーズに進まず、時間を要すると考えられます。
自賠責保険の名義変更手続きは簡単なので、忘れないうちに済ませておいたほうが賢明だと言えるでしょう。
手続きは加入先の保険会社の営業所窓口で行います。必要なものは手続きをする人によって異なりますが、共通するのが現在の自賠責保険証明書です。
更に、譲渡人が手続きする際は印鑑証明書もしくは車の譲渡や売買を証明する書類、譲受人の印鑑が押印された自賠責保険承認請求書が必要となります。印鑑証明書を持参する場合は、自賠責保険承認請求書には印鑑証明書の印鑑を押印しておいてください。
また譲受人が手続きする際は、自身と譲渡人の印鑑が押印された自賠責保険承認請求書と車の売買や譲渡が証明できる書類を持参します。自賠責保険承認請求書は事前に保険会社に連絡して郵送してもらいましょう。
譲渡人と譲受人双方が手続きに出向く場合は、双方が印鑑を持参すれば事前に取り寄せなくても、窓口に置いてある自賠責保険承認請求書に押印できます。あとは譲渡人の印鑑証明書もしくは車の売買や譲渡を証明する書類となります。

自賠責保険に加入すると発行される自賠責保険証明書には、契約者の氏名や住所が記載されています。自分が引っ越したり、結婚や離婚により名字が変わると記載内容と現在の氏名や住所が異なってしまうので、住所変更や改姓手続きを行ってください。
住所変更や改姓手続きをしておけば、万一の事故の際も手続きがスムーズであり、自賠責保険更新の通知も住所地にきちんと届くので安心です。
住所変更や改姓手続きは加入している保険会社の営業所窓口にて手続きを行います。
- 自賠責保険証明書
- 契約者の印鑑
- 自賠責保険証明書
- 改姓後の印鑑
- 運転免許証や戸籍抄本などの改姓を証明する書類
保険会社の営業所へ出向く時間がない場合は、サポートデスクに電話すると手続きに必要な書類が郵送してもらえるので、必要事項を記載して返送すれば手続きが可能です。
ただし、保険会社によっては車検証の原本の郵送を請求される場合もあるので、その際はコピーをとって手元に置いておきましょう。
自賠責保険に加入すると車台番号や保険の有効期限、契約者の住所や氏名などが記載された自賠責保険証明書が発行されます。自賠責保険に加入しているという証明になるので、車に携帯しなければならないと自動車損害賠償保障法でも明記されています。
しかし、ふと気づくと紛失していたというケースもあるかもしれません。紛失したまま、つまり不携帯で車を公道で走行させると法律違反で罰せられるので、早急に再発行手続きが必要となります。
再発行は保険会社の営業窓口で手続きを行います。再発行には契約者の印鑑と、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
営業所の窓口においてある自賠責保険証明書再交付申請書に必要事項を記入し、押印して本人確認書類を提示すれば手続きは完了します。即日新しい自賠責保険証明書が再発行されるので持ち帰ることができます。

自賠責保険証明書を確認すると、車台番号や契約者の氏名、住所、保険期間が間違って記載されている、記載漏れがあるというケースもあります。また、保険料が納められたことを示す収納印が押されていないケースも考えられます。
このように、記載ミス等があった場合は正しい内容に訂正してもらうことが必要です。特に車検を受ける際は、自賠責保険に加入しているかを証明書の内容で確認します。
記載ミスが見つかれば車検証が発行されないこともあるので、車検を通すのに時間がかかります。しかし、自賠責保険加入の事実があれば、交通事故の際に自賠責保険の補償対象内で保険金が下りますが、手続きに時間を要するので早めに訂正手続きをやっておきましょう。
手続きは保険会社の営業所窓口に出向いて行います。事前に連絡し必要な書類等を確認してください。
自賠責保険は車に付随する保険なので、廃車にした場合は解約手続きをすれば、残存保険期間によっては保険料が還付されることがあります。
保険料は前払いしていますが、日割りではなく月割りなので保険期間が残り1ヶ月未満では保険金の還付はありません。また、2ヶ月保険期間が残っていても返戻金は1000円未満と少ないこともあります。
予め保険残存期間と返戻金を調べ、手続きに見合うだけの額が返還されるかを確認しておくのがおすすめです。
大体1年以上保険期間が残っていれば、1万円ほどは還付されます。保険料の払い戻しのために解約手続きを行うには、自賠責保険証明書と廃車が証明できる書類、印鑑と返戻金振込先の口座番号が必要です。
原付など車検のないバイクの場合、ステッカーも準備してください。解約手続きは保険会社の営業所窓口のみで扱っています。
解約日を起点として返戻金の計算がなされます。解約日は解約手続きが完了した日になるので間違えないようにしましょう。
また郵送による手続きもできますが、時間を要するため解約日がずれ込む可能性があることは予め承知しておく必要があります。
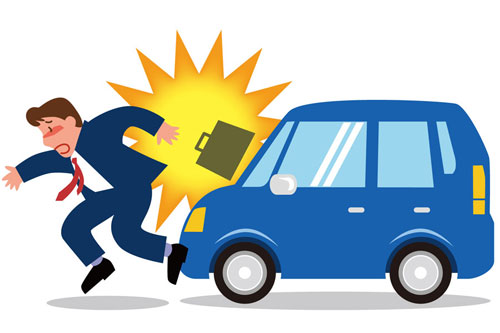
自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的とした自動車保険です。そのため、交通事故の被害者が受けた損害のみを賠償します。
具体的には、以下の3つのケースに分けて補償されます。
- 被害者が亡くなった場合
- 被害者がケガをした場合
- 被害者がケガにより後遺障害を負った場合
対人補償といっても無制限ではなく賠償限度額が決まっており、限度額を超えた部分は加害者の自己負担となるでしょう。
交通事故で被害者が亡くなるもしくは重い後遺障害を負った場合、かなり高額の損害賠償を請求される場合もあり、そうなると自賠責保険でカバーしきれない場合もあります。
また、加害者となった運転者が死傷した場合の補償はありません。交通事故により車や店舗、ガードレールや電柱などの物が壊れた際の対物補償も対象外です。
自賠責保険の保険金請求方法

交通事故により被害者が死傷した際は、加害者の自賠責保険から損害に対する補償がされます。自賠責保険は支払限度額や支払い基準も決まっています。
自賠責保険は通常は加害者が自分の加入している自賠責保険に保険金を請求し、被害者へ賠償を行う仕組みです。しかし、加害者によってはなかなか請求しない場合もあります。
被害者はその間も治療費や入院費などがかかっており、出費がかさんで経済的な負担が大きくなります。そうなると、自賠責保険の被害者救済という目的が果たせなくなるため、加害者からの請求だけではなく被害者からも必要に応じて治療費などに相当する保険金請求ができるシステムになっているのです。
加害者請求の流れは以下になります。
- まずは加害者が被害者に損害賠償金を支払った後で保険会社に保険金を請求します。
- 請求書などの必要書類を保険会社に提出すると、保険会社は書類を確認して損害保険料率算出機構の調査事務所に書類を送付します。
- 損害保険料率算出機構は、自賠責保険の保険料基準利率の算出や、全国に自賠責損害調査事務所を構えて、自賠責保険請求の適確性を調査するための団体です。この調査事務所で事故の発生状況や事故と損害の因果関係、保険金支払いの妥当性を調査します。
- 調査結果を保険会社に報告し、支払額が決定した後に保険金が支払われます。
被害者救済の目的を重視しているので過失相殺に関して厳格ではありません。ただし、被害者に100%過失がある場合、例えば車同士の衝突で被害車両がセンターラインを大幅にはみ出してきた場合などは、保険金の支払いが認められないこともあります。

交通事故が起きても、加害者の納得が得られずになかなか被害者に損害賠償金を支払ってくれないケースもあります。そんな場合は被害者から、自賠責保険の保険会社に損害賠償金を請求することが可能です。
交通事故による総損害額が決まらなくても、被害者請求の場合は被害者が病院へ治療費などを支払ったらその度に、何度でも損害賠償金の支払いを請求することができます。
通常、運転者は自賠責保険の他に、任意の自動車保険にも加入している場合がほとんどです。交通事故を起こすと加害者はまず任意保険の保険会社に連絡します。これは、任意の保険会社は本人に代わって被害者側と示談交渉をしてくれるからです。
補償を行う場合、まずは自賠責保険が適応され、補償がカバーしきれない部分を任意保険で補う形をとります。
任意の保険会社はまず必要な損害賠償金を被害者に支払い、その後自賠責保険の適応部分の損害に関しては賠償金を自賠責保険に請求するという流れです。
これは一括払い制度と言われ、請求の二度手間を防ぐためによく使われています。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自賠責保険の様々な手続きを知っておこう

自賠責保険は加入が義務づけられている強制保険なので、まずは車やバイクの購入時に加入手続きを行います。
ただし車検のある車やバイクは次回の車検までが自賠責保険の期限となっています。車検時に更新手続きして、保険期間が更新されているか確認しておいてください。
車検のない原付などは、更新を忘れがちです。ナンバープレートに貼付する保険標章の期限をチェックしながら、早めの更新手続きがおすすめです。
また、ライフスタイルの変化に応じて、自賠責保険の各種変更手続きが必要となる場合もあります。
- 車の譲受や売買に伴う名義変更や引っ越し
- 結婚や離婚による住所変更や改姓の手続き など
また車を廃車にした場合、残存保険期間によっては前払いした保険金が戻ってくることもあるので、解約手続きが必要になります。
自賠責保険に関する様々な手続きの仕方は役に立つので知っておきましょう。








