ハイブリッド車は補助金の対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。外部充電のできないハイブリッド車は補助金の対象外であり、EV車やプラグインハイブリッド車、水素自動車などがクリーンエネルギー自動車促進補助金の対象です。
この記事では、プラグインハイブリッド車の場合の受け取れる補助金について詳しく解説します。補助金を利用する際の注意点や知っておきたいポイントも紹介しているため、参考にしてみてください。
ハイブリッド車は補助金が利用できるのか解説

ハイブリッド車といっても外部充電ができるプラグインハイブリッド車であれば新車購入時に国からの補助金が受け取れます。しかし、補助金の利用には交付条件や処分制限期間などさまざまな注意点があります。
プラグインハイブリッド車のほかにEV車や水素自動車なども補助金が受け取れますが、車種や性能によって補助金額に違いがあるため利用時には注意が必要です。
この記事を最後まで読むことで、受け取れる補助金の具体的な金額や事前に知っておきたいポイントなどについて理解することが可能です。クリーンエネルギー自動車の購入を検討中の方は、ぜひ記事の内容を参考にしてください。
ハイブリッド車(HEV)は補助金の対象外
「ハイブリッド車」といっても外部充電のできないハイブリッド車(HEV)は補助金が受けられません。
対象となるのは、外部充電ができるプラグインハイブリッド車(PHEV)です。そのほかに、電気自動車(EV車)や燃料電池自動車(水素自動車)などが補助金の対象に含まれます。
現在国が設けているクリーンエネルギー自動車の補助金は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)というもので、新車のみが対象です。
CEV補助金は、環境性能の高い車の普及と促進を目的に取り組まれており、これを利用することで高価であるクリーンエネルギー自動車に手が届きやすくする効果があります。
プラグインハイブリッド車の場合は補助金がいくら貰えるのか

プラグインハイブリッド車はまだ種類も限られていますが、ハイブリッド車に比べてもさらに高い車両価格となっています。プラグインハイブリッド車の購入を検討している方にとって、数十万円の補助金の存在は、背中を押してくれるものでしょう。
ここからは、プラグインハイブリッド車の場合はいくら補助金が貰えるのか解説します。
補助金の上限は、車種や性能によって分けられています。乗用車に関しては、基本の補助金は55万円で、加算額5万円を合わせると60万円です。
この加算額は、環境負荷の低いグリーンスチールという鋼材を車を造るなかで採用したメーカーに設けられた加算措置です。
それぞれの補助金額の上限は2024年度から変わらず、プラグインハイブリッド車以外のEV車で85万円、水素自動車で255万円になります。
「トヨタ・プリウス」のハイブリッド車とプラグインハイブリッド車を比較すると、車両価格の差は約73万円です。60万円の補助金があると、プラグインハイブリッド車も選択肢のなかに入れられる可能性も出てくるでしょう。
補助金制度を設けている背景には、環境性能の高い自動車の普及と促進の狙いがあります。世界的な課題となっている環境問題は、自動車による影響も大きな原因のひとつです。
日本では2035年までに新車販売する車は100%電動化にすることを目標に掲げており、多くのメーカーからクリーンエネルギー自動車が販売されています。
ユーザーのなかには、車の乗り換え時にクリーンエネルギー自動車が気になっていても車両価格の高さから手が延ばせない方も多いでしょう。このような方が金銭的負担を理由に諦めることを減らせるように補助金制度が設けられています。
国が設けているクリーンエネルギー自動車の補助金は1種類ですが、そのほかに自治体が独自に行っている場合もあります。国の補助金では決められた年数の保有義務があったり、中古車・新古車は対象外だったりしますが、自治体によってはこのような条件・内容が異なるケースもあり、よく調べておくことが重要です。
とくに国の補助金が使えないからと諦めている方は、自治体の補助金制度もそのまま確認せずに流してしまわないよう気をつけましょう。国の補助金と自治体の補助金を併用できる可能性もあるため、当てはまる制度がないか要チェックです。
現在の補助金の対象車には、EV車やプラグインハイブリッド車、水素車などの燃料電池自動車が含まれています。
補助金の対象車は変更される可能性があるため、最新情報を確認しておきましょう。
補助金を利用する際の注意点

補助金を受け取って車を購入する場合、対象は新車限定だったり交付条件が毎年更新されていたりと、いくつかの注意点があります。
申請の受付は先着順であり、予算に達した時点で受付は終了してしまうため、最新情報はディーラーで確認することが重要です。
ここからは、補助金を利用する際の気をつけるべきポイントについて紹介します。
国が設けるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金は、限られた資金のなかで分配されており、予算に達した時点で受付は終了となります。2024年度の予算は1,291億円であったのに対し、2025年度の予算は1,000億円であり、減額されていることが分かります。
予算金額だけで見ると多額の予算を準備していることが分かりますが、多くのクリーンエネルギー自動車の購入者が受け取っていることを考慮するとすぐに底をついてしまうことが予想できるでしょう。
申請の受付は先着順であるため、購入と補助金の利用を決定した際にはスムーズに申請できるようにしておくことが重要です。
CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)と、各自治体が行っている独自の補助金制度に共通して、毎年交付条件や補助金額が異なる可能性があります。
もちろん据え置きにされるケースもありますが、「去年はこうだったのに…」とならないように注意が必要です。
車の購入は人生のなかで家の次に高い買い物といわれており、慎重に選ばなくてはいけません。しかし、慎重になり過ぎて購入を先延ばしにしていると、交付条件に当てはまらなくなったり補助金額が減額されたりするおそれもあります。
勢いだけで車の購入を進めてしまうことはリスクが高いですが、計画を立てて購入に踏み切ることも重要です。
CEV補助金が受けられる対象は新車購入時のみであり、中古車や新古車は対象外です。これは、EV車やプラグインハイブリッド車、水素自動車の普及が目的であることから、中古車市場に流通している車には適用されません。
中古といえど、クリーンエネルギー車は市場価値が高く、そこまで安価な価格では販売されていないでしょう。もちろん車の状態によっても異なりますが、新車で補助金を使って購入するか、中古車を選ぶかはよく比較して検討する必要があるでしょう。
なお、各自治体が独自で行っている補助金であれば中古車でも使える可能性があります。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金は、毎年予算や交付条件などが更新されています。しかし、ネット上には最新情報も数年前の古い情報も混在しており、なかには誤った情報も流れているため注意が必要です。
正確な情報を知るには、ディーラーで直接、担当スタッフに確認することがおすすめです。車の購入時には、不明点は相手の顔色を気にせずにしっかりと確認し、解決しておきましょう。基本的にスタッフは車を購入して欲しいため、丁寧に対応してくれます。
もし質問して不満な感情を表に出すような担当者だと、今後も気持ちよく取引ができないおそれがあり、避けておくのが無難です。補助金のことを含めて、不明点はしっかりと解消させておくのがポイントです。
なお、これは国が設けているCEV補助金の金額であるため、各自治体が独自で行っている補助金制度を併用するとより多額の補助金が受け取れるでしょう。
国が実施する補助金について知っておきたいポイント
補助金を利用するとなると、一定の保有義務があったり、補助金が利用できる対象の車が限られていたりすることに気を付けなければいけません。
仮に補助金を利用して車を購入したにもかかわらず、無断ですぐに売却した場合には補助金の返金が求められるケースもあります。
ここからは、国が実施する補助金について知っておきたいポイントを紹介します。
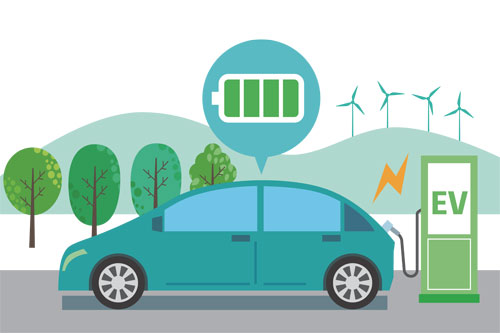
CEV補助金の対象車は、EV車(電気自動車)、水素自動車(燃料電池自動車)、プラグインハイブリッド車です。
EV車と水素自動車は、モーターの力で車を動かしており、エンジンは搭載していません。排気ガスを出さず、環境性能に優れています。
プラグインハイブリッド車は上記の車とは異なり、モーターに加えてエンジンも搭載していることが特徴です。しかし、ハイブリッド車に比べてエンジンの駆動率は低く、主にモーターを使って走行しています。
このような車は車両価格が高いため、普及を加速させる目的で補助金制度が設けられているのです。
本来、CEV補助金の目的はガソリン車に比べて高価なEV車・プラグインハイブリッド車などを手の伸ばしやすい価格にして普及させることです。そのため、高級車に対しても同等の補助金を分配することが疑問視されていました。
結果的に現在では、メーカー希望小売価格が840万円(税抜き)以上の高級車は、通常の補助金額の8割しか受け取れない仕組みになっています。
受け取れる金額の2割減になってしまうため、高級車にあたる車を購入予定の方は注意が必要です。
車を購入するのではなく、新車を一定期間レンタルする契約を結ぶカーリースでもCEV補助金の利用が可能です。利用には条件があり、処分制限期間(3~4年)以上の期間でのリース契約であることが必要です。
CEV補助金を受け取るには、申請をリース会社でなく車を利用する契約者が申請する必要があります。慣れない補助金申請は不安に感じる方もいるでしょうが、補助金を利用したい旨をリース会社の担当者に伝えると書類の準備などサポートしてくれます。
分からないことがあれば、そのままにせず知識のある方に尋ねるのがスムーズに補助金を受け取るためのポイントです。

CEV補助金を利用して購入した車は、一定期間の保有義務があります。これを「処分制限期間」といいますが、乗用車の場合は4年間の保有が義務付けられており、無断で売却してしまうと補助金額の返納が求められてしまうため注意が必要です。
もし、何らかの理由があって保有義務期間中に車を手放すことになった場合は、事前に次世代自動車振興センターにて手続きを行い、承認をもらわなければいけません。
順序を守らずに車を手放し、さらに返納にも応じなかった際には、返納金に加えて延滞金が発生してしまいます。信用情報機関にも情報が残ってしまうため、くれぐれも返納滞納は行わないようにしましょう。
国からの補助はありませんが、各自治体で補助金制度がある可能性もあるため、設置前に調べておきましょう。
補助金の申請方法と必要書類
CEV補助金の申請は、新車購入の際はディーラーの担当者が代行して手続きを行ってくれます。しかし、カーリースを利用する際は申請者は契約者と定められていることから、自分で手続きを行わなければいけません。
申請方法は、新車登録日から1ヶ月以内に必要な書類を揃えて、郵送かweb申請を行います。必要書類は、「交付申請書」「申請者・申請車両の確認書類」「車両代金の支払い証明書」などです。
審査に無事通過できれば、交付額が記された「補助金交付決定通知書」が送られてきます。
なお、補助金を受け取るには申請する時点で車の支払いが済んでいる必要があるため、一旦は全額を支払わなければならないことに気をつけましょう。
ハイブリッド車の購入時に補助金を使う魅力
あらゆる決まりがありますが、購入を検討している車が補助金の対象車であるなら、補助金の利用をおすすめします。
補助金は高額であることから、初期費用を抑えられて、費用を自宅の充電環境の設置に充てたり、より高いグレードのモデルを選べたりするでしょう。
ここからは、ハイブリッド車の購入時に補助金を使う魅力について紹介します。
補助金が受けられる分、初期費用の出費を抑えられることが最大の魅力です。
車を購入する際、予算を立てて計画的に車を選ぶ方が大半でしょう。EV車やプラグインハイブリッド車に魅力を感じていても、車両価格の高さから購入を断念している方は、補助金を受け取れることで購入に踏み切れる可能性が上がります。
環境性能に優れた車の普及や促進を目的としているため補助金も高額であり、従来の車両価格によっては補助金の額を差し引くことでエンジンを搭載した車とさほど変わらない金額で購入できるものもあります。
EV車やプラグインハイブリッド車、水素自動車に興味がある方は補助金のある今がチャンスといえるでしょう。
CEV補助金の対象車を選ぶということは、環境性能に優れた車を選んでいることであり、環境問題への取り組みに貢献したことになります。環境問題への自動車が与える影響は大きいとされており、1人ひとりの意識がとても重要です。
国は2050年までのカーボンニュートラル実現を宣言しており、その取り組みとして2035年までに乗用車の新車販売で電動化100%を目指しています。近い将来、自動車市場は「電動が主流」といった状態になっている可能性もあります。
ひと足早く自動車の電動化を取り入れられることは、魅力の一つだといえるでしょう。
自宅に充電環境を整えるとより快適になる
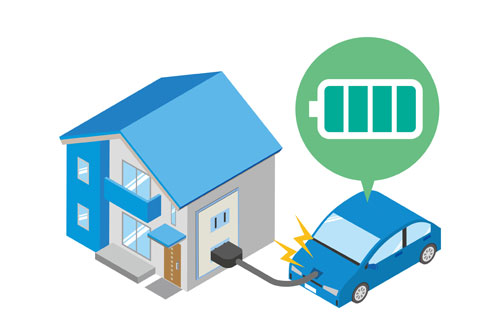
近頃、建売の一軒家には、既に電気自動車の充電設備が設けられているケースもあります。個人宅に利用できる補助金システムはありませんが、自宅に充電設備を備えておくと、帰宅したタイミングで充電ができ、翌朝には充電ができている状態で出かけられることが魅力です。
充電設備のあるスポットは、ガソリンスタンドほどまだ多くなく、充電時間もガソリンを給油するよりは長くかかってしまいます。このようなことからも、自宅で充電ができると、充電できる場所を探して充電時間にヒマを潰す手間や時間が省けます。
より快適性を上げるなら、自宅への充電設備を設置することがおすすめです。
環境性能が高い車は税制優遇も受けられる

EV車、プラグインハイブリッド車、水素自動車などは購入時の補助金に限らず、自動車税や環境性能割などの税金面でも優遇措置が受けられます。
それぞれの減税措置は車の環境性能によって異なり、車の購入時に納税が必要な環境性能割は上記の車は非課税となります。さらに、自動車税を軽減するグリーン化特例も対象です。
補助金が受けられるだけでなく、減税措置もあることで維持費の節約に繋がります。
補助金と同様に減税措置も対象や内容が毎年変更される可能性があるため、購入前にディーラーで最新情報を確認しておくと安心です。





