車を一時的に手放すけれど、これまで積み上げてきた等級が高い場合、自動車保険の解約をするのがもったいないと感じる方も多いのではないでしょうか。
自動車保険には中断証明書があり、希望者は申し込みを行うことで取得が可能です。中断証明書があると、自動車保険に再度加入するときに、これまでの等級を引き継げます。
この記事では、自動車保険の中断証明書について、その役割や発行条件について詳しく解説します。注意点もまとめているので、参考にしてください。
- 自動車保険の中断証明書は、高い等級を保持しておける仕組みで、希望者にのみ発行されます。
- 中断証明書の発行条件は、解約時点での等級が7~20等級で、解約日の翌日から5年以内に行う必要があります。
- 中断証明書を発行するには、車両廃車や譲渡などの正当な理由が必要です。
- 自動車保険を解約してから中断証明書の発行の申し込みを行います。
- 中断証明書を発行するには、中断理由によって必要な書類が異なります。
- 手数料はかからず手続きも簡単なため、発行を迷うなら申し込んでおくことがおすすめです。
自動車保険の中断証明書により保険料の節約が可能
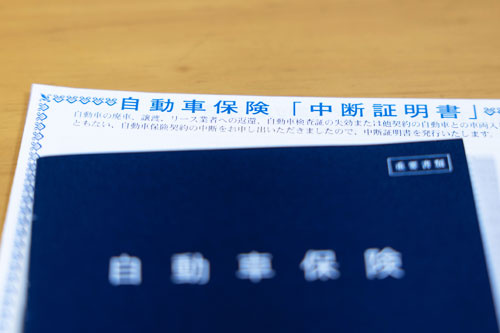
車を手放したり、海外に行ったりなどの理由で、一定期間車を使用しない場合には、自動車保険を解約してしまうのではなく中断証明書を取得しておくことがおすすめです。
自動車保険を一度解約すると等級がリセットされてしまいますが、中断証明書があれば解約時の等級をキープした状態で再開できます。
等級は保険料に大きく影響するため、再び車を使用する予定がある場合には、中断証明書の取得が保険料の節約に役立つでしょう。
自動車保険の中断証明書とは?
中断証明書とは、契約を中断する際に解約時の等級を、再び自動車保険に加入したときに引き継げる書類です。自動車保険を解約する際、自動的に配布される書類ではないため、希望する場合には保険会社に対して申し込みを行う必要があります。
自動車保険の等級は、保険料に大きく影響するため、等級が上がっている方にとって今後の保険料を節約する有効な手段だといえるでしょう。一時的に車を手放す方は、中断証明書の取得がおすすめです。
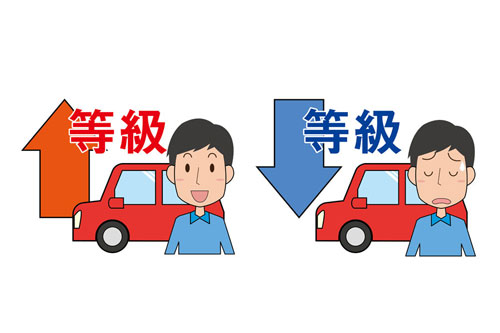
中断証明書の役割は、自動車保険を再開したときに等級を引き継ぐことです。例えば、13等級で契約していた人が何らかの理由で自動車保険を解約して後日再契約する場合、本来なら6等級からやり直しとなってしまいます。
そんなときに中断証明書があれば、解約時の13等級を最長で10年間保存でき、再契約時にその等級から再開可能です。等級が低いと保険料が高くなってしまいますが、中断証明書があることで保険料の節約ができます。
等級が高いことは、事故歴がないことを表します。無事故を維持してきたことで得られた等級は、自分自身のモチベーションにも繋がるでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
中断証明書を発行するときの条件

中断証明書は、希望すれば誰でも受け取れるものではありません。中断理由や等級条件、申請期限が定められており、これらを満たしている場合に限り中断証明書の発行が可能です。
そのため、中断証明書の申し込みを行う前に、自分が条件に当てはまっているか確認しておく必要があります。ここからは、中断証明書の発行条件について解説します。
中断証明書を発行するには、解約する時点での等級が7等級から20等級の範囲内であることが条件です。自動車保険の等級制度は7等級以上が「優良等級」で、無事故割引の対象になることから、等級を維持する価値があるとされています。
つまり、事故を起こしてしまっていたり、契約年数が短かったりして等級が低いと「わざわざ等級を維持する必要がない」と判断され、中断証明書の条件に当てはまりません。
新規契約で6等級から始まり、無事故で数年間契約を継続していたことで7等級以上になった方が、今後もお得に利用し続けられる制度です。
中断証明書の発行申請には期限があり、解約した日(もしくは満期日)の翌日から5年以内と決められています。この期限を1日でも過ぎてしまうと、他の等級条件や中断理由が中断証明書の発行条件に当てはまっていても発行は行われません。
保険会社によっては、中断証明書の申請がオンラインでできる場合もあるため、家事の合間や仕事帰りの電車の中でも行いやすいです。
とくに長期的な海外出張やライフスタイルの変化によって車を手放す場合には、再開の予定が未定の場合もあるでしょう。自分に合った申請方法を調べて、申請のし忘れがないよう注意が必要です。
中断証明書の発行には、単に保険の解約をするだけでなく、正当な中断理由が必要です。主に所有していた自動車の売却や廃車、契約者自身の海外赴任などが代表的な理由としてあげられます。
単なる節約目的や、車を一時的に使用しないといった理由では、中断証明書を発行する理由に値しないと判断される可能性があります。そのため、中断証明書の発行を予定している場合は、解約後に「中断証明書が発行されなかった」という事態にならないために、事前に条件を満たしているか調べておくことが大切です。
詳細は保険会社によって異なるため、加入している保険会社にて確認を行いましょう。
中断証明書の発行時に必要な書類

中断証明書の発行には、廃車や車検切れなど、申請内容に応じた書類が必要です。また、どの理由であっても「中断証明書発行申請書」を提出する必要があります。
- 車検切れの場合…「自動車検査証」「登録事項等証明書」など
- 廃車や譲渡などの場合…「登録事項等証明書」「登録識別情報等通知書」など
- 車両入れ替えの場合…「契約内容変更通知書」「移動承認書」など
- 盗難の場合…「盗難届証明書」など
中断証明書の申請には、公的機関・保険会社が発行した書類の提出が必要です。不備があると手続きに遅れが生じたり、発行がされなかったりする恐れがあります。
必要な書類は保険会社に確認しておくと安心です。
中断証明書の有効期限は10年間ととても長いため、保管場所を決めておかないと必要なときに失くしてしまうリスクが高い傾向です。重要な書類をしまう場所など定位置を決めておきましょう。
中断証明書発行手続きの流れ
自動車保険を中断するためには現在の契約を解約し、そのうえで保険会社に対して中断証明書の発行を申し込みする流れで行います。
手続きには時間がかかる場合もあるため、期限ギリギリになって焦ってしまうことのないよう、計画的に進めることが重要です。
ここからは、中断証明書を発行する手続きの流れを詳しく解説します。

中断証明書を発行するには、まず現在加入している自動車保険を解約する必要があります。中断は一時停止することですが、実際には一度自動車保険を解約しなくてはいけません。
解約手続きを行わずに、中断証明書だけを申請することはできないため、注意が必要です。
自動車保険の解約には、保険会社に電話やオンラインでの申請などの方法があり、手続きが完了すると解約日が決まります。この「解約日」が、中断証明書の発行申請期限にも関わってくるため、すぐに申請を行わない場合は忘れないように記録しておくなど対策を行いましょう。
自動車保険を解約した後は、中断証明書の発行を保険会社に正式に申し込みます。申し込み方法は、郵送やオンライン申請などさまざまですが、保険会社によって選択肢が異なるため、よく確認しておきましょう。
オンラインでの申請に対応している保険会社では、書類の提出もオンライン上でやり取りできるケースが多く、手軽に行えることが魅力です。申し込み時には契約者の個人情報や中断理由別の書類が必要になるため、事前に手元に揃えておくことをおすすめします。
申し込み内容に不備があると、手続きがスムーズに進まなかったり、中断証明書が発行されなかったりする可能性があります。とくに申し込み内容を入力する際は、丁寧に行いましょう。
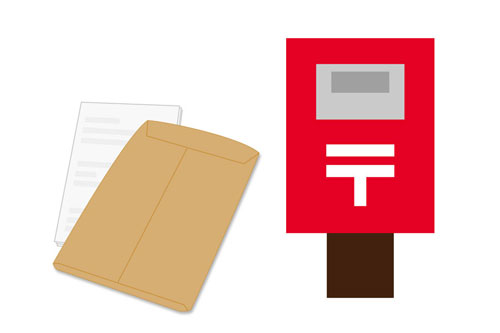
中断証明書の発行には、理由別に必要な書類を保険会社に提出しなくてはいけません。提出方法は郵送やオンラインでデータを送る方法が一般的で、対応は保険会社によってさまざまです。
例えば、廃車の場合は「登録事項等証明書」、車両入れ替えなら「契約内容変更通知書」が必要です。状況に適した書類がすべて揃っていないと発行に時間がかかってしまうため、早めに準備しておきましょう。
なお、提出時にはコピーではなく原本の提出が求められるケースが大半です。書類の提出が無事完了すると、保険会社にて審査が行われ、数日から数週間で中断証明書が発行されます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自動車保険を中断するメリット
無事故などで積み上げた高い等級を維持できることは、中断証明書の大きなメリットです。また、中断した等級は家族に引き継ぐことも可能で、新たにドライバーデビューした子どもがいる家庭では、経済的な負担軽減にも効果があります。
中断証明書の取得は簡単に行えるため、車を一度手放すといった方も取得しておくことがおすすめです。
ここからは、自動車保険を中断するメリットを紹介します。
中断証明書を発行する大きなメリットは、解約時点での等級を最長10年間保持できることです。等級とは、保険の利用の有無や加入年数によって決まるもので、数字が高いほど保険料が割引される仕組みです。
例えば、12等級で自動車保険を中断した場合、10年以内であれば契約再開時に12等級からスタートできます。中断証明書を発行していなければ、一度は12等級まで上がっていても、再び契約をするときには6等級からのスタートになってしまいます。
一度は車のない生活になるとしても、将来また車に乗る可能性がある方にとっては、等級を残しておけることはメリットだといえるでしょう。

中断証明書で維持した等級は、本人だけでなく家族にも引き継ぐことが可能です。具体的には、配偶者や同居している親族に等級の転移ができる仕組みで、家庭の経済的負担を軽減できます。
親が高い等級を保持しており、自分自身はもう車に乗る予定はなく、子どもが車に乗り始めたタイミングで等級の引き継ぎを行うとします。子どもは本来なら6等級から始めるところを、親が持っていた高い等級から利用できるため、保険料の割引が受けられることがメリットです。
中断証明書をうまく活用することで、家庭全体の保険料の負担を軽減できるでしょう。
中断証明書の発行の手続きは、とても簡単に行えて費用もかかりません。保険会社の多くは、電話や郵送、インターネットでの受付に対応しており、忙しい方でもスキマ時間を使って手軽に手続きが行えます。
書類の準備も普段見慣れない書類ですが、数は決して多くなく、保険会社に問い合わせておくと状況に合わせてサポートしてくれるため、スムーズに書類の準備もできるでしょう。さらに発行するための手数料はかかりません。
時間的にも金銭的にも負担が少ないことから、中断証明書の発行を迷うなら発行しておいて損はないといえるでしょう。

中断証明書は、現在加入している保険会社だけでなく、他の保険会社での再契約にも使用できます。これは、保険会社間で共通の制度として認識されていることが理由で、証明書を提示することで他社でも同じ等級から契約をスタートできます。
つまり、自動車保険を中断している間に別の保険会社からお得なプランが新しく登場した場合、再契約時には価格やサービス内容を比較検討し、より自分に合った保険会社を選ぶことも可能だということです。
中断証明書は、他の保険会社に乗り換えるときにも効果を発揮してくれるため、とくに高い等級を持っている方は利用しておくべき制度だといえるでしょう。
中断証明書なしで解約すると等級は引き継げず再契約したときにも6等級からのスタートになってしまいます。高い等級を持っている方は、中断証明書の申請がおすすめです。
中断後に自動車保険を再契約する際の注意点
メリットの多い中断証明書ですが、自動車保険を再契約する際には、いくつかの注意点があります。手続きのタイミングを間違えてしまうと、せっかく維持してきた等級を失ってしまう恐れもあるため再開する際は注意が必要です。
ここからは、中断後に自動車保険を再び契約する際の注意点について詳しく解説します。

中断証明書には有効期限があり、解約日または満期日翌日から10年間です。この期限を過ぎてしまうと、どれだけ高い等級を残していても証明書は無効になってしまい、中断前の等級は使えなくなってしまいます。
残しておいた等級が使えないとなると、自動的に等級は6等級からのスタートとなり、保険料は高くなってしまうでしょう。
このような事態を避けるためにも、証明書の発行日や有効期限は把握し、再契約の目途が立った際には後回しにせず早めの手続きをおすすめします。証明書は再契約を完了させるまで紛失しないよう保管場所にも気をつけましょう。
中断証明書を用いて自動車保険を再契約する際は、新たに車を手に入れてから「1年以内」に保険に再加入しなくてはいけません。この期限を過ぎると中断証明書の効力が無くなってしまい、残しておいた等級が引き継げなくなってしまいます。
また、保険会社によっては新しく車を手に入れてから再契約までの期限を1年ではなく1ヶ月と設定している会社もあります。
新車や中古車など、新しく車の購入を予定している場合は、入手後すぐに保険再契約の手続きを行うことが重要です。保険会社によっては車の取得日の確認書類を求められるケースもあるため、記録を管理しておきましょう。
中断証明書の取得理由が海外渡航だった場合、帰国後1年以内に保険に再加入する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、証明書の有効期限内であっても等級の引き継ぎができなくなってしまう恐れがあります。
海外勤務や留学を終えて日本に帰って来た場合、すぐに保険に入らず1年以上経過してしまうと中断証明書は無効です。
このようなトラブルを防ぐためにも、帰国後はなるべく早くに自動車保険の再加入を行いましょう。渡航期間や帰国日を証明できる書類を準備しておくと、より安心です。帰国後は何かと慌ただしいでしょうが、スケジュール調整が重要です、

中断証明書によって残された等級は、本人だけでなく親族にも引き継ぎが可能です。しかし、親族なら誰でも引き継げるというわけではなく、配偶者や同居している親族に限定されます。
親が運転しなくなって車を手放した後も、中断証明書を残しておけば、子どもが免許を取得して車を購入したときに高い等級を引き継げます。
別居している家族や、親族関係にない人には引き継ぎは認められないため、事前に相談しておくことがおすすめです。せっかく残しておいた等級は、有効活用できるように、引き継ぎ可能な範囲を明確に理解しておくことが大切です。








