車の最新技術
更新日:2024.10.18 / 掲載日:2024.10.18
ジャパンモビリティショービジネスウィークへの提言【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文と写真●池田直渡
昨年賑々しくスタートしたジャパンモビリティショー。事前の話としては、東京モーターショーを踏襲して隔年開催の噂だったが、広くモビリティー関連企業のスタートアップと、自動車メーカーの様な大手コンシュマービジネス企業を結びつけるためには、毎年開催が相応しいのではないかという議論を経て、一応は毎年開催となった。
ただし、巨大なイベントは金食い虫でもあるので、隔年で、コンシュマー向けの表回と、ビジネスサイドの交流を図る裏回を開催するという形に落ち着いた。なので今回は「ジャパンモビリティショービジネスウィーク2024(JMSBW)」は、その裏回の第1回ということになる。テーマは「未来を創る、仲間作りの場」である。
筆者も早速10月15日に行ってきたが、正直な話期待に沿うものではなかった。200以上の団体のブース出展と数は立派なのだが、残念ながら見どころがわからない。初めての試みなので仕方がないが、それぞれ良かれと思った譲り合いが悪い方に出てしまった。
表年はどうしても自動車メーカーが主役になるので、裏年はスタートアップに譲ってメーカーブースを最小にすることが試みられた。言わば主役の交代である。気持ちはわかるのだが、結果を見ると、自動車メーカーが引いた結果、主役がいなくなっただけだった。

結果を見れば当たり前だが、スタートアップは金がない。ここからのビジネス展開を援助してくれるパートナーを探しにきているのだから、デカくて派手なブースを自力で作れるわけがない。何の援助もしないで、さあ主役をどうぞといわれたって、そんなことができるはずがないのだ。結果的に200以上の脇役ブースがひたすら並ぶ場になった。
じゃあどうすればよかったのかと言えば、第一義的には自動車メーカーに代わる役割をティア1や2クラスのサプライヤーが果たすべきだったと思う。それともうひとつ、スタートアップの中で注目されるべき技術のある会社をちゃんとフィーチャーしてあげなくてはいけなかったのではないか。
そのためにはインキュベーションコンテストを事前に行っておくべきだと思う。スタートアップ企業のプレゼン大会を行い、OEMが選んだ企業、スタートアップが相互に選んだ企業、そして共同開催のCEATECが選んだ企業の3社に、無料で大きなブーススペースを貸与し、建て込みの費用を賞金として出す。
取材に行った記者は200のブースから宝探しをするのではなく、まずこの3つを取材すれば良い。お客さんもそこを見る。技術の売り込みに対し、露出機会というアドバンテージを与えることだ。それ以外のブースからは各自宝探しである。こうしておかないと、見当がつかないので、結局自動車メーカーのブースを探し出してそこで取材してはいお終いになってしまう。

記者の側から見て、そういう仕掛けをしていないとどうなるか、広報対応に慣れた自動車メーカーですら、何が訴えたいのか散々聞いてみないとわからないことが多いのに、広報経験のないスタートアップに自社のユニークさが伝えられるわけがない。例えば筆者はブースを1軒づつ歩きながら、建て込みに貼ってあるプレゼンボードを読むのだが、まあ何が言いたいかわからない。
しかし出展者は真剣勝負なので何とかして記者を捕まえようとする。捕まれば10分は話を聞く羽目になる。興味のある内容ならば30分だって話を聞くが、自動車のジャーナリストが食品用の冷蔵輸送管理システムの話を聞かされても、ちょっと困ってしまう。10分を200社繰り返したら33時間の拘束だ。回りきれない。
なので、説明員の動きを視線の端でチェックしながら説明を読み、ちょっとでも動きそうならスタコラ逃げ出すという取材したいんだか逃げたいんだかわからない動きになるのだ。そうやって2周半くらいまわったがちっとも要領を得なかった。


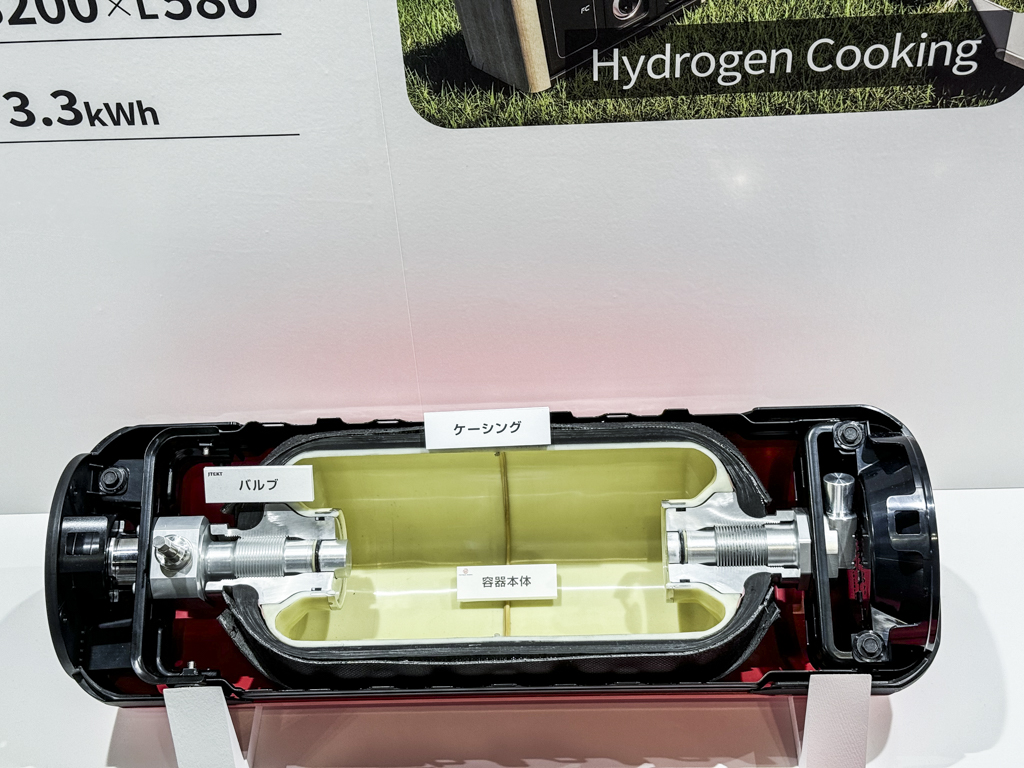
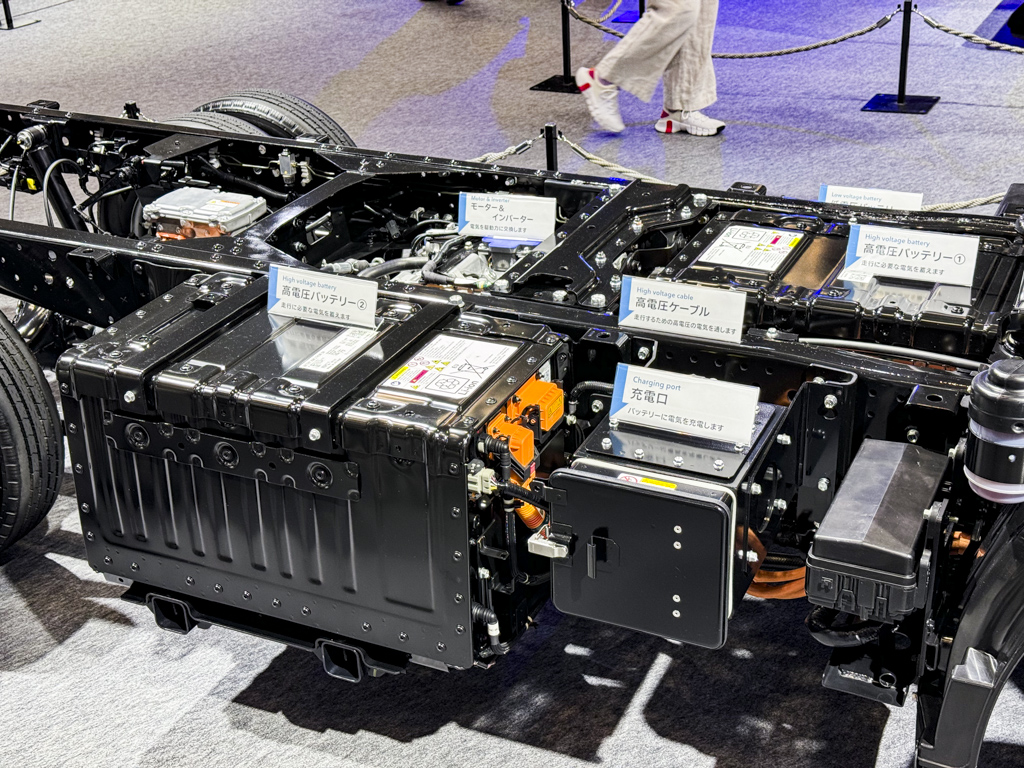
またJMSBWでは、各社のシーズ・ニーズ・事業課題を事前に把握できるオンラインコミュニケーションツール「Meet-up Box」を用意している。これももっと有効利用すべきだろう。マッチアップの段階を、Xで逐一ポストすべきだ。彼らが交渉を進め、ビジネスとして成立していく過程をちゃんと追えるようにしておかなくてはならない。せっかく導入したツールが業界の仲間作りに通年で使える様になるためには、そこで起きている新しい化学反応を世間に伝えなくては意味がない。
今回参加した出展者が何かを掴んで大きく発展すれば、JMSBWはゴールドラッシュの場になるが、イベントを成立させるために餌で釣るだけで成果がでなければやりがい詐欺になってしまう。主催者として、出展者の本当の成功のために真剣に汗をかく姿勢を見せないと次からは誰も協力してくれなくなる。「未来を創る、仲間作りの場」がテーマなのだとすれば、もっともっと出展者とOEM、あるいは投資家やメディアの効率の良いマッチングを進めないと、ただ並べただけのイベントになってしまう。
志は決して低いものではないが、その先に進めるためにまだまだできることがある様に思えたイベントだった。考えようによってはそれはまだまだ伸び代があるということ。第2回、第3回と、その伸び代を確実に現場で実現していって欲しいと思う。
