車の最新技術
更新日:2024.07.19 / 掲載日:2024.07.19
カーボンニュートラル燃料深掘り 水素編【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡
先週「CNFのゲームチェンジが来た!」という記事を書いた。どうやら世界的にカーボンニュートラル燃料(CNF)に期待が集まり始めている。もちろんBEVも重要な選択肢であるが、世界の人々を誰一人取り残す事なく、これまで通りの「移動の自由」を提供していくためには、BEVだけでは需要を満たす台数が作れない。
数年前までは、社会の志向が「ゼロカーボン絶対主義」であり、その前提ではBEVの他の選択肢と言えば、燃料電池だけだった。ところがこちらも普及にはだいぶ高いハードルが残っている。結局は走行時の絶対ゼロカーボンだけ考えても、製造時や廃棄時の話が置き去りになるだけなので、今やゼロカーボンより現実的なカーボンニュートラルが主流になりつつある。その上で、この先10年以内の解決策を考えれば結局のところCNF(カーボンニュートラル燃料)が何とかならないのであれば、人類は非常に厳しい状況を迎えることになるだろう。
航空機の利用を諦めないためには、どっちにしても航空機用のCNFは避けて通れない。これをSAF(Sustainable Aviation Fuel)と言うが、何とかして実用的なコストにしなければならない。となればSAFの近縁種であるCNFを発電やクルマなどに利用用途を拡大して、量産でコストを下げていくしかないという大事な視点もある。
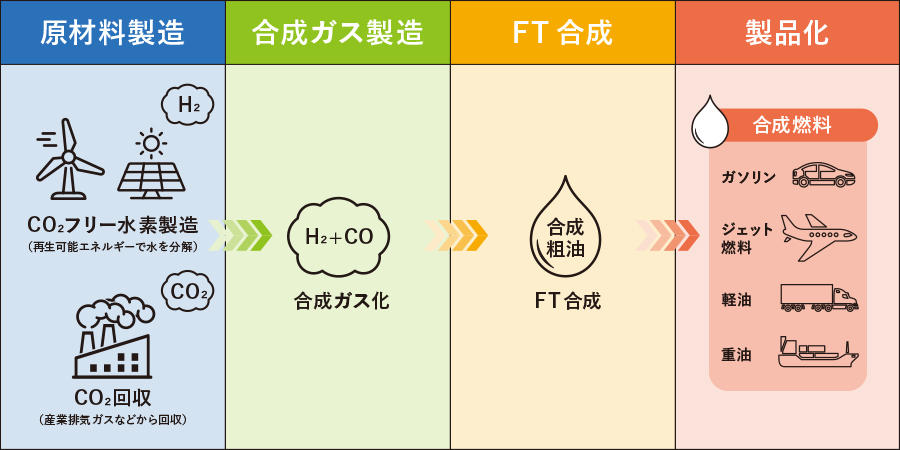
ということで、CNFの必要性と現状については先週の記事を振り返っていただくこととして、今週からは様々なCNFをひとつずつ掘り下げていきたいと思う。第一回は水素である。
水素と言えば、燃料電池の印象が強いと思うが、トヨタがスーパー耐久で開発を続けている通り、CNFとしては水素内燃機関という選択肢が挙げられる。

水素内燃機関には複数の問題がある。もっとも大変なのは車両内での貯蔵で、高圧タンクを用いるか、冷やして液化するかの二択である。高圧タンクは圧力が高すぎて素養として危ない。けれどもトヨタのMIRAIに代表される様な、安全性の高い高圧タンクはとりあえずできている。あとはやはり体積の大きさと、耐高圧ゆえの形状の不自由さである。幸いなことに安全性については700気圧もの高圧だがまだ事故は起きていない。実績だけで評価するなら「燃えるから危ない」という批判を結果でねじ伏せられないBEVよりは、今のところ優秀だということになる。とは言え、その安全性を確保するためにタンクのコストはまだまだ高い。

あるいは、冷やして液化しようとすると、マイナス253℃という極低温が求められる。エネルギーを使って冷やすのは効率が悪いので、現状では自動的に魔法瓶タイプの断熱タンクが選ばれている。しかしながら完全な断熱は不可能なので、どうしても揮発して水素が自然に減っていく。これをボイリングと言う。液化水素はメリットとデメリットが明確だ。ワンタンクあたり航続距離が伸ばしやすいが、一方で車両を使わずに停めておくと、ボイリングでの損失が大きい。
もうひとつのポイントは重量あたり熱量の少なさである。そういう意味では燃料としてのガソリンの性能が飛び抜けすぎているのだ。水素エンジンはおそらく過給が前提となる。ターボで過給圧を上げれば出力は出る。
形状が自由にならない高圧タンクの置き場所を許容するパッケージングや、断熱液化タンクの毎回使い切りという運用などを考えると、乗用車での普及はまだまだハードルが高い。主に大型トラックなど、フレーム周りのスペースに余裕があり、走行距離が計画的な大型商用車には適性が高い。ちなみに高圧水素タンクはタンクも中身の水素も軽いので、ルーフ上などに設置することも可能で、実際燃料電池バスの「SORA」はタンクをルーフ上に設置している。
さて、こうした大型商用車は、乗用車の様に週末にしか乗らないというような運用はありえない。思いつきで行き先が変わることもないので、計画運行で、きっちり燃料を使い切ることで、ボイリングのリスクを回避可能である。
そういう運用であれば水素のメリットが光ってくる。耐用年数が乗用車よりずっと長く、イニシャルコストが高く更新頻度が低い商用車は、2050年以降も路上に残る。そういう車両のカーボンニュートラルを考えると、燃料側で何とかするしかない。もちろんその場合、CNFは概ねどれもその対象になる。

古いトラックのインジェクターを水素対応に交換するレトロフィットがそれなりに安く提供可能であれば、ローコストに保有車の脱炭素化が可能になるわけだ。
水素に関してはそう近々の話だという楽観論を展開するつもりはないが、燃料電池の大型車両の普及によっては、大きなトラックターミナルには水素ステーションが導入される可能性は高い。となればその水素インフラの共用で内燃機関が運用できることのメリットは大きい。
水素内燃機関の活躍シーンがあるとすれば、それが最も現実的なケースである。逆に言えば、それ以外のルートはそれなりにハードルが高いとも言える。
火力発電のCN化やSAFなど、色々な場面で水素社会への期待は高まっているので、クルマの側はそれに便乗して、上手いバランスを取ろうと考えているのだ。
