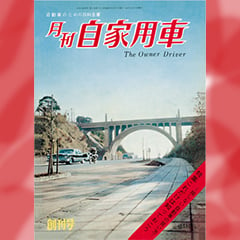車種別・最新情報
更新日:2022.01.25 / 掲載日:2021.12.23
bZ4X〜トヨタ電動SUVの注目ポイント〜

今年の春先にトヨタが開発発表した、EVシリーズ「TOYOTA bZ」。ついにその第一弾モデルとなる「bZ4X」の詳細が発表された。2022年央の市販化を公表するなど、その本気ぶりがひしひしと伝わってくる。トヨタ渾身の電気自動車はどんなモデルに仕上げられるのだろうか?
●文:川島茂夫
満を持してEV市場に参戦! 2022年央に正式デビュー予定
トヨタBEVの第一弾モデルは売れ線のミドルSUVからスタート
本格普及を念頭においた
実践的な機能も注入済み
近年「乗用車の未来は電気自動車(EV)」にあるという言葉を耳にすることが増えてきたが、世界に先駆けてハイブリッドの量販実用車を開発したトヨタにとっては、今さらと感じているのは間違いない。にも拘わらず、これまでトヨタは量産として実用EVを市販してこなかった。THS Ⅱを核とした完成度の高いハイブリッド車を展開していることもあって、EVは時期尚早とも考えていたことは容易に想像できるが、そのトヨタがついに量産実用EVとして投入するのがbZ4Xだ。
バッテリー駆動で走るBEVの駆動システムに革新的な技術導入がなされたという訳ではないが、寒冷期の航続距離短縮の予防など、効率と実用性向上の設計が施されている。この辺りの設計思想は、燃費という分かりやすい数値で効率が見えてしまうハイブリッドやPHVで得たノウハウを活かしたとも言える。分かりやすくいえば、安定した実用航続距離などの実践力向上に軸脚を置いた設計が特徴になっている。
ボディ形状は5ドアHB。車名の「X」が示すとおり、高い全高のクロスオーバーSUVとして開発された。車体寸法はRAV4にほぼ等しく、床下にバッテリーを抱えるせいか室内高はRAV4よりも50㎜低いが、ミドルSUVとしては標準的な室内スペースを実現している。SUVの中核を成すレジャー&ファミリーユースに適したパッケージングといえる。
BEVモデル「bZ4X」ここが注目ポイント
e-TNGAプラットフォーム

パワーユニット

ステアバイワイヤシステム

ルーフソーラーパネル

大容量バッテリーを搭載
満充電で約500㎞走れる
走行ハード面で注目したいのは、TNGAプラットフォームとしては6番目となるBEV専用プラットフォーム「e-TNGA」が導入されていることだ。一般的なプラットフォームにバッテリーを搭載する場合は、フロアパネルとなる床面下に積載されるが、e-TNGAは強固なバッテリー積載フレームを車体剛性部材とする二層構造を採用することで、衝突時のバッテリーの保護と車体剛性の向上を図っている。
さらに操舵システムも一般的な機械式の他に機械的に連結されないステアバイワイヤー式も採用されている。走行状況に応じて前輪舵角を電子制御することでステア舵角量1回転未満での運転も可能としており、この先進的な運転システムが採用されたことでも、bZ4Xの未来感を高めている。
駆動モーターの設定はFF用が150kW、4WD用は前80kW/後80kWの設定で、システム総合出力差は10kWでしかない。ちなみに現在発表されているWLTC総合モードの航続距離はFFが500㎞前後、4WDが460㎞前後。バッテリー容量は71・4kWhなので、FFなら1kWで約7㎞走れる計算。同サイズのBEVではトップクラスの電費性能だ。また、ルーフ装着のソーラーシステムも設定。試算では1年間で走行距離1800㎞に相当する充電が可能という。
運転支援についてはレクサスNX相当の機能を備えるトヨタセーフティセンスを採用。実用面を強く意識したモデルに仕上げられているのは、いかにもトヨタ車らしいこだわりぶりを感じてしまう。
インフラ関連は未整備
脱ガソリン車はまだ尚早
なぜトヨタはBEVを出さないのかと、疑問に思っていたユーザーも少なくないだろう。個人的にはタイミングの問題と理解している。例えば電動度合いで言えばハイブリッドはBEVの下位に位置付けられるが、電動と内燃機の最高の技術を最良で融合させなければならないハイブリッドの技術的な難しさはBEV以上といっても過言ではない。しかも、燃費という数値で技術的優劣も一目瞭然。言い方を換えるならBEVに必要な技術は、ハイブリッド車やPHVの開発で蓄積が可能といえる。
とはいえ、いきなり乗用車の主流をBEVにシフトするのは現実には不可能だろう。価格も、急速充電や電力供給のインフラを含めて一般化のための課題は多い。さらにクルマに限定しなければ、携行性やエネルギー密度から水素や天然ガスをもっと有効に活用する必要もある。トヨタがインフラ的に不利と思われるFCV(燃料電池自動車)を開発するのも、燃料電池を用いるかどうかは別として、BEVでは厳しい大型トラックまで見据えた水素へのそして未来への投資なのだ。船舶や航空機まで考えればなおさらだ。
乗用車だけを見れば無駄に多方面への技術開発を行っている感じだが、社会インフラとしてのモビリティにまで踏み込めばいずれも必須ということになる。何をして適材適所かも含めて、今は過渡期なのだ。
bZ4Xの登場により
電動車全体の活発化は必至
bZシリーズ第一弾として登場したbZ4Xの概要を見ての印象も過渡期のモデルと感じてしまう。現在市販されているすべてのBEVがそうなのだが、電動技術の革新は見当たらない。また、bZ4Xの基本コンセプトもSDGsを背景にすることを除けば、ミドルSUVの基本といえる。
ただ、e-TNGAやバッテリーパックとレイアウト、あるいはe-アクスルの採用と前後同出力のE-Fourから見えてくるのはコンポーネンツや技術の共通化によるコスト削減効果。これは見逃せない。車名中の「4」はクラス(車格)を示し、bZシリーズを銘打っていることからも、クラスを違えたモデルの登場が予想されている。車種毎にすべて専用で開発すれば高コストになるのは必須。部品や設計の共用化が図れれば小さな市場でもコスパを引き上げることが可能になるだろう。
急速充電スタンドや電力インフラの現況、費用対効果から推定される市場性、さらに賄えるBEV総量を前提にした適切なラインナップや価格の実現がbZシリーズの課題といえる。ハイブリッド、PHEV、FCVにBEVを加えることで、電動化に対応していくのかを見守りたい。
TOYOTA bZ4X
SUBARUとの共同開発で生まれた電動SUV、まもなくデビュー




乗員すべてが快適に過ごせるクラスレスな室内空間を実現