中古車購入チェックポイント
更新日:2022.12.25 / 掲載日:2022.12.25
車のレギュレーターが故障した際の症状とは?対処法も詳しく解説
皆さんは、レギュレーターという車の部品名を聞いたことがあるでしょうか?
精密機械である車の部品と部品をつなぐ「調整役」として重要な役割を果たしているのですが、名前すら聞いたことがないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、故障すると非常に困る「レギュレーター」とはどんな部品なのかに加え、故障した時の症状や原因、対処法や修理相場まで詳しく解説していきます。
例えば、燃料の爆発力で作動しているエンジンのピストン運動(上下運動)を、回転方向の運動に変え、タイヤに伝えなければ車は走行しません。このように、原動力や作動原理が異なる装備を正常かつ安定して動かすため必要なのがレギュレーターいう部品です。
つまり、レギュレーターが故障したら、車は走ることもその装備を快適に使うこともできないのです。
以下で示すとおり、車の各所に用いられていて、構造・仕組み・役割はそれぞれ異なるものの、調整役という大きな目的は全てに共通しています。

そして、電動ウィンドウの原動力であるモーターは回転運動をしているので、それを窓の開閉に合わせて上下運動に変換するのがウィンドウレギュレーターの役割です。
電動ウィンドウには、モーターがワイヤーを巻き取ることで上下運動するワイヤー式と、ギアを使って回転運動を上下運動に変換しているギア式があり、現在は後者が主流となっています。
ちなみに、窓の開閉度合いを「調整する」という意味から、手動式ウィンドウを開け閉めするため装着されているハンドルのことを、レギュレーターハンドルと呼んでいました。

例えば、アイドリング時は燃料を噴射する燃圧を下げて噴射量を減らし、走行時は逆に燃圧を上げて噴射量を増やす必要があります。
このように、走行状況で変化するエンジンへの燃圧を調整しているのが燃料レギュレーターという部品です。その役割から「燃圧レギュレーター」「プレッシャーレギュレーター」と呼ばれることもあります。
この他にも、燃料タンクのインジェクターから過度な燃料が噴射された場合、内蔵されている弁が開き、燃料タンクへ燃料を戻す役目も兼ねています。

一方、ライトやエアコン、オーディオやカーナビなどといった車載電装品は全て「直流」で作動するため、そのままでは使えません。そこで、電装系が作動する安定した直流に変換しているのが電圧レギュレーターの役割です。(正確にはその一部であるレクチファイア)
また、エンジンは走行状況により回転数が異なるため、回転力を利用しているオルタネーターが発電する電圧も変化します。この変化する電圧を調整し、常に一定電圧で保っているのも、電圧レギュレーターが果たしている役割の1つです。
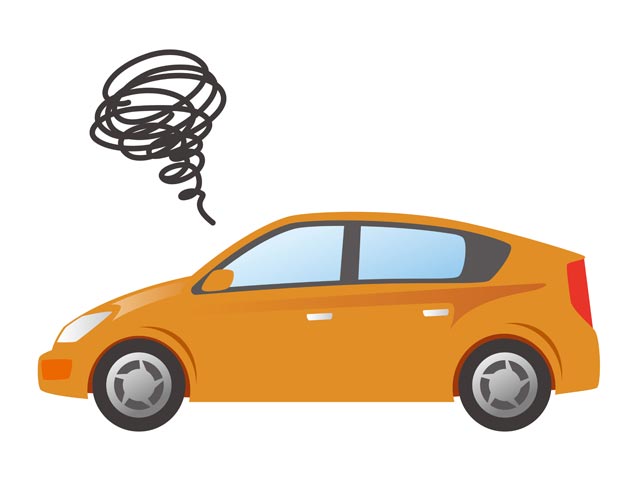
では、各レギュレーターが故障してしまった場合、車にどのような症状が出てしまうのでしょう?
以下で詳しく見ていきましょう。
手動式の場合は、引っ掛かりなどを感じて力を加減することもできますが、電動式はホコリが詰まっていようが関係なくスイッチ操作に従っていつも通りガラスを上下させます。
余計な力が構造的に最も弱いウィンドウレギュレーターにかかり、破損したり、曲がってしまったりするのです。すると、ウィンドウの動きが波打ってきたり、遅くなったりするといった症状が出始めます。
その状態が続き、ギア破損・ワイヤー断絶・モーター焼き付きなどに至ると、完全にウィンドウが動かなくなります。
燃圧が低下した場合は、必要な分の燃料がエンジンに送られません。そのため、アイドリング不安定・エンジンの出力低下・エンジンがかかりにくい・ノッキングなどの症状が出る可能性があります。
一方、燃圧が上昇した場合は少々厄介で、初期にはエンジン出力が上がったり加速が向上したりする「調子がよくなった」と勘違いしてしまうような症状が出るケースもあります。
しかし、時間経過とともにアイドリングの急上昇や燃費の低下が起き始め、ノッキング・マフラーからの黒煙・エンジン温度の異常な上昇などといった悪影響が現れるでしょう。
どちらにしても最終的にはエンジンが完全に故障する可能性があるため、早めの点検・整備が必要です。
一方、電圧レギュレーターは、電装品の作動不良・エンジン停止・エンジンの始動不良など、バッテリー上がりや電圧不足と故障の前兆がよく似ているため厄介です。
とはいえ、レクチファイア機能の故障で整流がうまくいかず、充電不良・電圧不足を起こしている場合は、電装品又は車自体が「動かなくなるだけ」なのでまだ軽いほうです。
レギュレーター機能が故障し、電圧の一定化がうまくできず、過充電・過通電が発生した場合は、一大事となります。バッテリーが過充電に耐えきれずパンクしたり、カーナビ・各種ライトが故障・破損したりと、その車に装備されている電装品全般に悪影響が及ぶケースもあるため、注意が必要です。

そこでここからは、電圧レギュレーターの仕組みについてもう少し詳しく解説していきます。
そんな交流の向きや大きさ(電流)と、勢い(電圧)を、レクチファイア側は、ダイオードなど電流を一方向にしか流さない特性を持つ「半導体」を組み込んだ電子回線で整え、直流に変えています。
また、エンジン停止時(オルタネーターが発電していない時)に、電装品への電力供給を賄っているバッテリーに充電されているのも、レクチファイアを介した「直流」です。
つまり、レクチファイア機能が故障などで停止した場合、あっという間にバッテリーは空っぽになってしまいます。
そうなると、なぜオルタネーターで作られる交流を直接電装品で使用できるようにしたり、バッテリーに溜めたりする構造にしなかったのか疑問に思うかもしれません。
それは、交流回路より直流回路のほうが構造が単純で軽量化やコストダウンによる量産化もしやすいからです。
ちなみに、各家庭のコンセントに届いている電流も「交流」で、これを各家電は内蔵しているコンバーター(レギュレーターの一種)で直流に変えることで動いています。(冷蔵庫やエアコンなど一部家電のモーターは除く。)
このサイリスタは半導体の一種で、一方向にしか電量を流さない性質とともに、一定電圧を超えると反対方向に流す特性を持っています。
この特性を利用して、電装品の稼働及びバッテリーへの充電に必要な一定量の電圧(14V程度)を超えた過剰な電気を、アース・ボディを通じ車外へ放出する仕組みになっています。
サイリスタが機能せず、想定以上の電圧が電装品やバッテリーに伝わったり、余った電気が放出されず車内に流れ込んでしまったりしたら一大事、と述べたのはこのためです。
そのため、「レギュレーターの故障=オルタネーターの故障」とひとくくりにされることがほとんどです。前述したような症状が出て電圧レギュレーターの故障を疑い、対処法などを調べようとネット名を検索してもあまり情報が出てこないことがあります。
また、構造上、電圧レギュレーターだけを修復・交換することも困難なため、どうしても修理コストが高くなってしまいます。

前述したウィンドウを開閉する際、ガラスの動きがぶれる、動きが遅いなどの症状が出ても、ゴム製の「ガラスラン」に詰まったホコリや砂を取り除くと症状が改善する場合があります。
それでも症状が改善しない場合は、ウィンドウレギュレーター自体に故障が発生している可能性が高いため、早急に修理工場などで点検を受けましょう。
また、ウィンドウが開閉しないという症状の場合は、レギュレーターの故障以外にスイッチの故障も考えられます。スイッチが生きている(機能している)場合、スイッチを入れた状態で耳を澄ますと、「ウィーン」というモーターの作動音が聞こえるため、確認すると良いでしょう。
レギュレーター単体で交換できる場合は、10,000円プラス工賃程度が相場です。そして、ギア型よりワイヤー型のほうがやや部品代が高い傾向にあります。
モーターとレギュレーターが一体となっているタイプもあり、その場合は20,000~30,000円+工賃が、目安の修理コストとなります。
いずれの場合でも、中古部品を使うと部品代をもう少し安くすることが可能です。しかし、大きな節約にはならず、工賃は変わらないため、修理後長く乗り続ける予定なら新品を使ったほうが安心です。

また、ネガティブにしろポジティブにしろ症状が微細である場合、プロの目をもってしても故障と判別できない場合もあります。万全を期すのであれば、複数の修理業者で点検を受ける「セカンドオピニオン」も必要です。
部品代は車種によってまちまちですが、おおむね4,000~10,000円程度です。工賃も車種・依頼先によって異なりますが7,000~12,000円が相場のため、合計で20,000円程度は見ておく必要があります。
さらに、車種によっては燃圧レギュレーターだけを交換することはできません。燃圧レール全体を交換する必要があるほか、燃圧上昇に伴う負担が他の部分に及んでいる場合、修理費用が高額になってしまうこともあります。

初期症状が似ているため、バッテリー劣化との区別が難しいですが、いずれにしろ近い将来、車は電気の通わない「ただの鉄の塊」と化してしまいます。
そのため、安全に留意したうえで車を停止し、JAFなどのロードサービスに依頼をしましょう。そして、最寄りの修理工場まで運び、点検と然るべき修理をしてもらってください。
新品を用いた場合、部品代だけで50,000~80,000円、それに工賃が10,000~20,000円必要です。
オーバーホール済のリビルト品を使えば、30,000~50,000円と部品代を節約できますが、工賃は変わりませんのでいずれにしても高額な出費を覚悟しなければなりません。
中古品を使えばさらに部品代をカットできますが、品質を保証できないため、請け負ってくれない業者も多いのが現実です。また、中古品の場合はレギュレーターが元気でも、発電機能のほうに故障が発生するリスクもあるため、あまりおすすめはできません。
また、燃圧レギュレーターと電圧レギュレーターは、燃圧や電圧を調整する機会をできるだけ減らすと効果的です。
電圧の調整は、発電していない停車中には必要以上の電装品を使わない、過剰な後付け電装品を装着しないなどで可能となります。
一方、燃圧の調整は難しいですが、車の走行速度を一定にしていれば安定します。つまり、急発進や急停車などを避け、安定したエンジン回転数・安定した速度を保つエコ走行をすることが、燃圧レギュレーター長持ちさせる秘訣となります。おのずと燃費性能も改善するため一石二鳥です。

ただし、いずれにしても故障が進行する前に予兆が現れるため、それを見逃さず点検と整備を行えば、被害を最小限に食い止めることも可能です。
特に電圧レギュレーターは予兆が分かりにくいため、普段と違うところがないか、愛車の様子を観察しておくことが大切です。
精密機械である車の部品と部品をつなぐ「調整役」として重要な役割を果たしているのですが、名前すら聞いたことがないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、故障すると非常に困る「レギュレーター」とはどんな部品なのかに加え、故障した時の症状や原因、対処法や修理相場まで詳しく解説していきます。
この記事の目次
いつも快適にドライブできるのはレギュレーターのおかげ
車には様々な装備がついてますが、1つ1つの役割はもちろん、原動力や作動原理が異なります。例えば、燃料の爆発力で作動しているエンジンのピストン運動(上下運動)を、回転方向の運動に変え、タイヤに伝えなければ車は走行しません。このように、原動力や作動原理が異なる装備を正常かつ安定して動かすため必要なのがレギュレーターいう部品です。
つまり、レギュレーターが故障したら、車は走ることもその装備を快適に使うこともできないのです。
車のレギュレーターってどんな部品なの?
レギュレーターとは、運動の方向や燃料圧力・電圧・油圧などを一定の方向・値に調整する部品の総称で、規制や制限を意味する「レギュレーション」がその名の由来となっています。以下で示すとおり、車の各所に用いられていて、構造・仕組み・役割はそれぞれ異なるものの、調整役という大きな目的は全てに共通しています。
ウィンドウレギュレーターの役割

そして、電動ウィンドウの原動力であるモーターは回転運動をしているので、それを窓の開閉に合わせて上下運動に変換するのがウィンドウレギュレーターの役割です。
電動ウィンドウには、モーターがワイヤーを巻き取ることで上下運動するワイヤー式と、ギアを使って回転運動を上下運動に変換しているギア式があり、現在は後者が主流となっています。
ちなみに、窓の開閉度合いを「調整する」という意味から、手動式ウィンドウを開け閉めするため装着されているハンドルのことを、レギュレーターハンドルと呼んでいました。
燃料レギュレーターの役割

例えば、アイドリング時は燃料を噴射する燃圧を下げて噴射量を減らし、走行時は逆に燃圧を上げて噴射量を増やす必要があります。
このように、走行状況で変化するエンジンへの燃圧を調整しているのが燃料レギュレーターという部品です。その役割から「燃圧レギュレーター」「プレッシャーレギュレーター」と呼ばれることもあります。
この他にも、燃料タンクのインジェクターから過度な燃料が噴射された場合、内蔵されている弁が開き、燃料タンクへ燃料を戻す役目も兼ねています。
最重要!電圧レギュレーターの役割

一方、ライトやエアコン、オーディオやカーナビなどといった車載電装品は全て「直流」で作動するため、そのままでは使えません。そこで、電装系が作動する安定した直流に変換しているのが電圧レギュレーターの役割です。(正確にはその一部であるレクチファイア)
また、エンジンは走行状況により回転数が異なるため、回転力を利用しているオルタネーターが発電する電圧も変化します。この変化する電圧を調整し、常に一定電圧で保っているのも、電圧レギュレーターが果たしている役割の1つです。
各レギュレーターが故障した時の症状
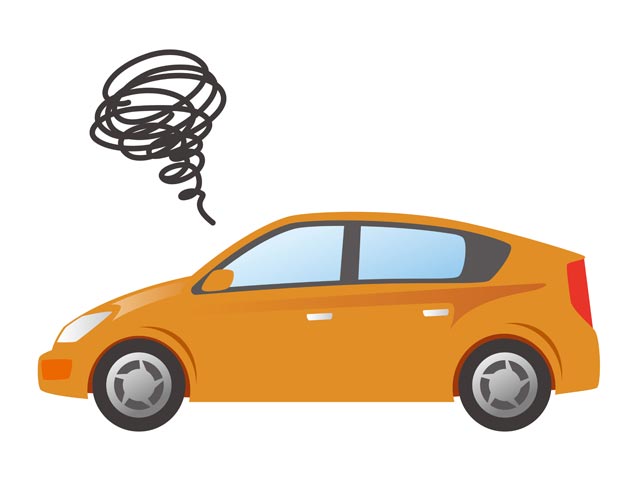
では、各レギュレーターが故障してしまった場合、車にどのような症状が出てしまうのでしょう?
以下で詳しく見ていきましょう。
ウィンドウレギュレーターが故障している場合
手動式にしろ電動式にしろ、車のウィンドウガラスは「ガラスラン」と呼ばれるゴムの窓枠に沿って動いています。ここにホコリや砂などが詰まることがあります。手動式の場合は、引っ掛かりなどを感じて力を加減することもできますが、電動式はホコリが詰まっていようが関係なくスイッチ操作に従っていつも通りガラスを上下させます。
余計な力が構造的に最も弱いウィンドウレギュレーターにかかり、破損したり、曲がってしまったりするのです。すると、ウィンドウの動きが波打ってきたり、遅くなったりするといった症状が出始めます。
その状態が続き、ギア破損・ワイヤー断絶・モーター焼き付きなどに至ると、完全にウィンドウが動かなくなります。
燃料レギュレーターが故障している場合
燃圧を調整しているレギュレーターが故障した場合、求められるエンジン出力と燃料噴射量のバランスが崩れてしまいます。その結果、燃圧低下(噴射量不足)あるいは、燃圧上昇(噴射量過剰)のいずれかを起因とした症状が出てきます。燃圧が低下した場合は、必要な分の燃料がエンジンに送られません。そのため、アイドリング不安定・エンジンの出力低下・エンジンがかかりにくい・ノッキングなどの症状が出る可能性があります。
一方、燃圧が上昇した場合は少々厄介で、初期にはエンジン出力が上がったり加速が向上したりする「調子がよくなった」と勘違いしてしまうような症状が出るケースもあります。
しかし、時間経過とともにアイドリングの急上昇や燃費の低下が起き始め、ノッキング・マフラーからの黒煙・エンジン温度の異常な上昇などといった悪影響が現れるでしょう。
どちらにしても最終的にはエンジンが完全に故障する可能性があるため、早めの点検・整備が必要です。
電圧レギュレーターが故障すると一大事
ウィンドウレギュレーター及び燃圧レギュレターは、不具合・故障の進み具合やその症状がはっきりしていて、比較的素人でも発見しやすいです。そのため、電動ウィンドウの使用を一時的にやめる、症状が軽いうちに修理工場に持ち込むといった対処のしようもあります。一方、電圧レギュレーターは、電装品の作動不良・エンジン停止・エンジンの始動不良など、バッテリー上がりや電圧不足と故障の前兆がよく似ているため厄介です。
とはいえ、レクチファイア機能の故障で整流がうまくいかず、充電不良・電圧不足を起こしている場合は、電装品又は車自体が「動かなくなるだけ」なのでまだ軽いほうです。
レギュレーター機能が故障し、電圧の一定化がうまくできず、過充電・過通電が発生した場合は、一大事となります。バッテリーが過充電に耐えきれずパンクしたり、カーナビ・各種ライトが故障・破損したりと、その車に装備されている電装品全般に悪影響が及ぶケースもあるため、注意が必要です。
電圧レギュレーターの仕組みを知っておこう

そこでここからは、電圧レギュレーターの仕組みについてもう少し詳しく解説していきます。
「半導体」を使って交流を直流へ変換
オルタネーターが作る「交流」は、簡単に言うとプラス極とマイナス極との間を行ったり来たりしています。そんな交流の向きや大きさ(電流)と、勢い(電圧)を、レクチファイア側は、ダイオードなど電流を一方向にしか流さない特性を持つ「半導体」を組み込んだ電子回線で整え、直流に変えています。
また、エンジン停止時(オルタネーターが発電していない時)に、電装品への電力供給を賄っているバッテリーに充電されているのも、レクチファイアを介した「直流」です。
つまり、レクチファイア機能が故障などで停止した場合、あっという間にバッテリーは空っぽになってしまいます。
そうなると、なぜオルタネーターで作られる交流を直接電装品で使用できるようにしたり、バッテリーに溜めたりする構造にしなかったのか疑問に思うかもしれません。
それは、交流回路より直流回路のほうが構造が単純で軽量化やコストダウンによる量産化もしやすいからです。
ちなみに、各家庭のコンセントに届いている電流も「交流」で、これを各家電は内蔵しているコンバーター(レギュレーターの一種)で直流に変えることで動いています。(冷蔵庫やエアコンなど一部家電のモーターは除く。)
変換した直流電圧を一定に制御
一方、電圧の調整役であるレギュレーター側には、これまた半導体の一種である「サイリスタ」という部品が組み込まれています。このサイリスタは半導体の一種で、一方向にしか電量を流さない性質とともに、一定電圧を超えると反対方向に流す特性を持っています。
この特性を利用して、電装品の稼働及びバッテリーへの充電に必要な一定量の電圧(14V程度)を超えた過剰な電気を、アース・ボディを通じ車外へ放出する仕組みになっています。
サイリスタが機能せず、想定以上の電圧が電装品やバッテリーに伝わったり、余った電気が放出されず車内に流れ込んでしまったりしたら一大事、と述べたのはこのためです。
車のレギュレーターはオルタネーターと一体になっている
通常、レクチュファイヤとレギュレーターは一体構造になっています。バイクの電圧レギュレーターは、発電部品と別口で設置されていることが多くなっていますが、車の電圧レギュレーターはオルタネーターの中に組み込まれています。そのため、「レギュレーターの故障=オルタネーターの故障」とひとくくりにされることがほとんどです。前述したような症状が出て電圧レギュレーターの故障を疑い、対処法などを調べようとネット名を検索してもあまり情報が出てこないことがあります。
また、構造上、電圧レギュレーターだけを修復・交換することも困難なため、どうしても修理コストが高くなってしまいます。
ウィンドウレギュレーターが故障した時の対処法

前述したウィンドウを開閉する際、ガラスの動きがぶれる、動きが遅いなどの症状が出ても、ゴム製の「ガラスラン」に詰まったホコリや砂を取り除くと症状が改善する場合があります。
それでも症状が改善しない場合は、ウィンドウレギュレーター自体に故障が発生している可能性が高いため、早急に修理工場などで点検を受けましょう。
また、ウィンドウが開閉しないという症状の場合は、レギュレーターの故障以外にスイッチの故障も考えられます。スイッチが生きている(機能している)場合、スイッチを入れた状態で耳を澄ますと、「ウィーン」というモーターの作動音が聞こえるため、確認すると良いでしょう。
目安となる点検・修理・部品交換費用
点検の結果、故障が判明した場合、整備では改善できないことがほとんどです。基本的には部品交換の必要があります。レギュレーター単体で交換できる場合は、10,000円プラス工賃程度が相場です。そして、ギア型よりワイヤー型のほうがやや部品代が高い傾向にあります。
モーターとレギュレーターが一体となっているタイプもあり、その場合は20,000~30,000円+工賃が、目安の修理コストとなります。
いずれの場合でも、中古部品を使うと部品代をもう少し安くすることが可能です。しかし、大きな節約にはならず、工賃は変わらないため、修理後長く乗り続ける予定なら新品を使ったほうが安心です。
燃圧レギュレーターが故障した時の対処法

また、ネガティブにしろポジティブにしろ症状が微細である場合、プロの目をもってしても故障と判別できない場合もあります。万全を期すのであれば、複数の修理業者で点検を受ける「セカンドオピニオン」も必要です。
目安となる点検・修理・部品交換費用
燃圧レギュレーターが故障している場合、整備や調整での症状回復は困難なため、部品を交換するのが一般的です。リビルト品や中古品はほとんど出回っていないため、新品に交換することになるでしょう。部品代は車種によってまちまちですが、おおむね4,000~10,000円程度です。工賃も車種・依頼先によって異なりますが7,000~12,000円が相場のため、合計で20,000円程度は見ておく必要があります。
さらに、車種によっては燃圧レギュレーターだけを交換することはできません。燃圧レール全体を交換する必要があるほか、燃圧上昇に伴う負担が他の部分に及んでいる場合、修理費用が高額になってしまうこともあります。
電圧レギュレーターが故障した時の対処法

初期症状が似ているため、バッテリー劣化との区別が難しいですが、いずれにしろ近い将来、車は電気の通わない「ただの鉄の塊」と化してしまいます。
そのため、安全に留意したうえで車を停止し、JAFなどのロードサービスに依頼をしましょう。そして、最寄りの修理工場まで運び、点検と然るべき修理をしてもらってください。
目安となる点検・修理・部品交換費用
個別に取り付けられているバイクの電圧レギュレーターとは異なり、車の電圧レギュレーターはオルタネーターに内蔵されています。そのため修理を行うには、オルタネーターASSY(一式)を部品交換する必要があります。新品を用いた場合、部品代だけで50,000~80,000円、それに工賃が10,000~20,000円必要です。
オーバーホール済のリビルト品を使えば、30,000~50,000円と部品代を節約できますが、工賃は変わりませんのでいずれにしても高額な出費を覚悟しなければなりません。
中古品を使えばさらに部品代をカットできますが、品質を保証できないため、請け負ってくれない業者も多いのが現実です。また、中古品の場合はレギュレーターが元気でも、発電機能のほうに故障が発生するリスクもあるため、あまりおすすめはできません。
各種レギュレーターを長持ちさせる方法
ウィンドウレギュレーターは、窓枠(ガラスラン)に詰まっているホコリや砂をまめに掃除し、レギュレーター・電動モーターにかかる負荷を減らしてあげると寿命が延びる可能性が高くなります。また、燃圧レギュレーターと電圧レギュレーターは、燃圧や電圧を調整する機会をできるだけ減らすと効果的です。
電圧の調整は、発電していない停車中には必要以上の電装品を使わない、過剰な後付け電装品を装着しないなどで可能となります。
一方、燃圧の調整は難しいですが、車の走行速度を一定にしていれば安定します。つまり、急発進や急停車などを避け、安定したエンジン回転数・安定した速度を保つエコ走行をすることが、燃圧レギュレーター長持ちさせる秘訣となります。おのずと燃費性能も改善するため一石二鳥です。
肝心なのは故障の「予兆」を見逃さないこと!

ただし、いずれにしても故障が進行する前に予兆が現れるため、それを見逃さず点検と整備を行えば、被害を最小限に食い止めることも可能です。
特に電圧レギュレーターは予兆が分かりにくいため、普段と違うところがないか、愛車の様子を観察しておくことが大切です。
まとめ
①レギュレーターは、車の各所で部品と部品の調整役をしている重要な部品
②ウィンドウレギュレーターが故障すると、電動ウィンドの動きが悪くなる
③燃圧レギュレーターが故障すると、エンジンの好・不調などの症状が発生し、最終的にはエンジン自体の故障につながる
④電圧レギュレーターが故障すると、電装部品の不具合やエンジン停止、エンジン再始動不能などの症状が出る
⑤ウィンドウレギュレーターが故障した時の修理相場は、10,000~30,000円+工賃
⑥燃圧レギュレーターが故障した時の修理相場は、10,000~30,000円程度だが、被害がエンジンに及ぶと高額になる
⑦電圧レギュレーターはオルタネーターに内蔵されているため、故障した時の修理費用は非常に高額である
⑧レギュレーター故障の被害拡大を防ぐには、わずかな「予兆」を見逃さないことが大切
この記事の画像を見る
