新車の購入を検討する際、「少しでもお得に車を購入したい」「環境に優しい車を選びたいけれど、価格が高そうで不安」と感じている方も多いでしょう。
特にハイブリッド車は本体価格が高いため、購入をためらってしまうかもしれません。しかし、エコカー減税をはじめとする各種優遇制度を活用すれば、実質的な負担を大幅に削減できる可能性があります。
この記事では、ハイブリッド車を購入する際のエコカー減税について、適用条件から具体的な削減率、メーカー別対象車種まで詳しく解説します。
「本当にお得になるのか」「どんな車が対象なのか」といった疑問を解消しながら、環境への配慮と経済性を両立した車選びをしましょう。
ハイブリッド車は条件を満たせばエコカー減税でお得に乗れる!

ハイブリッド車をお得に購入したい方にとって、エコカー減税は大きなメリットがあります。この制度は、環境性能に優れた車に対する自動車重量税の軽減措置で、2026年4月30日まで延長されています。
対象車両については「燃費基準」と「排ガス規制」を達成しているかが、大きな判断基準となり、国土交通省が定めた基準を満たすハイブリッド車であれば適用されます。
自動車重量税が25~100%軽減されるため、新車購入時の負担を大幅に軽減できるでしょう。
ただし、軽減対象となる排出ガス基準・燃費基準等は、2024年1月1日、2025年5月1日にそれぞれ引き上げとなっているため、購入を検討している車が対象かどうか事前に確認することが大切です。
エコカー減税を活用すれば、環境に優しいハイブリッド車をよりお得に手に入れることができるので、エコカー減税の適用条件を確認しましょう。
エコカー減税の概要
エコカー減税は、2009年4月からスタートした国の制度です。環境性能に優れた車の普及を促進するため、車の性能に応じて自動車重量税を削減・免税されます。
対象車両は燃費基準と排出ガス性能基準の両方を満たす必要があり、基準達成度に応じて25%、50%、100%の自動車重量税が削減または免税されます。
ハイブリッド車も対象車の1つですが、条件を満たさないと、エコカー減税は受けられません。
ハイブリッド車の購入を検討しており、エコカー減税を活用したいと考えている方は、どんな条件があるのかを確認しましょう。
エコカー減税の適用期間は2026年4月30日までです。
初回車検分(新車新規登録)および2回目車検(継続車検)分の自動車重量税が免税されます。
ただし、2024年1月1日、2025年5月1日にそれぞれ基準が引き上げられるため、購入時期によって適用条件が変わるため注意しましょう。
エコカー減税の対象車は、以下のとおりです。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合)
- クリーンディーゼル乗用車
- ハイブリッド車
- そのほか、国土交通省が定めた基準に達するガソリン車
対象車両については「燃費基準」と「排ガス規制」を達成していることが、大きな判断基準です。ハイブリッド車の場合、メーカーや車種によって減税率が異なるため、購入前に各メーカーの対象車一覧で確認しましょう。
自動車重量税と減税による削減率について

ハイブリッド車の自動車重量税は、エコカー減税により大幅な削減を受けられます。では、この自動車重量税とはどのうような税金なのでしょうか。
ここからは、自動車重量税の内容と、エコカー減税による削減率について詳しく解説します。
自動車重量税は、車両の重量に応じて課税される国税で、新車購入時と車検時に納付する税金です。
車両重量によって課税される「自動車重量税」は、車両の重量を0.5トン刻みで税額が決まり、重い車ほど税額が高くなる仕組みとなっています。(※軽自動車は重量に関係なく定額)
新車購入時は3年分、車検時は2年分をまとめて支払うため、車を長期間所有する場合は相当な負担です。
エコカー減税の削減率は、燃費基準の達成度によって決まる仕組みです。2025年5月1日〜2026年4月30日までに新たに登録した車は、2030年度燃費基準達成の割合によって25%~100%までの間で変化します。
具体的には、90%達成で25%削減、100%達成で50%削減、120%達成で免税となり、基準をクリアしたハイブリッド車ほど優遇措置を受けることが可能です。
初回車検分(新車新規登録)および2回目車検(継続車検)分の自動車重量税が免税される車両もあり、最大で税額の100%が削減されます。
そのほかの補助・減税制度

エコカー減税以外にも、ハイブリッド車の購入をサポートする以下のような制度が複数用意されています。
- 環境性能割
- グリーン化特例
- CEV補助金
- 自治体独自の補助金
これらの制度を組み合わせて活用することで、ハイブリッド車をより一層お得に購入することが可能です。
各制度には適用条件や申請手続きが異なるため、購入前に詳細を確認しておくことが重要です。
ここからは、それぞれの制度の詳細を確認していきましょう。
環境性能割は、新車・中古車に関わらず自動車の取得時に課税される税金です。通常0~3%の税率が課せられますが、燃費基準を満たすハイブリッド車では非課税のものがあります。
特に電気自動車は購入時に納める「環境性能割」が2025年度末まで非課税となっており、ハイブリッド車も環境性能に応じて税率が削減されます。
車両価格が高額になるほど削減効果も大きくなるため、新車購入時の負担削減に大きく貢献する制度です。
グリーン化特例も自動車税の削減制度で、2026年3月までに環境性能が高い車を新車として登録した場合に適用されます。翌年度の税額を、以下のように節約することが可能です。
- 電気自動車:約75%
- 燃料電池車:約75%
- プラグインハイブリッド車:約50%
グリーン化特例は、新車として登録した翌年度に1回限り適用される制度です。
電気自動車は総排気量に応じて課税される「自動車税」、車両重量に応じて課税される「自動車重量税」についても一定期間、免税または減税措置がとられています。年間の維持費を大幅に削減できる制度です。
CEV補助金は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の略称で、国が交付する補助金制度です。電気自動車やプラグインハイブリッド車などが対象となります。
2025年度の補助金額の上限は最大90万円で、自治体の補助金も併用でき、通常より大幅に低価格で導入できます。そのため、高額なエコカー購入時の負担削減に大きく貢献しています。
申請には期限があるため、購入前に確認しておくと安心です。
各都道府県や市区町村が独自に設けている補助金制度で、国の制度と併用できる場合が多いのが特徴です。
自治体の補助金も併用でき、通常より大幅に低価格で導入できる制度として、国や自治体が交付する補助金を組み合わせることでさらなる負担削減が期待できます。
補助金額や対象車種は自治体により大きく異なり、数万円から数十万円まで幅があります。例えば、東京都では電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車を購入した場合、最大100万円の補助金を受け取ることが可能です。
お住まいの地域の制度を事前に調べておくことで、より効果的に活用できるでしょう。
ハイブリッド車のメリット・デメリット
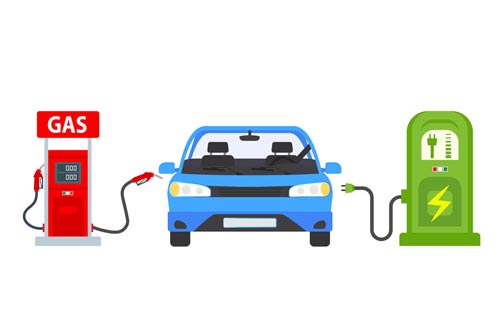
ハイブリッド車には、環境面や経済面で多くのメリットがある一方で、購入時のコストや維持に関するデメリットもあります。
環境負荷の削減や優れた静粛性、リセールバリューが高いといった利点がある反面、本体価格の高さやバッテリーの寿命、修理費の高額化などの課題もあるでしょう。
購入を検討する際は、これらのメリット・デメリットを総合的に判断し、自分の使用環境やライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
ハイブリッド車の最大のメリットは、3つあります。
1つ目は、環境負荷が少ないことです。ガソリンエンジンとモーターを組み合わせることで燃費が向上し、CO2排出量を大幅に削減できます。子どもや未来のために、ハイブリッド車を選ぶ方もおられます。
2つ目は、リセールバリューが高いことです。ハイブリッドカーはガソリン車に比べると、元々の本体価格も高額です。また中古車市場でもハイブリッドカーは人気が高いため、値崩れしづらく、リセールバリューも高い傾向にあります。
3つ目は、静粛性と乗り心地の良さです。低速走行時にはモーターのみで静かに走行できるため、住宅街での早朝・夜間の運転でも周囲への騒音を抑えられます。
ハイブリッド車のデメリットも、3つあります。
1つ目は、本体価格が高いことです。車両本体価格の差が十万円~数十万円の差があるケースが多くあります。ハイブリッド車は、複雑なシステムを搭載するため、初期投資の負担が大きくなりやすいのです。
2つ目は、バッテリーに使用期限があることです。ハイブリッド車の駆動バッテリーは、経年劣化によって定期的に交換します。使用期限は8~10年程度で、交換費用は30~80万円程度かかります。
3つ目は、修理費が高額になりやすいことです。その複雑な構造から、専門的な知識や部品を揃えている整備工場での対応が必要になるため、故障時の修理費が高額になることがあります。
・環境に優しいもののがいい方(CO2排出量の削減に貢献でき、エコカー減税などの優遇措置も受けられます。)
・走行中の音が気になる方(静粛性と乗り心地の良さにより、早朝・深夜や住宅街での運転も周りを気にせず、快適にドライブできる。)
・数年で乗り換える予定の方(ハイブリッドカーはガソリン車に比べると、値崩れしづらい傾向があるため、高いリセールバリューを期待できます。)
これらの条件に当てはまる場合、ハイブリッド車の特徴を最大限活用できるでしょう。
エコカー減税の3つの注意点

エコカー減税を最大限活用するには、制度の注意点を事前に把握することが重要です。
以下の3つのポイントを理解することで、制度の詳細を確認し、適切なタイミングで車両を選択することが可能です。
確実に減税のメリットを受けるためにも確認しておきましょう。
エコカー減税には明確な適用期限が設定されており、永続的な制度ではありません。2026年4月30日まで自動車重量税のエコカー減税は延長されていますが、それ以降の継続は未定です。
さらに、削減対象となる排出ガス基準・燃費基準等は、2024年1月1日、2025年5月1日にそれぞれ引き上げとなるため、時期によって適用される基準が変わります。
ハイブリッド車の購入を検討している場合は、優遇期間内に手続きを完了させることが重要です。
中古車でエコカー減税を受ける場合、車両の初回登録時期が適用の可否が変わります。
新車だけでなく、中古車も制度の対象ですが、中古車でエコカー減税の適用を受けたい場合には、特定の期間内に登録された車両のみが対象となります。車検証の初度登録年月を必ず確認し、エコカー減税の対象期間内に登録された車両かをチェックしましょう。
中古車の場合でも、事前確認が大切です。
エコカー減税の対象車は、以下の通りです。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- クリーンディーゼル車
- プラグインハイブリッド自動車
- 天然ガス自動車
メーカー名や型式などの詳しい情報は、日本自動車工業会(JAMA)や国土交通省公式サイト、各メーカーの公式サイトで確認できます。
また、同じ車種でもグレードや仕様により減税率が異なる場合があるため、しっかりと確認することが大切です。
購入前に必ず最新の対象車リストを確認しておきましょう。
【メーカー別!】どんなハイブリッド車が減税対象?

エコカー減税の対象となるハイブリッド車は、各メーカーから多数販売されており、燃費基準と排ガス基準を満たす車種が認定されています。
各自動車メーカーの公式サイトでは「エコカー減税・対象車一覧」のPDFをダウンロードできます。
購入前に各メーカーの公式サイトや日本自動車工業会の一覧表で、希望車種の減税内容を確認しておきましょう。
トヨタからは、以下の車種が減税対象のハイブリッド車です。
- プリウス
- アクア
- カローラスポーツ
- ヤリス
- アルファード
- ヴォクシー
- シエンタ
- ノア など
トヨタでは、多数のハイブリッド車がエコカー減税対象となっています。車種によって削減率は異なるので、気になる方はディーラーで確認しましょう。
ホンダからは、以下の車種が減税対象のハイブリッド車です。
- フリード
- ヴェゼル
- ステップワゴン
- フィット
- オデッセイ
- シビック など
軽自動車のN-BOXやN-WGNのハイブリッド仕様も含まれており、幅広い車種でエコカー減税のメリットを受けられます。対象車種の詳細はホンダ公式サイトで確認しましょう。
スズキでは軽乗用車・乗用車・福祉車両以外に、商用車でも減税対象車を用意しています。
- ハスラー
- ワゴンR(ハイブリッド仕様)
- エスクード
- スペーシア
- アルト
- エブリイ
- エブリイ(車いす移動車)など
車を使用する用途に応じて選択できます。
継続検査、中古車の新規登録等の自動車重量税額は「自動車重量税額照会サービス」で、具体的な税額を事前に確認することができます。





