ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)が普及する背景には、地球環境の維持に対する貢献度の高い車に対してかかる税金の支払いを低減する制度の恩恵があります。
一般的なガソリン車と比較して車両価格が高い一方、国がこれらの車に対する減税措置を設けることで、HV等の購入を促しています。
ただし、このように国が消費行動を後押しするような税制は時限措置であることが一般的です。
この記事では、ハイブリッド車などに対して設けられた各種税制の内容と、その適用期間を解説します。
環境性能基準を満たしたハイブリッド車に適用されるエコカー減税
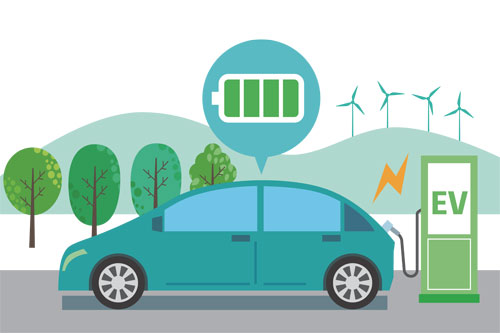
省エネや脱炭素が求められる社会情勢の中、地球環境にやさしい自動車に対しては、支払うべき税金を優遇する仕組みがあります。
決められた基準を満たしたハイブリッド車は、よく耳にするエコカー減税の他、グリーン特例や近年の税制改正により新たに定められた環境性能割などで、減税措置が受けられます。
エコカー減税(自動車重量税)とは?
自動車にかかる税金の一つに「自動車重量税」というものがあります。自動車重量税は車体の重量に比例してかけられる税金です。
車の走行による道路や橋にかける負荷は大きく、徐々に劣化していくインフラ整備の財源とするため、車体の重い車ほど多額の税金がかけられます。
新車購入時(新車登録時)および定期的な車検のタイミングで支払い義務が発生するため、車を保有している限り計画的に準備しておかなければならないお金です。
エコカー減税は、ガソリン車の中でも排出ガス基準と燃費性能に優れたハイブリッド車(HV)と呼ばれる車に対しては、一定割合の支払いを減額する措置が設けられています。
燃費性能基準は国土交通省が定めている、2030年度までに日本国内車の達成すべき燃費性能の目標値を示した「2030年度燃費基準」により評価します。
エコカー減税の対象車

エコカー減税は電気自動車に限りません。ガソリン車でも、燃費性能に優れている車であれば減税され、2030年度燃費基準の充足度合いに応じて優遇幅が変動します。
ハイブリッド車への買い替えを検討している方は、燃料費の節約だけでなく、減税額にも注目して購入車種を考えましょう。
ハイブリッド車(HV)はガソリンエンジンと電動モーターを切り替えて走行するタイプの車です。走行中のエネルギーを電力に変換して蓄え、適宜モーター動力に切り替えて走行します。
発進や低速走行では基本的にモーターを使いますが、加速時や高速走行時ではエンジンを使用することで燃費を大幅に向上させます。電気エネルギーは走行中の動力エネルギーを電気エネルギーに変換し生成したものを使用するに限り、外部からの給電はできません。
一方、LPG車は液化石油ガス(LPG)を燃料とする車です。主にタクシーや業務用車両で普及しています。排気ガス中の有害物質が少なく、環境負荷を抑えられるのが特徴です。
どちらもエコカー減税の対象になりやすく、ランニングコストの低減という経済的メリットと環境への負荷低減を両立しています。
電気自動車(EV)はガソリンや軽油を使わず、大容量バッテリーに蓄えた電力によりモーターを回して走行する車です。走行中に二酸化炭素や窒素酸化物を排出しないため、地球環境の維持に貢献します。
HVのようにエンジンはありません。バッテリーには外部から給電します。公共の充電スポットで給電しますが、現状は給電インフラの少なさが課題です。今後は自宅用給電設備の普及が見込まれており、EVのさらなる普及が期待されています。
エネルギー効率が高く燃料費を節約できたり、静粛性が高くスムーズな加速も魅力で、エコカー減税の優遇幅が大きいのも特徴です。

燃料電池自動車(FCV)は水素と酸素の化学反応によってモーターを駆動させて走行する車です。走行時の排出物は水だけで、二酸化炭素など大気汚染物質を一切排出しない車として注目されています。
水素は短時間で補給でき、ガソリン車と同等の利便性を持ちながら長距離走行を実現しています。環境保全を担う次世代車として、エコカー減税や補助金の対象になりやすく、環境への負荷低減と走行性能を両立している車です。
燃料インフラの水素スタンドの少なさがFCV普及の課題です。
プラグインハイブリッド車(PHEV)は、HVと同様にエンジンとモーターを切り替えて走行する車です。大容量バッテリーに外部電源から充電できるのがHVとの違いで、HVとEVの中間的な位置づけです。
短距離走行は電気だけで行い、バッテリーが減ると自動的にエンジン走行に切り替わります。電動走行時、ガスは排出せず静粛性に優れ、またエンジンを併用しているため長距離の道のりでも安心して走行できます。
災害時には車のバッテリーを電源として活用できるためエコカー減税の優遇対象車として人気の高い車です。

天然ガス自動車(NGV)は、圧縮天然ガスを燃料とする車です。ガソリン車やディーゼル車に比べ、二酸化炭素排出量が少なく、有害物質の排出も大幅に低減できます。
主に路線バスやトラック、業務用車両に採用されており、大気環境改善に大きく貢献しています。
燃料費は比較的安価でエンジンの耐久性も高いことから、経済的なメリットも大きい車です。環境保護と経済性を兼ね備えたエコカーとして、減税の恩恵を受けられるのが魅力です。
クリーンディーゼル車は、最新の排ガス浄化技術により、ディーゼルエンジン特有の黒煙や窒素酸化物を大幅に削減した車です。
ディーゼルエンジンは燃費性能が高く、トルクが大きいため高速走行や重い荷物の運搬に適しています。軽油を燃料とするため、ガソリン車に比べて燃料費が安く、長距離ドライブや商用利用で経済効果を発揮します。
環境への負荷低減と実用性を両立した次世代ディーゼル車として、一定基準をクリアしたモデルはエコカー減税の対象になっています。2024年1月1日以降、減税基準についてはHVと同様の扱いとなりました。
エコカー減税は国土交通省が定めた基準を満たし、一定期間内に新車登録した車に対して初回車検時と初回継続車検時の自動車重量税が優遇される制度です。
初回継続車検時も優遇が受けられる車はさらに限定されますが、要件を満たしていれば中古車でも減税を受けられます。
エコカー減税適用の対象期間

エコカー減税は時限措置です。現在2026年4月30日までの取り扱いが決定しています。
2025年5月以降、減免基準が厳格化し、新車登録のタイミングが「2024年1月1日~2025年4月30日」か「2025年5月1日~2026年4月30日」かによって減税内容が異なります。
今乗っている車の新車登録時期を確認し、受けられる減税額がいくらなのかを把握しておきましょう。
EV・FCV・NGV・PHEVは初回、初回継続時ともに免税です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の達成度合いに応じて段階的に減税率が変動します。
| 120%以上 | 初回、初回継続時ともに免税 |
|---|---|
| 90%以上 | 初回のみ減免 |
| 80%以上 | 初回のみ50%軽減 |
| 70%以上 | 初回のみ25%軽減 |
いずれも2018年排出ガス規制に適合していることが条件です。
HV・FCV・NGV・PHEVは初回、初回継続時ともに免税です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の達成度合いと減税内容に変化があります。
| 125%以上 | 初回、初回継続時ともに免税 |
|---|---|
| 100%以上 | 初回のみ減免 |
| 90%以上 | 初回のみ50%軽減 |
| 80%以上 | 初回のみ25%軽減 |
いずれも2018年排出ガス規制に適合していることが条件です。
また、2024年1月1日~2025年4月30日に新車登録した車と、2025年5月1日~2026年4月30日に新車登録した車とでは減税内容が異なるため、自分の乗っている車の優遇幅をしっかりと確認しておきましょう。
エコカー減税以外の優遇税制措置
HVなどの環境性能の高い車にかかる税金の優遇措置は、エコカー減税だけではありません。保有自動車にかかる税金は自動車重量税の他に、2019年に廃止された自動車取得税に代わって導入された「環境性能割」と、所有自動車に対して毎年課税される「自動車税」があります。
エコカー減税は自動車重量税に対しての優遇税制ですが、他の2つの税金に対しても、燃費基準や排出ガス基準に適合した車に対しての減税制度があります。
ここでは、環境性能割と自動車税のグリーン化特例について解説していきます。エコカー減税と合わせて覚えておきましょう。

環境性能割は、2019年10月に廃止された自動車取得税に代わって導入された税制です。自動車購入時に支払うものである点において、自動車取得税の性質を引き継いでいます。
しかし、燃費性能や排出ガス基準に応じて税率が変わる仕組みを導入したことで、購入者のエコカー選択を後押しする狙いがあります。
取得価格に対して、自動車の環境性能に応じた税率をかけて算出された税額を購入時に一度だけ支払う税金です。
環境性能割の適用期間は、現時点でエコカー減税と同じです。今後延長する可能性がありますが、2026年4月30日までの措置が決定しています。
導入当初から段階的に減免基準が厳しくなっており、2024年1月1日~2025年4月30日に新規登録したものと、2025年5月1日~2026年4月30日に登録した自動車とで燃費基準の達成度合いと税率が異なります。
今からエコカーの購入を検討している人は、減税内容を間違えないよう、しっかりと確認しておいてください。
EV・FCV・NGV・PHEVは非課税です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の適合度合いに応じて段階的に税率が変動し、また普通自動車か軽自動車かで適合基準が異なります。
| 85%以上 | 非課税 |
|---|---|
| 80%以上 | 1% |
| 70%以上 | 2% |
| 70%未満 | 3% |
| 75%以上 | 非課税 |
|---|---|
| 70%以上 | 1% |
| 70%未満 | 2% |
EV・FCV・NGV・PHEVは非課税です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の適合度合いに応じて段階的に税率が変動し、引き続き普通自動車か軽自動車かで適合基準が異なります。
| 90%以上 | 非課税 |
|---|---|
| 85%以上 | 1% |
| 75%以上 | 2% |
| 75%未満 | 3% |
| 80%以上 | 非課税 |
|---|---|
| 75%以上 | 1% |
| 75%未満 | 2% |

グリーン化特例は、購入翌年度分の自動車税もしくは軽自動車税を2030年度排出ガス基準に応じて減免する制度です。
自動車税は自動車重量税とは違い、地方税であり、都道府県の一般財源です。道路などの自動車インフラの維持・管理に使われるため、利用者である自動車保有者はインフラの受益者として毎年支払う必要があります。
特例の無い場合の課税金額は自動車の排気量に応じて段階的に大きくなります。1,000cc以下では25,000円、以降4,500ccまでは500ccごとに5,000円~10,000円ずつ増加し、4,500cc~6,000ccでは87,000円、6,000cc以上では最大の110,000円と、かなりインパクトの大きい金額です。
また、老朽化した車は環境性能が悪化するため買い替えを促す狙いから、購入から13年を経過すると一部のエコカーを除き課税額が増えます。
グリーン化特例の適用期間も、現時点でエコカー減税と同じです。同じく今後延長する可能性がありますが、2026年4月30日までの措置が決定しています。
段階的に減免基準が厳しくなっているのも同様で、2024年1月1日~2025年4月30日に新規登録したものと、2025年5月1日~2026年4月30日に登録した自動車とで燃費基準の達成度合いと減税内容が異なります。
先に解説した2つの制度と合わせて、こちらも確認しておきましょう。
EV・FCV・NGV・PHEVは一律、約75%減免です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の適合度合いに応じて段階的に減免割合が変動しますが、自家用車は対象外です。普通自動車か軽自動車かで減免割合が異なります。
| 90%以上 | 約75%減免 |
|---|---|
| 70%以上 | 約50%減免 |
| 90%以上 | 約50%減免 |
|---|---|
| 70%以上 | 約25%減免 |
いずれも2018年排出ガス規制に適合している車に限ります。
EV・FCV・NGV・PHEV車は一律、約75%減免です。
HV・LPG車・クリーンディーゼル車は、2030年度燃費基準の適合度合いに応じて段階的に減免割合が変動しますが、自家用車は対象外です。普通自動車か軽自動車かで減免割合が異なります。
| 90%以上 | 約75%減免 |
|---|
| 90%以上 | 約50%減免 |
|---|
いずれも2018年排出ガス規制に適合している車に限ります。
ハイブリッド車は節税と車両価格のバランスに優れる

EVやFCVは節税効果は大きいものの、補助金を活用しても車両購入価格は高くなります。また、現時点では給電設備等の燃料インフラも不十分であり、利便性においてもまだまだ十分とは言えません。
その点、HVは既存のインフラを活用でき、購入価格の高さも減税措置や燃費効率である程度カバーできるため、給油頻度の低減という時間的メリットを考えれば価格と汎用性のバランスに優れた車と言えます。
自宅に給電設備のない人や、一括で高額な購入価格の準備が難しい人にとっては有力な選択肢となるでしょう。
エコカー減税は自動車重量税、環境性能割は自動車取得時にかかる税金(以前の自動車取得税に替わるもの)、グリーン化特例は自動車税を対象にした優遇措置です。





