中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.10 / 掲載日:2023.04.10
軽自動車税はどんな税金なの?税額や納付方法などを徹底解説!
軽自動車税と呼ばれる税金には、主に種別割と環境性能割の2つがあります。そして、軽自動車を所有して使用するならば、この2つの税金は必ず納めなければなりません。
ここでは、軽自動車税とはどのような税金なのか、課税対象や税額、納付方法などについて詳しく解説していきます。
また、軽自動車税を滞納した場合はどうなるのか、どんなデメリットがあるのかも知っておきましょう。

軽自動車税(種別割)は、毎年軽自動車の所有者に対して課税される地方税です。
環境性能割は、車の環境負担に応じて車を購入した際に課税される税金となります。

まずは、四輪以上で総排気量が660cc以下の軽自動車です。さらに、三輪で総排気量が660cc以下、二輪で総排気量125cc超~250cc以下の軽自動車も含まれます。
また、二輪で総排気量250cc超えの小型自動車や原付も課税対象です。他にも、ミニカーや農作業用の小型特殊自動車も含まれています。
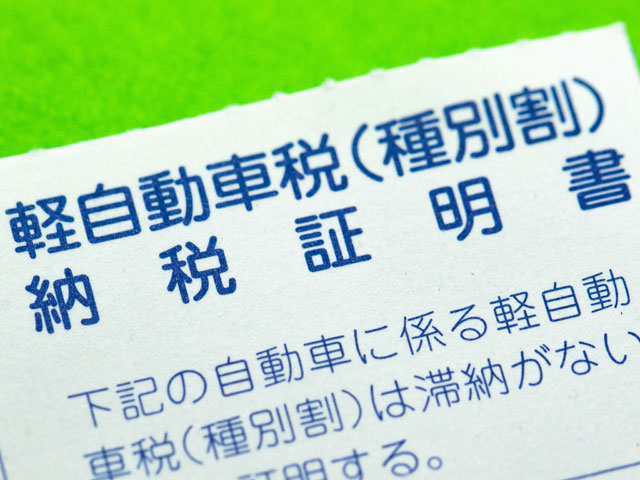
普通車の場合は、税額は車の排気量によって異なり、排気量が500cc増えるごとに税額が高くなっていきます。大きくて馬力のある車ほど税金が高くなるという仕組みです。
一方、軽自動車税(種別割)は、排気量に関係なく金額が一律となっています。
ただし、軽自動車でも自家用や事業用ごとに税額が変わります。また、二輪車や小型特殊自動車も税額が違うので気を付けましょう。
新車登録が2015年3月31日までの車は旧税率が適用されるので、自家用が7,200円、事業用が5,500円です。
新車登録が2015年4月1日以降の車は新税率が適用されるので、自家用が10,800円、事業用が6,900円となります。
ただし、環境に優しい電気自動車やハイブリッドカーなどは対象外となります。
新車登録から13年経過した軽自動車が重課となる理由は、環境保護が関係しています。温暖化を速める要因の一つとされているのが、排ガスによる大気中の二酸化炭素の増加です。
古い車はエンジンの劣化が進むため、排ガス量も増加傾向にあります。エコカーなどの環境に優しい車が税制面で優遇されていることも考慮され、環境への負荷が大きいので税金面でも重課されています。
グリーン化特例は、二酸化炭素などの有害物質の排出を抑えた排ガス低減性能と、燃費性能に優れた環境に優しい車に関しては特別に税金を減額するという制度です。
軽乗用車の自家用で見ると電気自動車や燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車は基本税額の約75%軽減で3,500円となっています。
グリーン化特例は、2023年3月31日までに新車登録を済ませた軽自動車のみと期限が決まっていました。しかし、2022年12月に発表された「令和5年度税制改正大綱」では3年間の延長とされていますので、今後の動向に注目したいところです。

窓口納付とネット納付とは、どんな支払方法になるのか、それぞれ見ていきましょう。
納税通知書と現金を持参し、窓口やレジで支払うと納税通知書に領収印が押され、半券が切り離されて渡されます。これが有効な納税証明書となるので、きちんと保管しておきましょう。
また、現金ではなく一部電子マネーでの支払いも自治体によっては対応している場合があります。アプリのバーコードを読み取れば、キャッシュレス決済が可能です。
クレジットカード払いならポイントがたまるのでお得ですが、自治体によっては決済手数料がかかることもあるので注意しましょう。
また、口座振替にも対応しているので自動引き落としで納付することができます。しかし、事前に金融機関での手続きが必要となります。
また、ペイジーを利用すればネットバンキングからでも納付が可能です。
原因としては、転居後に車検証の住所変更を行っていないことなどが考えられます。郵便局の転送サービスを利用していたとしても、転居後1年間しか有効ではないので注意しましょう。
5月中旬までに納税通知書が届かない場合は、前に住んでいた市区町村の役所に問い合わせてみましょう。
手続き方法は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の窓口で行います。
必要なものは車検証と発行から3ヶ月以内の住民票の写し、もしくは印鑑証明書です。
管轄の軽自動車検査協会が以前の住所と異なる場合は、ナンバープレートの変更手続きも必要となります。

また、一部の自治体に関しては納付期限が通常より1ヶ月遅れの6月末日となっているところもあるので、住んでいる自治体のホームページなどで確認しておきましょう。この場合は、納税通知書が6月中旬頃に届くこともありますので注意しましょう。
納付期限が切れた納付書をそのまま使って納付できるか否かは、自治体によって対応が異なる場合があります。
多くの自治体では、納付期限切れの納付書はネット納付などでは使えず、原則窓口納付での対応となります。金融機関や市区町村役所の税務課などに出向いて、直接窓口で支払いをしなければなりません。コンビニは使える場合と使えない場合があるので、役所に確認しましょう。

滞納期間によっては、ペナルティーとして遅延金が加算されることになります。それでも滞納し続けると、預貯金や給与などの財産が差し押さえられ、強制的に税額分を徴収されるという事態になるかもしれません。
軽自動車税の納付が車検の条件となっているので、支払いの確認ができないもしくは過去に未納状態の年があると、車検が受けられなくなります。
納付期限から1ヶ月以内なら税額の約2~3%、納付期限から1ヶ月を経過したら税額の約8~9%の遅延金が生じます。遅延金の割合は、自治体やその年度ごとに異なる場合もあります。
また、延滞金が加算されるのは1,000円を超えてからで、100円未満は切り捨てとなっているところが多いです。
納付期限切れとなったら、延滞金が加算されるタイミングで延滞金付きの新たな納付書が郵送されてくるので、早めに納付しましょう。
滞納者の財産や勤務先などを調査し、給与や預貯金、不動産などの財産の有無を確認します。そして、その財産から強制的に未納分の軽自動車税(種別割)分の税額を徴収する措置をとることになります。
催告状が届くと、事前に差し押さえを予告する通知が郵送されます。それでも応じなければ、自治体の判断で順次差し押さえが行われます。
以前は、車検時に納税証明書の提示が必要でしたが、2023年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)というオンラインシステムが導入され、納税証明書は不要となりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)は、軽自動車税(種別割)がきちんと納付されているか、軽自動車検査協会が各市区町村にオンライン上で確認ができるというものです。
ただし、軽JNKSに納付状況が反映されるには数日を要するので、納付後すぐに車検を受ける場合などは、納税証明書を準備しておく必要があります。
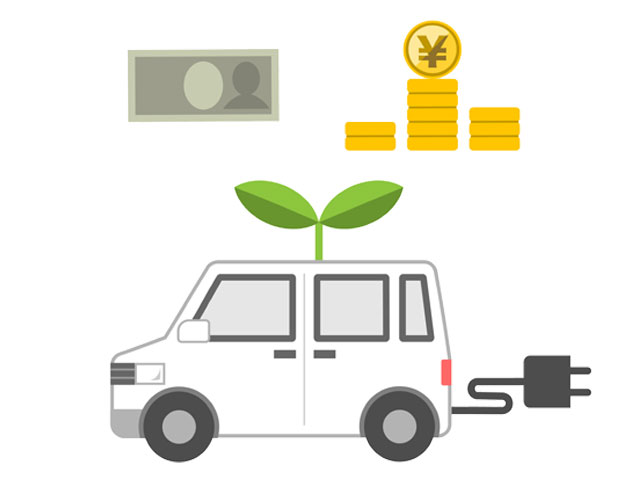
燃費のよい環境に優しい車を購入すると、税額が安くなります。また、車の種類によっては非課税となる場合もあるので、知っておくと購入時の車選びの参考になるかもしれません。
新車の税額は、原則として軽自動車を購入した時の価格(取得価格)に環境性能割の税率をかけて算出します。
課税標準基準額に付加物の価額を足すと、取得価額となります。
課税標準基準額は、課税対象となる車の購入価格のことで、車の型式などからグレード、車種などに基づき決められているものです。そして、実際の販売価格から購入時の値引き額は差し引かれることになっているため、大体販売価格の9割ほどの値段になると言われています。
付加物というのは、購入時のカーナビやオーディオといったオプション品の価格のことです。
こうして算出された取得価額に、自分の車が該当する環境性能割の税率をかけることで税額が分かります。
中古車の経過年数による価値が、残価率です。残価率は新車時を1.0とすると、新車から1年経過で0.562、1年半経過で0.422、2年経過で0.316といった形で決まっています。
環境性能割の税額は、課税標準基準額に残価率をかけて取得価額を出します。そして、取得価額に税率をかけることで算出します。
例えば、課税標準基準額100万円、新車購入から1年経過した税率が1%の車の場合の計算式を見ていきましょう。
100万×0.562=532,000
532,000×0.01=5,320円
よって税額は5,320円です。
因みに、取得価額は50万円以下になると非課税となるので、環境性能割はかかりません。
軽乗用車の場合、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車(2009年排ガス規制NOx10%以上低減、または2018年排ガス規制適合)は、非課税です。
さらに、ハイブリッドカーを含むガソリン車(2009年排ガス規制75%低減、または2018年排ガス規制50%低減)で、2030年燃費基準75%以上達成の場合には課税がありません。
そして、ハイブリッドカー含むガソリン車(2009年排ガス規制75%低減、または2018年排ガス規制50%低減)で2030年燃費基準60%以上達成の場合は、税率が1%となります。
これらの条件に該当しない車は、全て税率が2%です。
しかし、それ以外にも非課税となるケースがあります。それは、車を相続により取得した場合もしくは法人の合併や分割などで取得した場合です。
また、ローンで車を購入した場合の所有権は車の購入者ではなく、ディーラーやクレジットカード会社などになりますが、それを所有権留保と呼びます。
所有権留保のままで売買された車に関しては、ローンを完済後に所有権が購入者に戻ってきて正式に車を取得した場合(所有権解除)も、環境性能割は課税されません。
自動車取得税は、普通車なら取得価額の3%、軽自動車なら取得価額の2%が税率となっていました。しかし、環境性能割では環境に優しい車はさらに税制面で優遇される形となっています。
自動車取得税は基本的に同じ車種なら税率が一律となっていましたが、環境性能割はエコカーであれば、自動車取得税の税率よりも低い税率が適用され、税額も安くなるという点が大きな違いだと言えるでしょう。

ディーラーや中古車販売店からの購入費用の中に、項目の一つとして環境性能割が含まれていることが多いので、気づきにくいかもしれません。明細書にはきちんと記載があるので確認してみましょう。
また、車を所有していると毎年課税される軽自動車税(種別割)や、車検ごとに納税する自動車重量税とは異なり、環境性能割は購入時に1回のみ支払えばよい税金となります。
ここでは、軽自動車税とはどのような税金なのか、課税対象や税額、納付方法などについて詳しく解説していきます。
また、軽自動車税を滞納した場合はどうなるのか、どんなデメリットがあるのかも知っておきましょう。
この記事の目次
軽自動車税には2つの税金がある

軽自動車税(種別割)は、毎年軽自動車の所有者に対して課税される地方税です。
環境性能割は、車の環境負担に応じて車を購入した際に課税される税金となります。
軽自動車税の適用車両

まずは、四輪以上で総排気量が660cc以下の軽自動車です。さらに、三輪で総排気量が660cc以下、二輪で総排気量125cc超~250cc以下の軽自動車も含まれます。
また、二輪で総排気量250cc超えの小型自動車や原付も課税対象です。他にも、ミニカーや農作業用の小型特殊自動車も含まれています。
軽自動車税(種別割)とは?
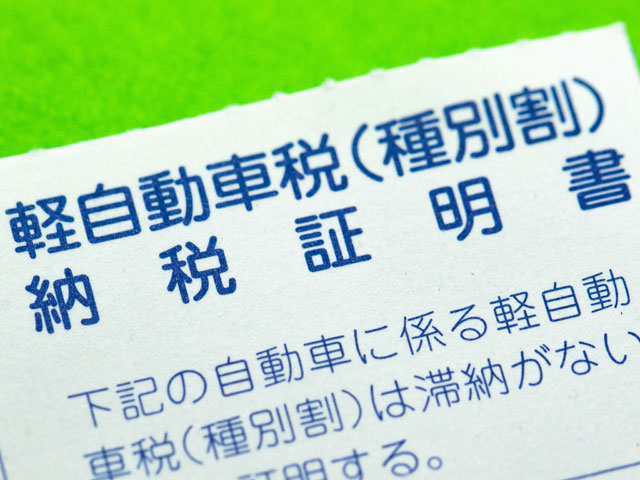
普通車の場合は、税額は車の排気量によって異なり、排気量が500cc増えるごとに税額が高くなっていきます。大きくて馬力のある車ほど税金が高くなるという仕組みです。
一方、軽自動車税(種別割)は、排気量に関係なく金額が一律となっています。
ただし、軽自動車でも自家用や事業用ごとに税額が変わります。また、二輪車や小型特殊自動車も税額が違うので気を付けましょう。
軽自動車税の税額(旧税率と新税率)
軽自動車税(種別割)の税額は、種類や用途ごとに一律で決まっています。(原付は除く)ただし、2015年を境に税率が変わりました。新車登録が2015年3月31日までの車は旧税率が適用されるので、自家用が7,200円、事業用が5,500円です。
新車登録が2015年4月1日以降の車は新税率が適用されるので、自家用が10,800円、事業用が6,900円となります。
13年経過した車は重課税
新車登録から13年を経過した軽自動車は、軽自動車税(種別割)の税額が高くなります。13年未満の税額の約20%増となり、12,900円です。ただし、環境に優しい電気自動車やハイブリッドカーなどは対象外となります。
新車登録から13年経過した軽自動車が重課となる理由は、環境保護が関係しています。温暖化を速める要因の一つとされているのが、排ガスによる大気中の二酸化炭素の増加です。
古い車はエンジンの劣化が進むため、排ガス量も増加傾向にあります。エコカーなどの環境に優しい車が税制面で優遇されていることも考慮され、環境への負荷が大きいので税金面でも重課されています。
グリーン化特例について
環境性能に優れた車は、税制上で優遇されています。軽自動車税(種別割)に関する優遇措置が、グリーン化特例です。グリーン化特例は、二酸化炭素などの有害物質の排出を抑えた排ガス低減性能と、燃費性能に優れた環境に優しい車に関しては特別に税金を減額するという制度です。
軽乗用車の自家用で見ると電気自動車や燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車は基本税額の約75%軽減で3,500円となっています。
グリーン化特例は、2023年3月31日までに新車登録を済ませた軽自動車のみと期限が決まっていました。しかし、2022年12月に発表された「令和5年度税制改正大綱」では3年間の延長とされていますので、今後の動向に注目したいところです。
軽自動車税の納付方法

窓口納付とネット納付とは、どんな支払方法になるのか、それぞれ見ていきましょう。
窓口納付
窓口納付は、銀行や信用金庫などの金融機関や郵便局、コンビニなどに出向いて税金を納める方法です。納税通知書と現金を持参し、窓口やレジで支払うと納税通知書に領収印が押され、半券が切り離されて渡されます。これが有効な納税証明書となるので、きちんと保管しておきましょう。
また、現金ではなく一部電子マネーでの支払いも自治体によっては対応している場合があります。アプリのバーコードを読み取れば、キャッシュレス決済が可能です。
ネットでの納付
金融機関などに直接出向かなくても、パソコンやスマホなどから納付することもできます。クレジットカード払いならポイントがたまるのでお得ですが、自治体によっては決済手数料がかかることもあるので注意しましょう。
また、口座振替にも対応しているので自動引き落としで納付することができます。しかし、事前に金融機関での手続きが必要となります。
また、ペイジーを利用すればネットバンキングからでも納付が可能です。
納税通知書が届かない場合
納税通知書は、毎年4月末~5月中旬に車検証に記載された住所地に郵送されます。しかし、中には届かないケースもあります。原因としては、転居後に車検証の住所変更を行っていないことなどが考えられます。郵便局の転送サービスを利用していたとしても、転居後1年間しか有効ではないので注意しましょう。
5月中旬までに納税通知書が届かない場合は、前に住んでいた市区町村の役所に問い合わせてみましょう。
転居時は住所変更手続きが必要
引っ越しをしたら、車検証の住所変更の手続きを忘れずにやっておきましょう。手続き方法は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の窓口で行います。
必要なものは車検証と発行から3ヶ月以内の住民票の写し、もしくは印鑑証明書です。
管轄の軽自動車検査協会が以前の住所と異なる場合は、ナンバープレートの変更手続きも必要となります。
軽自動車税の納付時期

また、一部の自治体に関しては納付期限が通常より1ヶ月遅れの6月末日となっているところもあるので、住んでいる自治体のホームページなどで確認しておきましょう。この場合は、納税通知書が6月中旬頃に届くこともありますので注意しましょう。
納付期限が過ぎたら納付書が使えない場合も
軽自動車税(種別割)を納めるには、郵送されてくる納付書が必要です。うっかり忘れていて、未納のまま納付書に記載されている納付期限が過ぎてしまったというケースもあるでしょう。納付期限が切れた納付書をそのまま使って納付できるか否かは、自治体によって対応が異なる場合があります。
多くの自治体では、納付期限切れの納付書はネット納付などでは使えず、原則窓口納付での対応となります。金融機関や市区町村役所の税務課などに出向いて、直接窓口で支払いをしなければなりません。コンビニは使える場合と使えない場合があるので、役所に確認しましょう。
軽自動車税を滞納した場合のリスク

滞納期間によっては、ペナルティーとして遅延金が加算されることになります。それでも滞納し続けると、預貯金や給与などの財産が差し押さえられ、強制的に税額分を徴収されるという事態になるかもしれません。
軽自動車税の納付が車検の条件となっているので、支払いの確認ができないもしくは過去に未納状態の年があると、車検が受けられなくなります。
遅延金が発生する
軽自動車税(種別割)の納付期限が過ぎても納付しなかった場合、まず督促状が届くのが一般的です。そして、納付期限からの経過日数に応じて遅延金がペナルティーとして加算されます。納付期限から1ヶ月以内なら税額の約2~3%、納付期限から1ヶ月を経過したら税額の約8~9%の遅延金が生じます。遅延金の割合は、自治体やその年度ごとに異なる場合もあります。
また、延滞金が加算されるのは1,000円を超えてからで、100円未満は切り捨てとなっているところが多いです。
納付期限切れとなったら、延滞金が加算されるタイミングで延滞金付きの新たな納付書が郵送されてくるので、早めに納付しましょう。
財産差し押さえとなる場合も
督促状が届き、遅延金が加算されているのに軽自動車税(種別割)が未納な場合、最悪財産の差し押さえが行われることになるかもしれません。滞納者の財産や勤務先などを調査し、給与や預貯金、不動産などの財産の有無を確認します。そして、その財産から強制的に未納分の軽自動車税(種別割)分の税額を徴収する措置をとることになります。
催告状が届くと、事前に差し押さえを予告する通知が郵送されます。それでも応じなければ、自治体の判断で順次差し押さえが行われます。
車検が受けられない
車検を受けるには、軽自動車税(種別割)を納付しなければならないという条件があります。そのため、滞納をしていると車検を受けることができません。以前は、車検時に納税証明書の提示が必要でしたが、2023年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)というオンラインシステムが導入され、納税証明書は不要となりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)は、軽自動車税(種別割)がきちんと納付されているか、軽自動車検査協会が各市区町村にオンライン上で確認ができるというものです。
ただし、軽JNKSに納付状況が反映されるには数日を要するので、納付後すぐに車検を受ける場合などは、納税証明書を準備しておく必要があります。
環境性能割とは?
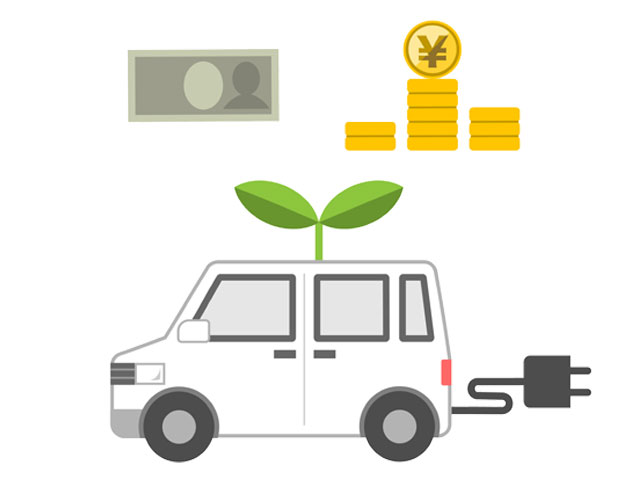
燃費のよい環境に優しい車を購入すると、税額が安くなります。また、車の種類によっては非課税となる場合もあるので、知っておくと購入時の車選びの参考になるかもしれません。
新車の税額の計算方法
環境性能割は、新車と中古車で税額の算出方法が異なるので注意しましょう。新車の税額は、原則として軽自動車を購入した時の価格(取得価格)に環境性能割の税率をかけて算出します。
課税標準基準額に付加物の価額を足すと、取得価額となります。
課税標準基準額は、課税対象となる車の購入価格のことで、車の型式などからグレード、車種などに基づき決められているものです。そして、実際の販売価格から購入時の値引き額は差し引かれることになっているため、大体販売価格の9割ほどの値段になると言われています。
付加物というのは、購入時のカーナビやオーディオといったオプション品の価格のことです。
こうして算出された取得価額に、自分の車が該当する環境性能割の税率をかけることで税額が分かります。
中古車の税額の計算方法
中古車の場合、新車登録から年数が経過するとエンジンなどの部品に劣化が進みます。メンテナンスをしっかり行っていても、新車と同様の価値というわけにはいかないため、経過年数に応じて車の価値は下がります。中古車の経過年数による価値が、残価率です。残価率は新車時を1.0とすると、新車から1年経過で0.562、1年半経過で0.422、2年経過で0.316といった形で決まっています。
環境性能割の税額は、課税標準基準額に残価率をかけて取得価額を出します。そして、取得価額に税率をかけることで算出します。
例えば、課税標準基準額100万円、新車購入から1年経過した税率が1%の車の場合の計算式を見ていきましょう。
100万×0.562=532,000
532,000×0.01=5,320円
よって税額は5,320円です。
因みに、取得価額は50万円以下になると非課税となるので、環境性能割はかかりません。
燃費達成基準に応じて減税となる
環境性能割は、国が定めた燃費基準達成度に基づき税率が決まっています。そのため、燃費基準達成度が高く、燃費性能に優れた車は、非課税もしくは税率が低くなっています。軽乗用車の場合、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車(2009年排ガス規制NOx10%以上低減、または2018年排ガス規制適合)は、非課税です。
さらに、ハイブリッドカーを含むガソリン車(2009年排ガス規制75%低減、または2018年排ガス規制50%低減)で、2030年燃費基準75%以上達成の場合には課税がありません。
そして、ハイブリッドカー含むガソリン車(2009年排ガス規制75%低減、または2018年排ガス規制50%低減)で2030年燃費基準60%以上達成の場合は、税率が1%となります。
これらの条件に該当しない車は、全て税率が2%です。
非課税となるケース
環境性能割が非課税となるのは、電気自動車やガソリン車でも燃費達成基準などの国が定めた基準をクリアしている環境に優しい車です。また、中古車であっても取得価額が50万円以下になる場合も非課税とされています。しかし、それ以外にも非課税となるケースがあります。それは、車を相続により取得した場合もしくは法人の合併や分割などで取得した場合です。
また、ローンで車を購入した場合の所有権は車の購入者ではなく、ディーラーやクレジットカード会社などになりますが、それを所有権留保と呼びます。
所有権留保のままで売買された車に関しては、ローンを完済後に所有権が購入者に戻ってきて正式に車を取得した場合(所有権解除)も、環境性能割は課税されません。
廃止となった自動車取得税との違い
これまでは車の譲渡や購入などの取得時には、「自動車取得税」という税金を納めていました。しかし、2019年10月1日から新たに環境性能割が導入され、自動車取得税は廃止となっています。自動車取得税は、普通車なら取得価額の3%、軽自動車なら取得価額の2%が税率となっていました。しかし、環境性能割では環境に優しい車はさらに税制面で優遇される形となっています。
自動車取得税は基本的に同じ車種なら税率が一律となっていましたが、環境性能割はエコカーであれば、自動車取得税の税率よりも低い税率が適用され、税額も安くなるという点が大きな違いだと言えるでしょう。
環境性能割の支払時期や納付方法

ディーラーや中古車販売店からの購入費用の中に、項目の一つとして環境性能割が含まれていることが多いので、気づきにくいかもしれません。明細書にはきちんと記載があるので確認してみましょう。
また、車を所有していると毎年課税される軽自動車税(種別割)や、車検ごとに納税する自動車重量税とは異なり、環境性能割は購入時に1回のみ支払えばよい税金となります。
まとめ
- ①軽自動車税には、毎年課税される軽自動車税(種別割)と車購入時に課税される環境性能割がある
- ②軽自動車税(種別割)は一律で金額が決まっており、毎年所有者のもとに納付書が届くので、コンビニ払いやクレジットカード払いなどで納付する
- ③軽自動車税(種別割)が未納の場合、遅延金が発生することもある。また、未納のままだと車検を受けることができない
- ④環境性能割は、環境負荷によって税率が異なり、中古車であったも課税対象となる
この記事の画像を見る
