ハイブリッド車はエンジンのほかにモーターも搭載していることから、水害や冠水が発生した際「ハイブリッド車は水に弱いのではないか」「感電の危険があるのではないか」と考える方も多いのではないでしょうか。
ハイブリッド車もガソリン車も共通して冠水した道路を走ることはできませんが、ハイブリッド車の方が修理費用は高額になる傾向があります。
この記事では、ハイブリッド車が水没した際の危険性や緊急対処法、水害から愛車を守る予防策などについて詳しく紹介します。
冠水時の無理な走行は車の寿命を縮めてしまう危険な行為

ハイブリッド車・ガソリン車問わず道路が冠水している状態で無理に走行するのはとても危険です。
車の吸気口から水がエンジン内部に侵入すると「ウォーターハンマー現象」が起き、エンジンが故障してしまうおそれがあります。また、電装系やブレーキに不具合が生じると、修理費がより一層高額になることもあります。
一度の無理な走行が車の寿命を大きく縮めてしまう危険性もあるため、道路が冠水していたら迂回するのが無難です。また、水没車扱いになってしまうと、車を手放すときにも思うような買取金額がつかなくなります。
少しでも不安を感じたら、無理せず走行を行わないようにしましょう。
ハイブリッド車の水没時のリスクを解説
ハイブリッド車は水に弱く、一度でも水没してしまうとエンジンや電装品への深刻なダメージを受けたり、火災の危険性が出てきます。また、車内にカビやサビが発生してしまうこともリスクの1つです。
ここからは、ハイブリッド車が水没してしまったときのリスクについて解説します。
水没直後の火災リスクは低いものの、時間が経過すると火災の危険性が高まります。
これは主に12Vバッテリーからの漏電やショートが原因とされており、泥や汚れが付着したり金属部分が腐食したりすることで通電しやすくなることが原因です。
とくに塩分を含む海水に浸かった場合、塩水は真水に比べて導電性が高く、金属の腐食を促進するため火災リスクが高まります。
このようなことから、一般的な感電への懸念とは異なり、水没直後には見えない内部損傷が遅れて予期せぬ火災を引き起こす可能性こそが、ハイブリッド車の危険性であるといえるでしょう。
水没した車を始動しようとすると、エンジン内部に水が吸い込まれて、ピストンやシリンダーが破損する「ウォーターハンマー現象」を引き起こす可能性があり、エンジンが故障してしまう原因となります。
一度水が吸い込まれるとエンジンは壊れてしまうため、浸水してしまった際、再始動は避けておきましょう。
エンジンの修理は数十万円と、数多くある車の修理のなかでも最も高いとされています。再始動することで愛車に大きなダメージを与えてしまいかねないため、水に浸かってしまった場合は、プロによる徹底的な点検が必要不可欠です。
水没車は泥水や汚水が車内に浸水することで、不衛生な状態になり乾燥後もカビや雑菌が繁殖してしまいます。これらが理由で車内に強烈な悪臭が残る可能性があります。
とくに海水に浸かった場合は、バクテリアによる腐敗臭が強く、シートやマットを交換しても完全には取り切れないケースもあります。
この程度の修理でも業者によっては数十万円以上の費用がかかることがあります。数年乗ってきた車に大金の修理費用を支払うのであれば、新しい車に乗り換える選択肢を選ぶ方も多い傾向です。
車内まで水が入った車は全損扱いとなる可能性が高いでしょう。
しかし、ハイブリッド車はガソリン車に比べてモーターなどの電子部品が多いことから、浸水時にはダメージが深刻化してしまう傾向があります。
ハイブリッド車が水没・冠水してしまったときの緊急対処法

気をつけていても、思わぬアクシデントや災害によって愛車が水没してしまう可能性はゼロではありません。水没したときには、むやみにエンジンをかけたり自力で何とかしようとせず、速やかにロードサービスに連絡して助けを求めましょう。
ここからは、ハイブリッド車が水没・冠水してしまったときの緊急対処法について紹介します。
発火するおそれがあるため、水が引いてもむやみに触らずエンジンをかけないことが重要です。とくにハイブリッド車は高電圧バッテリーを搭載しており、感電のリスクは低いとはいえ、万が一の破損などによる危険を避ける必要があります。
また、水がエンジン内部に吸い込まれ、致命的な損傷を引き起こす「ウォーターハンマー現象」が発生する可能性があるため、エンジンをかけるのは避けましょう。
緊急時にはパニックに陥りやすいものですが、「触らない」「かけない」という原則を徹底することが、二次災害を防ぐために重要なポイントです。
ハイブリッド車の高電圧バッテリーは、通常、水没時でも安全装置が作動し、自動的に電源を遮断するよう設計されています。これにより水没直後の感電リスクは低いとされていることがポイントです。
しかし、実際にはバッテリー内部に水が浸入したり、外部の接続部分が損傷したりすると、数時間から数日後にショートや熱暴走による火災が発生する危険性があります。
とくに海水に浸かった場合は、腐食が猛スピードで進んでしまうため、より注意が必要です。たとえ水が引いた後で外見上問題がないように見えても、内部では腐食や損傷が進行している可能性があるため、自己判断は避けましょう。
水没した車は自己判断で対応せず、速やかにJAFなどのロードサービスや最寄りの自動車整備工場に連絡し、プロによる点検と処置を依頼することが必須です。
とくにハイブリッド車の場合、高電圧バッテリーの専門的な知識と資格を持つ整備士の対応が必要になります。知識のない人が手を出すと、二次災害(感電や火災)のリスクが高まってしまうでしょう。
火災防止のため、ボンネットを開けてバッテリーのマイナス側のターミナルを外して絶縁処置を施すことが推奨されています。しかし、少しでも不安のある場合は無理をせずプロに任せるべきです。
車内からの安全な脱出方法

もし、乗っている車が水没してしまい身動きがとれなくなった場合でも、慌てずに落ち着いて対応することが重要です。
車内に水が浸入してくると、パニックになってしまう方が多いでしょう。しかし、車内外の水圧の差が激しいときは車のドアにも圧力がかかっている状態です。
ここからは、車内からの安全な脱出方法について詳しく紹介します。
水圧で窓やドアが開かない場合は、緊急脱出用ハンマーの使用も選択肢に入れておきましょう。フロントガラスは衝撃を受けても割れないように工夫されているため、ハンマーを使うときはサイドガラスをたたき割るようにしましょう。
車内に備えておく緊急脱出用ハンマーを選ぶ際は、何でも良いというわけではありません。JIS規格かGSマークに適合しているものを選ぶようにするのがポイントです。
女性の力でも比較的簡単に叩き割れるよう工夫されたコンパクトなタイプなど、様々な種類があります。自分が使いやすいと感じる商品を選んでおきましょう。
車内外の水圧の差が激しいと、ドアは圧力がかかって上手く開けられません。車は水中に落ちてもすぐには沈まないため、落ち着いてシートベルトを外し、窓を開けて脱出を試みます。
車内に水が浸入してきて、胸元あたりまで水位が上がってくればドアからの脱出が可能です。内外の水位差が小さくなるのを冷静に待ち、ドアロックを解除して足でドアを蹴り上げる方法もあります。
車の安全だけでなく、乗員の安全確保も水害対策の重要なポイントであり、万が一の事態に備えた行動計画を立てることが、大切な人の命を守るうえで必要不可欠です。
とくに泥水などで深さが分かりにくくなっている箇所は、見た感じよりも深くなっていると考えるのが無難です。
水害から愛車を守る浸水対策と予防策
日頃生活をしていて、水害について考える機会はあまり多くはありません。しかし、事前に浸水に備えておくことは、被害を小さく抑えるためにも非常に重要です。
ここからは、水害から愛車を守る浸水対策と予防策について紹介します。
冠水している道路を走ることは、とても危険です。水深が30cm以上(ドアの切りかきまで)になると、一般的な車は走行不可になり、全損となってしまう可能性が高まります。
最低地上高の高いSUVでも40cm程度が限界とされており、無茶な走行は避けておくべきです。水深が深いとエンジンへの水の吸い込みや電装品のショート、車の浮き上がりによる制御不能など、様々なリスクが発生します。
とくに、急激に水深が深くなるアンダーパスなどには決して侵入しないように気をつけましょう。「行けるだろう」と安易な考えがもたらすリスクを理解しておくことが重要です。
大雨や台風の際には、事前に自治体が公開しているハザードマップを確認し、浸水や土砂災害のリスクが高い場所を把握しておくことが重要です。
自宅や職場の駐車場、よく利用する場所などが危険区域に指定されていないかを確認し、必要に応じて安全な高台や立体駐車場などへ車両を移動させるようにしましょう。
これは、水害が起こる前に個人が実行できる最も効果的な予防策の一つであり、車が水に触れる機会そのものを減らすというリスク回避の方法です。
普段利用している駐車場のリスクが高く使用できない場合は、早めに対応しておきましょう。
万が一の事態に備えて、緊急脱出用ハンマーなどの防災用品を車内に常備しておくことが重要です。また、加入している自動車保険の契約内容を確認し、水害による車両損害が補償されるかどうかも確認しておきましょう。
車両保険に加入していれば、水没による修理費用や買い替え費用が補償される場合があります。保険金請求に必要な書類や証拠写真(水没状況など)を事前に把握しておくことで、もしものときにも慌てずに申請が行えるでしょう。
防災対策はハンマーだけに限らず、車内に積んでおくと安心です。水害対策は、物理的な安全確保と経済的な負担に備えておくことが重要です。
愛車が浸水してしまった際は自分で解決しようとせず、ロードサービスなどに連絡してプロの判断を仰ぎましょう。適切を処置を行ってくれるため安心です。
水没車の中に人が取り残されていたら助けよう
自分自身が水没被害に遭っていなくても、周囲で水没車を発見した場合の注意点と、二次災害を防ぐための行動も重要です。
水没しているハイブリッド車中に人が残されているシーンに遭遇した場合は、ガソリン車同様に中の人を助けましょう。ハイブリッド車の感電リスクがSNS上で出回っていますが、過去に一度も感電事故は起きていません。
また、道路上などに放置された水没車は、見た目には問題なく見えても、電気系統のショートによる火災のリスクを抱えています。もし、自分の家の近くに知らない車が流れ着いていた場合は、警察に連絡し、ナンバーを伝えるなどしておきましょう。
水没車の定義とは?
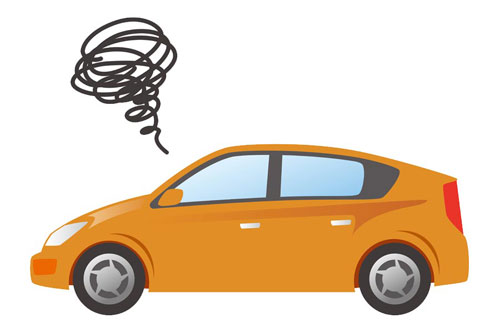
水没車とは、大雨や洪水などで車両の床面より高い位置まで水に浸かってしまった車のことを指します。タイヤが少し水に浸かった程度では水没車扱いにはなりませんが、室内フロア以上に浸水した場合は水没車として見なされます。
見た目がキレイでも、電装系の故障やサビ、異臭などのトラブルが後から発生することが多いため、車を買取に出したときも相場よりもずっと低い査定額しかつかなくなってしまうことが注意点です。
また、水没車はあらゆるパーツに大きなダメージを受けており、「トラブルのスーパーマーケット」になってしまう可能性があります。
車が水没してしまったときの対処法
どれだけ車が浸水しないように注意を払っていても、水害被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。
ここからは、愛車が水没してしまったときの対処法について解説します。

「水没してしまったけれど、愛着のある車でまだ手放したくない」という方は、まず修理が必要です。浸水してしまった場合は、あらゆる部品にダメージがきている可能性が高いため、見た目がキレイでもしっかりとプロに見てもらいましょう。
水没車は修理が必要な個所が多いことから「トラブルのスーパーマーケット」と呼ばれてしまうほどです。具体的な修理費用は車の状態や依頼する業者によって様々ですが、比較的高額になってしまう傾向があるため、買い替えも視野に入れておくと良いでしょう。
なるべく費用を抑えるには、複数の業者で相見積もりを取るのがおすすめです。
浸水した車は「水没車」として見なされ、市場価値がガクッと落ちてしまうのが現状です。数年乗った車に高い修理費用を払うのなら、同じ金額を新しい車を購入するための頭金に充てようと考える方も多いでしょう。
売却して新しい車に乗り換える際は、被害の程度次第では下取りも不可能ではないため、一度相談してみるのがおすすめです。
次の車の販売店で下取りをしてもらうよりも、買取専門店を利用した方が高く買取ってくれる可能性があります。水没車になってしまっても、これまで大切にしてきた愛車に変わりありません。納得できる売却先を選びましょう。
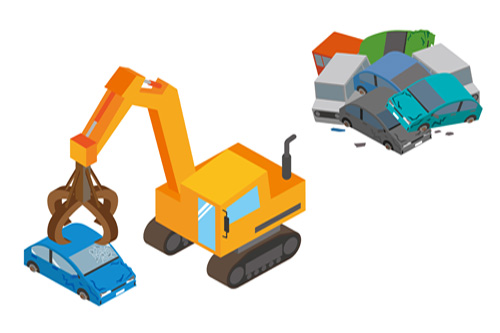
浸水の被害が大きい場合は廃車にすることも視野に入れておきましょう。廃車買取業者によっては、いくらか買取金額をつけてくれるため、満足できる形で車を手放すには、相見積もりを取っておくことがおすすめです。
水没車は新しい買い手はなかなか見つかりにくいですが、資材としてリサイクルする方法で価値があります。見積もりを取ってみる廃車買取業者を選ぶ際は「水没車買取可能」と謳っている業者を選ぶと良いでしょう。
自走ができない状態なら、レッカー車の手配の有無や、手数料なども要チェックです。不明点があるなら、そのままにせずスタッフに確認しておきましょう。





