新型車比較・ライバル車対決
更新日:2025.10.27 / 掲載日:2025.10.27
スーパーハイト軽ワゴン最新事情〜新型デリカミニ登場〜
実力モデルの登場で激戦区はどうなる?
もともとスーパーハイト軽ワゴンは、国内屈指の激戦カテゴリー。そんな状況の中、デリカミニを筆頭とした実力モデルが参入することで、今以上の注目を集めることは間違いない。ここではライバルモデルとの関係を含めた最新情報をお届けしよう。
文:川島 茂夫
スーパーハイト軽ワゴン最新事情

「軽」でも広々キャビンクラス以上の“便利”がある
座面高を高くすると、足を引くような着座姿勢になる。そのため、同じ室内長でも足元の空間に余裕が生まれる。この考え方はミニバンのパッケージングが分かりやすい例だ。このアイデアを軽自動車に展開したのが、スーパーハイト軽ワゴンと呼ばれるモデルになる。ここで紹介するモデルたちは、いずれも軽自動車離れしたキャビンの広さと機能性を大いにアピールしている。
ただ、キャビン機能にこだわった設計はコスト高にもつながる。スライドドアの採用や安全性、使い勝手を考えると、最低でも左側はパワースライド機能が欲しい。できれば両側にも、と装備を追加していくと当然のように価格は高くなる。
また、大きなボディは車両重量もかさむため、運転のしやすさに余裕を求めるならターボも欲しい。高速走行の機会が多いならばなおさらだ。装備や性能に軽自動車としては贅沢な機能や性能を求めると、価格はすぐに200万円を突破する。
スーパーハイト軽自動車は、実用性の優等生であると同時に、軽自動車としては上級設定のモデルになる。実際、価格は登録車のエントリークラスとさほど変わらない。軽自動車は安価であるべき、というユーザーには向かない。簡単にいってしまうと、使って元を取るタイプといえる。
そこまで価格が上がるなら実用性以外の魅力も欲しい、というユーザー向けに市場を伸ばしてきたのが、プレミアム性をプラスしたモデルで、特にSUVテイストを武器にするモデルたちの人気は急上昇。もはやこのカテゴリーの主役に成り変わる魅力を持っている。レジャー需要も用途に入るため、主力となるのはターボ車。さらに加飾や装備が1クラス上になることもあって、標準のスーパーハイト軽ワゴンよりも、さらに予算が必要になってしまうのが悩みどころだが、そのコストアップに見合う価値は十分にある。
タウンユース派はもちろんのこと、レジャーシーンでも活用したいユーザーにとっても、スーパーハイト軽ワゴンは見逃せない選択になってきたのは間違いない。
MITSUBISHI eKスペース

デジタルと融合した新しい「カワイイ」を提案
「カワイイ」は軽自動車のキャラクターづくりのひとつだが、新型となったルークスは、電脳的あるいはサイバー的な要素とキューブのセンスを融合させたような外観が、スーパーハイト軽ワゴンの中でも個性的だ。ちなみにeKスペースはルークスの標準系モデルと姉妹車であり、ほぼ共通した外観を採用する。
特に注目したいのが「ウルトラワイド・フラットディスプレイ」と名付けられた表示系だ。クリアパネルによって、メーターからセンターディスプレイまでを一体化。サイバー時代の車をイメージさせる。外観の印象ともマッチしている。また両モデルとも、今回のフルモデルチェンジで後席の座り心地を向上させるなど、キャビンの実用性の改善も加えられていることも見どころのひとつ。
走行性能面では、加速性能を重視したパワートレーン制御や、高速域でも落ち着きのある足回り、ロードノイズも含めた静粛性など、快適に走れる距離を延ばす工夫もプラスされている。

HONDA N-BOX

高速走行を苦にしない新時代の軽自動車
センタータンクレイアウトとロングホイールベースによるキャビンの広さが売りのひとつとなっているが、広さを自慢するモデルが揃ったこのカテゴリーでは、アドバンテージは「多少」のレベル。キャビンの実用性で注目すべきポイントは、後席機能のバリエーションの多さ。後席格納は座面跳ね上げ式と、バックレストを前倒しして床に沈み込ませるダイブダウンの2ウェイ式を採用。もちろんスライド&リクライニング機能も備わっている。積載物や積載状況への対応力の高さは、このカテゴリーでも最上級にある。
もうひとつ見逃せないのが、高速走行への適性の高さだ。全グレードにACCやLKAを含むホンダセンシングが標準装備であることもポイントだが、余力感をうまく引き出すパワートレーン制御と、高速でも安定したハンドリングと乗り心地が、高速での長距離走行ではかなり効いてくる。標準モデルにターボ車の設定がないのは惜しまれるが、軽自動車へ乗り換えで長距離用途への適性の低下を心配するユーザーにとっては、このモデルが第一の候補になるだろう。
SUZUKI スペーシア

経済性&使い勝手は良好。コスパに優れる優等生モデル
全グレードにハイブリッドシステムを採用しているのは、このカテゴリーではスペーシアだけだ。といっても本格的なストロングハイブリッドではなく、ISG(モーター機能付き発電機)を使ったマイルドハイブリッドになるため、効果は限定的だが、市街地での燃費向上や、余力感を高めてくれる。
ユーティリティ面では、後席に採用された、ふくらはぎを支えるオットマンや、座面上に荷物を置いた時にストッパーとして機能するマルチユースフラップが注目の装備。上級グレード向けの設定になるが、スペーシアならではの実用面でのきめ細やかな機能と言える。
ほかにもスズキの伝統的な装備となった感のある、助手席下の取り外し式ボックスや、買い物フックや後席用トレイなど、日常用途を中心にしたポケット類の充実は、ファミリーユースの現実を反映したもの。価格も含めて、このカテゴリーでもバランスの良さが際立っている。
DAIHATSU タント

センターピラーレスで抜群の使い勝手を実現
スーパーハイト軽ワゴンの実質的な元祖となるのがタントだ。2003年に登場した初代モデルは、スライドドアは採用していなかったが、広いキャビンと見晴らしの良さを武器に、家族のためのタウンカーとして誕生した。その後、スライドドアを採用して、機能と性能を向上。歴代モデルは、家族が生活を楽しむタウンカーとして人気を博している。
現行世代のセールスポイントは「ミラクルオープンドア」と名付けられた、センターピラーレスのスライドドアだ。大きなドア開口は乗り降りを楽にするが、それだけでなく、後席格納時には荷物の積み下ろしでもかなり役立つ。センターピラーはドアと一体化しているため、側面衝突時の安全性も確保されている。
走行性能面では、標準モデルにもターボ車を設定しているのが強み。比較的安価な価格でターボを選べるのは、山間部など走行負荷の大きな状況での走行が多いユーザーには魅力的だ。
MITSUBISHI デリカミニ

街なかも、オフロードもしっかり楽しめる軽ワゴン
先代はeKクロススペースの実質的な後継モデルとして、eKスペースのモデルライフ途中から登場した。最大のセールスポイントは、SUVのタフさと愛玩動物のような可愛らしさを融合させた外観であり、フルモデルチェンジでも基本的なキャラクターを踏襲している。
また、SUV系のスーパーハイト軽ワゴンは、シャシー回りをタイヤも含めて共通としているが、デリカミニはHDC(ヒルディセントコントロール、降坂制御)やグリップコントロールを採用するほか、4WD車ではホイールサイズを15インチに大径化し、専用のサスペンションチューニングも施されている。4WDシステムこそ軽自動車では標準となるVCU(ビスカス)式を採用するものの、日常的な4WDにプラスアルファの悪路走破性が与えられている。
eKスペース/ルークスの派生車種でもあり、キャビン機能や基本的な走行性能はそれらに準じているが、オンロードやラフロードの性能からすれば、このカテゴリーでは最もレジャー用途に適したモデルだ。
HONDA N-BOXジョイ

優れた基本性能はそのままにSUVテイストを上手にプラス
標準モデルのボディシェルをベースに、バンパーやグリルなど一部を変更。SUV系としては控えめな外観だが、撥水加工の専用シート表皮や荷室床下収納ボックスなど、レジャー用途向けの便利な機能を追加している。
また、標準系には設定されていないターボ車をラインナップしているので、N-BOXの強みである長距離レジャー用途への対応力にも優れる。見た目や雰囲気よりも、使い勝手でアウトドアレジャー向けのモデルを求めるユーザー向けだ。
SUZUKI スペーシアギア

街でも映えるタフなSUVスタイル。外観の好みが選択の決め手
SUV系スーパーハイトの元祖となったモデルであり、現行モデルは2代目となる。標準モデルが機能的なスタイルを強めたこともあり、スペーシアギアの雰囲気は初代以上にSUV色が濃くなっている。シャシーや4WD制御は標準モデル系と共通であり、パワートレーンは全グレードにマイルドハイブリッドを採用。後席機能や格納系も共通した設計になるため、選び分けのポイントは、外観の好みによる要素がほとんどだ。もし悪路走破性を重視するならば、スズキ・ハスラーと比較検討するのもオススメだ。
DAIHATSU タント ファンクロス

基本性能は標準モデルと共通。外観の雰囲気が好みなら買い
ルーフレールやタフなイメージを強める意匠がボディ各所にプラスされたことで、SUVテイストを強化。フロントマスクは同社のミニSUVのタフトにも似ている。パワートレーン、シャシー、4WDシステムは標準モデルと共通になるため、スーパーハイト軽ワゴンとしての押しのポイントは、標準モデルと同じくセンターピラーレスのスライドドアによる乗り降りのしやすさと荷物の積みやすさだ。他モデル以上に、この外観の雰囲気が好きなユーザー向けのモデルといえる。
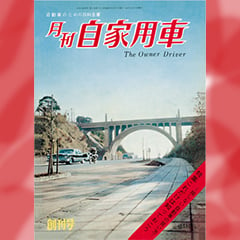
ライタープロフィール
オーナードライバーに密着したクルマとクルマ社会の話題を満載した自動車専門誌として1959年1月に創刊。創刊当時の編集方針である、ユーザー密着型の自動車バイヤーズガイドという立ち位置を変えず現在も刊行を続けている。毎月デビューする数多くの新車を豊富なページ数で紹介し、充実した値引き情報とともに購入指南を行うのも月刊自家用車ならではだ。
オーナードライバーに密着したクルマとクルマ社会の話題を満載した自動車専門誌として1959年1月に創刊。創刊当時の編集方針である、ユーザー密着型の自動車バイヤーズガイドという立ち位置を変えず現在も刊行を続けている。毎月デビューする数多くの新車を豊富なページ数で紹介し、充実した値引き情報とともに購入指南を行うのも月刊自家用車ならではだ。
