車の最新技術
更新日:2021.05.24 / 掲載日:2021.05.21
電気自動車のバッテリーの寿命はどのくらい?【EVの疑問、解決します】
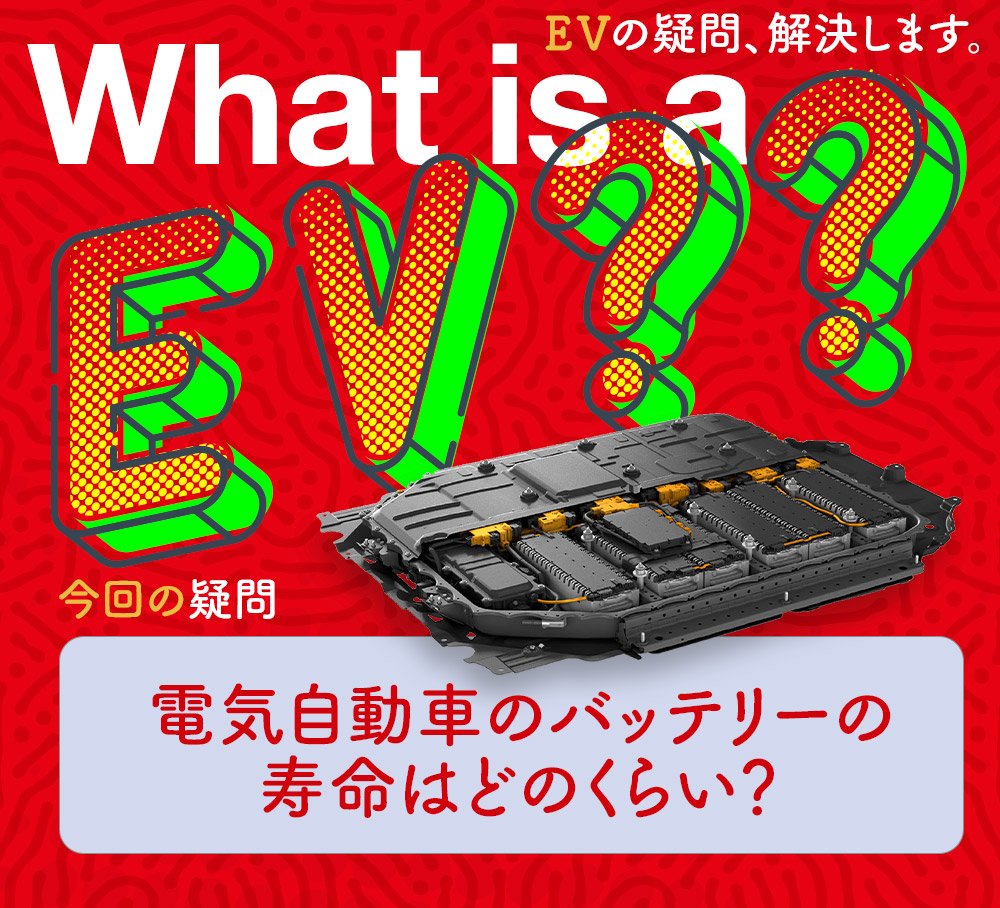
文●大音安弘 写真●ホンダ
電気自動車(EV)のエネルギー源には、主にリチウムイオン電池が採用され、しかも大容量のものが搭載されています。リチウムイオン電池は、スマートフォンなどの身近な携帯家電にも使われていますが、これらの製品では、良くバッテリーの劣化が話題となります。そこでホンダの最新EV「Honda e」のe開発責任者である一瀬智史さんのお話を交えながら、EVのバッテリーの寿命と劣化を防ぐ手段について解説します。
いくら高性能なEVの駆動用バッテリーでも、劣化を避けることはできません。そのため、ユーザーに安心して使用できるように自動車メーカーでは、駆動用バッテリーに特別保証制度を設けていることが多いようです。下記に、一部のEVの保証制度を纏めました。
疑問:電気自動車のバッテリーの寿命はどのくらい?
答え:多くはクルマの寿命に近い8年16万km程度を保証している
自動車メーカーによる駆動用バッテリーの保証内容
| 車種 | 保証期間 | 保証内容 |
| 日産 リーフ | 8年または16万km | バッテリー容量計が9セグメント以下になった場合、修理及び部品交換で9セグ以上へ復帰 |
| メルセデス・EQ EQA | 8年または16万km | 診断機でバッテリー容量が70%に満たない場合、交換 |
| ホンダ e | 8年または16万km | 診断機でバッテリー容量が70%に満たない場合、交換 |
| マツダ MX-30 EVモデル | 8年または16万km | 診断機でバッテリー容量が70%に満たない場合、交換 |
現在新車で販売されているEVであれば充電によるバッテリーの劣化も心配いらない
一瀬さんのお話では、最新EVの駆動用バッテリーの性能を10年で7割程度に保つように設計する流れだそう。ホンダeでは、どのような使い方であっても、10年後に駆動用バッテリーの容量の7割が維持できるように設計しているそうです。
つまり新型の乗用EVならば、駆動用バッテリーの経年劣化は生じるものの、劇的な劣化について心配する必要はないともいえます。しかしながら、バッテリー自体は生ものなので、使い方次第で劣化が進んだり、逆に劣化を抑えたりできるのも事実。
そこで一瀬さんに、バッテリーにとって最も良くない状況を伺うと、乗らずに放置することだそう。EVの駆動用バッテリーは、使わないことでも劣化が進むので、逆に小まめに走らせた方が良いと言います。毎日、単距離を移動することがクルマの負担にならないので、EVはシティコミューターには適しているといえます。それはホンダeが街乗り中心のコンパクトEVとなった原点でもあります。ただホンダeの場合、乗らず放置することで生じるバッテリーの劣化は、数%レベルではないかとのこと。因みに、ホンダeの取扱説明書では、充電量が少ない状態で放置すると、バッテリーの寿命を縮める原因となるため、少なくとも3か月に1度は充電するように記載されています。
それでは、充電による駆動用バッテリーの劣化への影響はどうなのでしょうか。これまで一般的に、急速充電器の多用が劣化を早めると言われてきました。一瀬さんによれば、最新のEVならば、ユーザーが使用上で気にする点はないといいます。
その理由は、バッテリーの温度管理と充電制御の進化にあります。急速充電では、大電流を流すため、バッテリー内部の温度が上昇します。もしバッテリーが高温になると劣化が生じ、性能低下として表れます。それを防ぐために、最新のEVでは、バッテリーの温度と状態に合わせて、EV自身がコントロールを行っているのです。つまり、ユーザーはいつも通りに充電を行うだけで、後はEVが最適な対応を図ってくれるという訳です。
バッテリーの冷却システムは、空冷式と水冷式の2種類があり、現在の主流は水冷式。ホンダeも水冷式を採用しています。それでは寒い方が良いかと言えば、そうともいえません。例えば、-30°などの極低温化では、冷え過ぎによる影響で走行さえ出来ないこともあります。その場合は、バッテリー用のヒーターで温めることで性能を回復。これは充電時も同様で、寒すぎると温めて充電効率を高めるようにします。しかし、全ては自動的に行われるため、ユーザーの操作は一切不要となります。
それでは、家庭などでも利用する普通充電では、ゆっくりと充電を行うため、バッテリーの温度上昇も少なく、あまり劣化の心配はないそう。だから、出先や帰宅時など気軽に日常的な充電を行っても悪影響はないといえます。むしろ、EVの利便性を高める上でも、小まめに普通充電を活用すべきでしょう。もちろん、普通充電でも、駆動用バッテリーの温度に合わせた制御は行われます。
まだ市販車としては珍しい存在のEVですが、自動車メーカー各社の実証実験など取り組みの歴史を含めると、昨日今日生まれたものでもありません。だからこそ、エンジン車に給油するように、充電すれば普通に使えるクルマへと成長を遂げているのです。
執筆者プロフィール:大音安弘(おおと やすひろ)

自動車ジャーナリストの大音安弘氏
1980年生まれ。埼玉県出身。クルマ好きが高じて、エンジニアから自動車雑誌編集者に転身。現在はフリーランスの自動車ライターとして、自動車雑誌やWEBを中心に執筆を行う。歴代の愛車は全てMT車という大のMT好き。
