車の最新技術
更新日:2021.05.07 / 掲載日:2021.04.23
電気自動車の購入を支援して貰えるって本当!?【EVの疑問、解決します】

文●大音安弘
現在のEVに対する国や自治体による補助金制度は、大きく3つに分かれます。一つ目が国からの補助金、二つ目が減税制度、3つ目が自治体による独自の補助金制度があります。
疑問:電気自動車の購入を支援して貰えるって本当!?
答え:本当。条件はあるが、最大で約80万円もの補助が受けられるケースも
基本となるのは国からの補助金

補助金交付を通じて環境車の普及を促進する一般社団法人「次世代自動車振興センター」のWEBサイト
CEV補助金は、クリーンエネルギー自動車(CEV)の新車購入者を支援するための補助金制度で、EVやPHV(プラグインハイブリッド)、FCV(燃料電池車)、そして、クリーンディーゼル車が対象となります。EVの場合、補助金額は一充電走行距離に応じて算出されており、航続距離が長いものほど、補助金額が大きくなります。但し、上限額は40万円(※外部給電機能付きEVなら42万円)となります。補助金を受けた車両は、定められた期間(4年または3年)の保有が義務付けれており、期間内にやむを得ず、売却等の処分を行う場合は、処分前の申請及び補助金の一部返納しなくてはなりません。本年度も概ね令和2年度と同様の内容が予定されており、4月以降の詳細が公表される予定となっています。
これまではCEV補助金が中心だった国からのサポートでしたが、新たな普及促進の取り組みとして、令和2年度第3次補正予算のよる「環境省補助金」と「経済産業省補助金」が設けられました。これらの補助の対象は、EV、PHV、FCVに限定されます。
「環境省補助金」こと、「令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」は、「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」として、CEVの購入時、EVで最大80万円の補助が行われます。但し、環境省補助金を受けるには、自宅等の電力を再生可能エネルギー100%電力で調達すること、政府が実施する調査にモニターとして参画すること(※4年度間に年1回のアンケートなど)のふたつが義務付けられます。つまりEVなどの車両購入に加え、日常生活等で利用する電力を含め、再生可能エネルギー100%の電力とする必要があるので、一般的には、小売電気事業者等が提供する「再エネ電力メニュー」を購入することになります。
もうひとつの「経済産業省補助金」こと、「令和2年度第3次補正予算クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」は、「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」では、CEV購入時、EVで最大60万円の補助が行われます。これは日常及び非常時の両方で活用できる充放電設備/外部給電器の普及を促進することを目的としており、車両購入と共に、充放電器(V2H)や外部給電器(V2L)の同時購入がマスト。さらに車両や設備の活用状況等モニタリング調査への協力(※2年度間で年1回程度のアンケートなど)と、地域で災害等が生じた場合、可能な範囲での協力が求められます。もちろん、V2HとV2Lの設備購入の補助もあり、充放電設備の設備費は1/2補助の上限75万円、その工事費は定額補助で上限40万円。外部給電器の設備費は1/3補助の上限50万円となります。このため、外部給電に対応できない車種については該当外に。ただ給電設備と聞くと高額な出費が想像されますが、一概にそうともいえません。補助金の対象車には、車内にコンセントがあり、直接電気製品等と繋ぐことが可能な車両も含まれるので、コンセント装備するEVやPHV、FCVならば、車両購入のみでも補助が受けられます。
ただし、CEV補助金同様に、乗用車の場合、4年間の保有が、外部給電器で3年、V2H充放電設備及びその付帯設備については5年の保有が義務となるので、やむを得ず、手放す場合は、事前申請と補助金の一部返還が必要となります。
令和3年度のCEV補助金の受付が開始されれば、現状では上記の3つの補助金から自身のEV購入に最適な方法を選ぶことができます。但し、「環境省補助金」と「経済産業省補助金」は、令和2年度第3次補正予算によるもののため、受付期限も令和3年9月30日(必着)と早め。予算の上限も、定期的に行われてきたCEV補助金よりも少なくなります。そのため、これらの補助金の利用を検討するならば、早めに決断し、行動するのがベターです。またV2HとV2Lの設備購入の補助については、CEV補助金と経済産業省補助金でも制度が設けられています。
税金の負担も軽減!
様々な税負担が強いられる自働車ですが、EVの場合、免税及び減税となるものも多いため、維持費の軽減にもつながります。新車及び中古車の購入時に課税される環境性能割は、非課税に。登録時と車検ごとに課税される自動車重量税は、新車購入時と初回車検時となる3年目が免税となります。また5年目以降も、エコカーに該当するため、ユーザーの負担は、軽減されています。そして、毎年の課税となる自動車税についても、グリーン化特例により概ね75%軽減。さらに自動車税は地方税のため、東京都のように独自の次世代自動車導入促進税制を設けることも……。現在、東京都では、新規登録から5年度分が、EV、PHV、FCVで免税とされています。またエンジン車では、日常的な付き合いとなるガソリンや軽油に課せられる税金の負担もなくなるのも、決して小さくはありません。
地方自治体独自の補助金制度も有り!
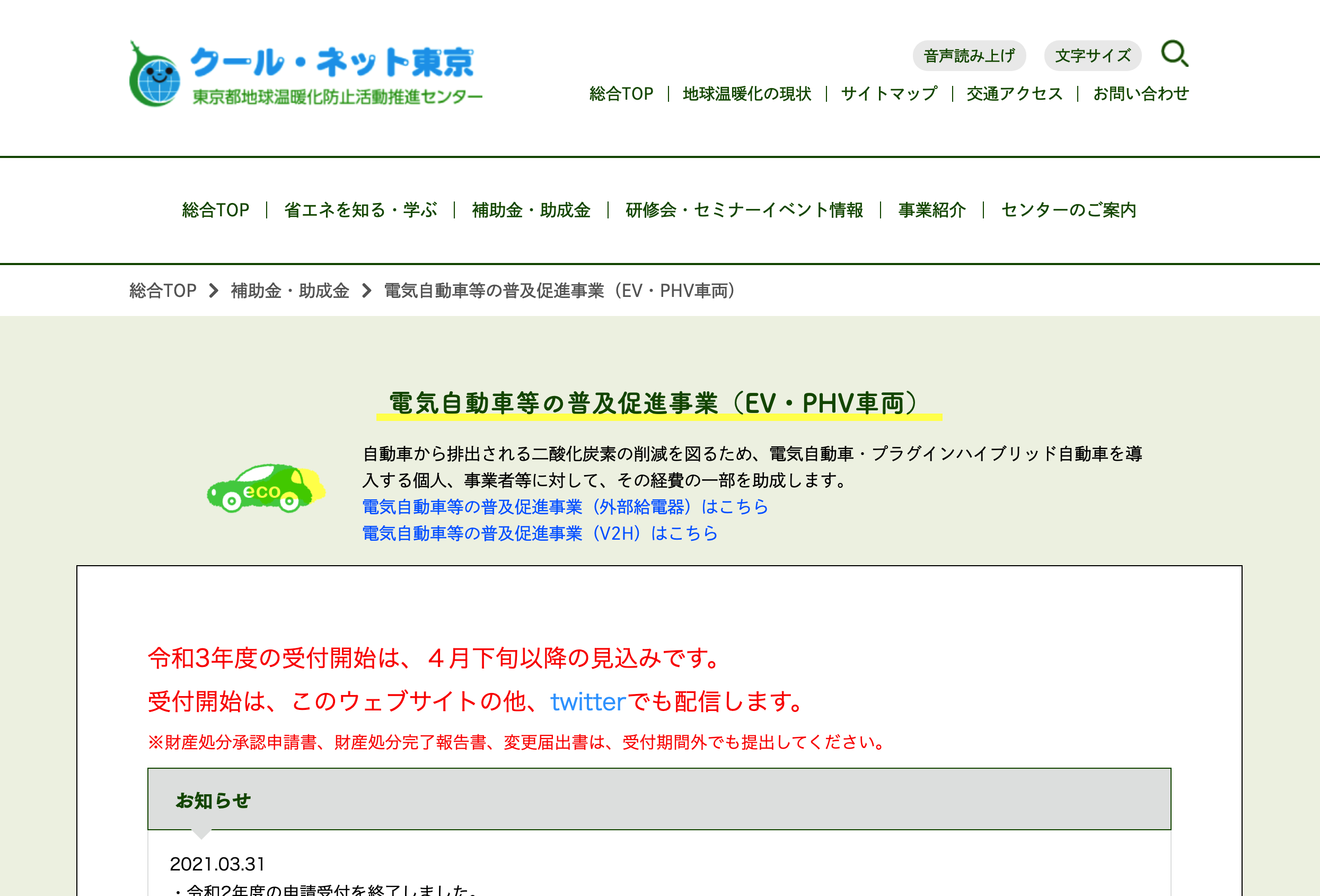
東京都のEV補助金にまつわる情報を提供している東京都地球温暖化防止活動推進センター「クール・ネット東京」
最後が地方自治体独自のCEVに対する補助金にも触れておきましょう。東京都の場合、EVとPHVの新車購入者に、30万円(※令和2年度の例)をサポート。さらに23区内には、独自の助成金制度設けているところも有り、例えば、東京都江東区では「(次世代自動車用)地球温暖化防止設備購入助成」として、EV、PHV、FCVの新車を購入した区民に10万円を助成しています。予算の関係も有り、全体としては地方自治体による助成制度は、限定的で助成金額もまちまちですが、まずは地元の自治体で助成制度がないか調べてみると良いでしょう。
なお、補助金や助成金に関する該当車種や補助金額などの詳細な情報は、CEV補助金の申請受付窓口でもある一般社団法人次世代自動車新興センターをはじめ、経済産業省や環境庁、各自治体、自動車メーカーなどの公式サイトで確認することができます。
執筆者プロフィール:大音安弘(おおと やすひろ)

自動車ジャーナリストの大音安弘氏
1980年生まれ。埼玉県出身。クルマ好きが高じて、エンジニアから自動車雑誌編集者に転身。現在はフリーランスの自動車ライターとして、自動車雑誌やWEBを中心に執筆を行う。歴代の愛車は全てMT車という大のMT好き。
