車の最新技術
更新日:2021.08.06 / 掲載日:2021.08.06
電気自動車の軽自動車は登場しないのですか?【EVの疑問、解決します】
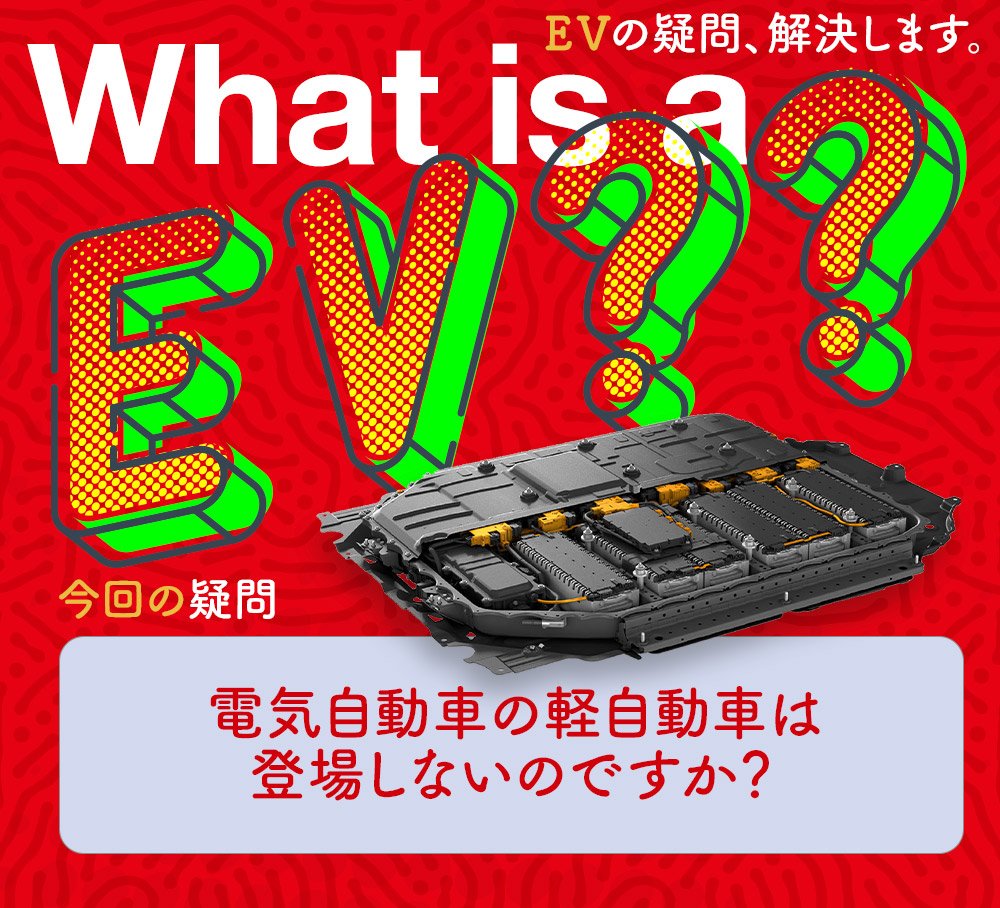
文●大音安弘 写真●三菱、日産
カーボンニュートラルの実現に向け、電気自動車の普及が目指されていますが、その主役は、高価な輸入車たち。国産車で最も身近な日産リーフでも、約330万円からと身近なクルマとは言いにくいのが現状です。そもそも日本の自動車保有台数のうち、約38%を占める軽自動車でありながら、現時点では、乗用タイプのEVの設定はありません。今回は、最も身近なクルマである軽電気自動車の過去と未来について解説します。
電気自動車の軽自動車は登場しないのですか?
2022年に新型軽EVが登場予定です
軽EVのパイオニア 三菱 i-MiEVが1世代限りに終わった理由

三菱 i-MiEV
そもそも近代の量産EVの歴史は、軽自動車から始まったことをご存じでしょうか。それが、2009年6月5日に登場した三菱「i-MiEV」です。当初の販売先は、官公庁及び自治体、法人に限定されたものの、発表の翌月となる7月下旬よりデリバリーを開始。ただ一般向けの販売も翌年の2010年4月より開始されました。EV普及の功績という点では、日産「リーフ」に軍配があがりますが、その発売は、1年以上先となる2010年12月のこと。そのため、世界での量産乗用EVの未来を切り開いたのは、三菱自動車工業の軽自動車となるわけです。
現代のEVのパイオニアとなったi-MiEVですが、結果的には、後発となるリーフに大敗を期してしまいます。その背景には、軽自動車に求められるニーズを当時のEVではクリアできなかったという厳しい現実がありました。第一は価格です。なんとサイズも性能も異なる2台の価格は、ほぼ同等。しかも、航続距離や車内の広さなどは、サイズの大きいリーフが有利。また当時のEV普及促進を目指し、多額の補助金が支給されましたが、それでも同クラスの乗用車と比べても、圧倒的に割高。しかも主な顧客は、企業や官公庁などでもあったため、後席の利便性なども重視され、リーフ有利な状況にありました。
そして、充電と航続距離です。5分程度の給油で、500km以上の走れる軽乗用車に対して、i-MiEV では、約7時間(200V充電)の満充電で160km(10・15モード)しか走れません。しかも高価な車両代に加え、自宅での充電環境の整備まで整えるのは、大きな負担に感じられたことでしょう。さらに当時は充電インフラの整備も始まったばかりで、急速充電器も珍しい存在。そのため、出先で充電場所を探すのも難儀したはず。このように気軽さや身近さが持ち味の軽乗用車とはマッチしない点が多すぎたのです。
また構造面でも、軽自動車とEVのマッチングの難しさがありました。小型軽量な軽ボディでは、バッテリーの搭載容量にも限界があるためです。もちろん、当初からリーフとは異なり、シティコミューターを目指しており、その方向性は正しかったのですが、日本のアイデアが生み育んだオールマイティな軽乗用車の前では、新技術の塊で、発展途上にあるEVを成立させることは非常に難しかったのです。その点、普通車であるリーフは、進化と共に、エンジン車とのギャップ。主に航続距離と価格の差を抑えることに成功。静かさや加速の良さなど独自の魅力も評価され、着実な成長を続けることができました。そして、今は第2世代のリーフへとバトンタッチしています。その一方、i-MiEVは、2021年3月末に歴史に幕を下ろすことになりました。
航続距離200kmの軽EVがもうすぐ日産からデビュー

日産 IMk
しかし、軽EVが終ってしまった訳ではありません。i-MiEVの技術を活用し、2011年に生まれた軽商用EV「ミニキャブMiEV」は、バン仕様が現在も生産が継続され、郵便局などの配送業務に多く活用されています。16kWhのコンパクトな駆動用バッテリーを搭載し、航続距離は150km(JC08モード)にすぎませんが、規定エリア内を走行する配達車の1日の走行距離を十分満たすことができます。また走行音の静かさから、早朝や深夜の輸送業務にも適していると評価され、今後も活躍の舞台を広げていくかもしれません。
そして、軽乗用EVについても、続報がありました。日産と三菱が共同開発している新型乗用軽EVが、2022年度初頭の発売されることが予告されています。
これは日産と三菱が軽自動車を共同開発するNMKV社によるプロジェクト。そのデザインやコンセプトは、未公表ですが、東京モーターショー2019で初披露された日産のコンセプトカー「IMk」がベースとなるようです。つまり日産デイズや三菱ekワゴンと同じハイトワゴンが企画されています。
事前情報では、航続距離200kmほどのシティコミューターで、補助金を含めた実質価格を200万円以下が目標とのこと。恐らくエントリーモデルの価格であり、装備次第で価格は上昇すると見られますが、リーフなど他の国産EVと比べても、かなり現実的な価格。それぞれのEVの経験も色々と盛り込まれるでしょうから、かなり魅力的な軽EVに仕上げられることが期待されます。
その生産工場は、かつてi-MiEVの生まれ故郷である三菱自動車工業水島製作所。I-MiEVの志は、次世代軽EVに受け継がれようとしているのです。他メーカーも、軽自動車の電動化を推進していく予定ですが、まずはハイブリッド。EVの登場は、まだ先というのが現実。それだけに日産と三菱による新軽EVが市場からどんな評価を受けるのか、業界内からも多くの注目が集まっています。
執筆者プロフィール:大音安弘(おおと やすひろ)

自動車ジャーナリストの大音安弘氏
1980年生まれ。埼玉県出身。クルマ好きが高じて、エンジニアから自動車雑誌編集者に転身。現在はフリーランスの自動車ライターとして、自動車雑誌やWEBを中心に執筆を行う。歴代の愛車は全てMT車という大のMT好き。
