ハイブリッド車の減税はどのくらいなのか、車の購入を検討している方にとっては気になるポイントです。減税が受けられる種類は数種類あり、どれも車の重量や排気量、燃費基準達成率などによって減税額が異なります。
この記事では、ハイブリッド車の減税がどれくらい受けられるのか具体的な例を交えながら解説します。また、ハイブリッド車の魅力や注意点も紹介しているため、購入を検討している方は参考にしてください。
ハイブリッド車の税制優遇

車を所有しているとあらゆる税金がかかってきますが、ハイブリッド車の場合は、税制優遇が受けられる可能性があります。
車に関する税金は、車両を購入するタイミングで支払う環境性能割のほかに、自動車税や車両重量税など決められたタイミングでの支払いが必要です。
ハイブリッド車の場合は、エコカー減税や種別割などが条件次第で適用され、燃費基準達成率が高いモデルは数万円の免除が受けられます。
車両価格では、ガソリン車に比べて数十万高価なハイブリッド車ですが、トータルコストを考えれば得をする選択肢は人によって変わってくるでしょう。
ハイブリッド車とは?

近年、主流となりつつあるハイブリッド車は、ガソリンで動くエンジンだけでなく、電気で動くモーターも搭載していることが特徴です。ハイブリッドシステムには複数の種類があり、普通車だけでなく軽自動車にも用いられています。
まずはハイブリッド車に関する基本的な特徴と、ハイブリッド車が減税の対象になる理由について解説します。
ハイブリッド車は、ガソリンで動くエンジンと電力で動くモーターの2つの動力源を備えていることが特徴です。そして、以下のような種類があります。
- エンジンで蓄電してモーターで走行する「シリーズ方式」
- 発進や低速走行時にはモーターで駆動して高速走行時にはエンジンも作動させる「パラレル方式」
- 走行にはエンジンが作動してモーターはサポートに努める「パラレル方式」
エンジン1つで駆動するガソリン車に比べてエンジンの負担が少なく、結果的にガソリンの使用量も減少します。その結果、少ない燃料で長距離の走行が可能になり、低燃費を実現したことがハイブリッド車の魅力です。
環境性能の高い車ほど減税措置が受けられるのは、環境問題に配慮した自動車の普及と促進の狙いが背景にあるためです。
地球温暖化は世界的な問題であり、政府は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」の目標を掲げています。これにはガソリンで動く車の排出ガスが大きく影響しており、国としては環境性能の高い車をユーザーに選択してほしいため、環境性能の高い車ほど税金が安くなる仕組みをつくっています。
なお、2035年にはガソリン車の新車販売が無くなる方針ですが、それ以降もガソリン車が乗れなくなるわけではありません。
ハイブリッド車が減税になる税金

ハイブリッド車が受けられる減税措置はいくつかの種類があり、車両価格や燃費基準達成率などによって減税率・金額はそれぞれ異なります。
また、車を購入するタイミングによっても基準が違ってくるため、具体的な金額を知るには購入時期や金額、燃費基準達成率を把握しておくことが重要です。
ここからは、ハイブリッド車が減税になる税金について、それぞれ詳しく解説します。
環境性能割は、車を新しく取得した際にかかる税金のことです。数年前までは「自動車取得税」という税金が課せられていましたが、消費税が8%から10%に引き上げられるタイミングで廃止となり、現在の環境性能割が導入されました。
対象になる車は新車・中古車問わず売買によって手に入れた車すべてです。その名の通り、環境性能が高ければ高いほど、減税措置が受けられる仕組みになっています。
税率は0%(非課税)から3%までです。2025年4月1日から2026年3月31日までに取得した自動車は、2030年度燃費基準の達成率を基に税率が分けられます。
環境性能割の税額は、取得価額と環境性能割の税率を掛けることで算出が可能です。購入時にオプションを搭載する場合は、オプションの価格も含まれることを覚えておきましょう。
取得価格が50万円以下の中古車や、相続した車には環境性能割がかかりません。そのため、高年式・多走行の中古車は残価が少ないと判断され、環境性能割の対象外になります。
ギリギリで環境性能割がかかる車は、その分の支払い総額が増えるため、「損をしてしまった」と感じるケースもあるでしょう。中古車を購入する際に「少しでも安く手に入れたい」と考えている場合には、環境性能割の対象外になるよう残価の低い車を選んだり、オプションを必要最低限に抑えたりすることがポイントです。
なお、原付バイクや二輪車は環境性能割の対象外です。
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している方が納税する義務のある税金で、税額は自動車の総排気量で分けられています。
例えば、ホンダ・フリードなら総排気量は1.496Lであるため、自動車税(種別割)の税額は30,500円(1L超え1.5L以下)です。これが年式が古くなり13年が経過すると、税額は34,500円に跳ね上がります。
ガソリン車とハイブリッド車で搭載しているエンジンが同じ場合、自動車税の税額は変わりありませんが、13年以降の増税が対象外であるため、長く乗り続けても税負担が増えないことがハイブリッド車の魅力のひとつです。
4月1日時点での車の所有が税金を納める判断基準ですが、納税時期は5月中旬ごろです。
プラグインハイブリッド車を含む一部のより環境問題に配慮した自動車は、自動車税を減税される「グリーン化特例」を受けられる可能性があります。ただし、新車を購入した場合のみ有効で、中古車の場合は対象外です。
グリーン化特例を受けると、新車登録を行った翌年の自動車税が75%減税されます。トヨタのプリウス(2.0L、2WD)の場合、総排気量は1.986Lであるため、従来の自動車税は36,000円(1.5L超え2L以下)です。グリーン化特例を受けると、新車登録をした翌年に収めるべき税額は75%減税され9,000円になります。
2026年4月30日まで適用されるエコカー減税では、令和12年度燃費基準を達成している場合は免税、80%達成で25%の軽減・90%の達成で50%の軽減が受けられます。
13年以降の自動車税の増税もハイブリッド車は対象外であり、減税額は数万円分になる可能性も大いにあるでしょう。
ハイブリッド車は年式が落ちても増税されない
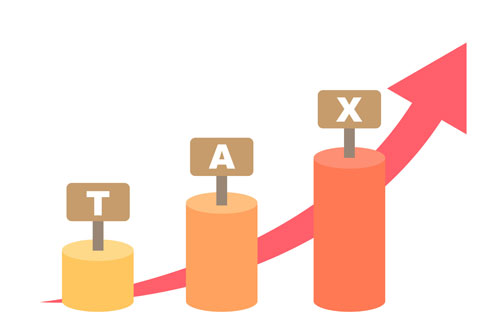
本来は新車登録から13年経過した車は、自動車税や車両重量税が増税されます。古い車は燃費も悪く、排出ガスによって地球温暖化など環境問題に悪影響を与えてしまっていることが理由です。
そのため、地球環境に配慮して造られたハイブリッド車は13年経過しても増税の対象にはなりません。
新車で購入した車に13年乗り続けることを考えると、そもそも乗り換えのタイミングなのではないかと考える方も多いでしょう。しかし、中古車市場には10年落ちの車がまだまだ現役で多く販売されています。
中古車を購入する場合には、購入してから13年ではなく、その車が新車登録された年からの13年であることを忘れないよう注意が必要です。
エコカー減税は2026年4月30日まで

エコカー減税は本来2023年4月で終了予定でしたが、物価高や破壊情勢の変化により2026年4月30日までと3年間の延長が決定されました。
しかし、これまでよりも基準は厳しくなり、基本的には電気自動車やプラグインハイブリッドなど、より環境性能の高い自動車が対象です。
減税措置が受けられる基準は高くなったものの、ハイブリッド車やガソリン車も対象外ではありません。
エコカー減税が受けられるかどうかは、車の購入金額や維持費に大きく影響するため、エコカー減税を視野に入れて車の購入を検討している方は適用期間が過ぎてしまわないよう気を付けましょう。
エコカー減税は2026年4月30日までの間に新車登録を行った車が対象で、国土交通省が定めた燃費基準を達成している場合にのみ適用されます。
エコカー減税は車両重量税の減税措置であり、エコカーでない場合は数万円支払わなくてはならないところが、免税もしくは25%減・50%減される特別措置です。
車選びで悩んだ際には燃費基準達成率も調べてみましょう。
ハイブリッド車の魅力

ハイブリッド車には、減税措置が受けられることだけではない様々な魅力があります。
購入時の金額差からハイブリッド車にしようかガソリン車にしようか迷っている方も多いでしょう。日々の燃料代やリセールバリューを加味すると、ハイブリッド車でも購入時の差額は簡単に取り戻すことが可能です。
ここからは、ハイブリッド車の魅力について紹介します。
ハイブリッド車とガソリン車では同じ車種でも、カタログ燃費を比べれば分かるように、ハイブリッド車の方が燃費性能に優れています。燃費性能は燃料代に直結し、とくに車の使用頻度が高い方にとっては毎月の維持費に大きな違いを出すでしょう。
ハイブリッド車の方が低燃費なのは、ガソリン車には搭載されていないモーターを備えているためです。車は発進時に最も多くのガソリンを消費しますが、ハイブリッド車の場合は発進時の動きをモーターがサポートするため、ガソリンの消費を最小限に抑えられます。
ハイブリッド車を選ぶことは、ガソリンの使用を減らすことにつながるため、環境にも維持費にも良いといえるでしょう。
ハイブリッド車は市場価値が高いことから、売却時により高い値がつく傾向があり、安定していることがハイブリッド車の魅力のひとつです。
中古車市場でもハイブリッド車を求める方が多く、時代のニーズに合っていることが需要が高い要因だといえるでしょう。ハイブリッド車のモーターはとても高価で、もし故障してしまった場合には修理よりも乗り換えを選ぶ方が多くいましたが、現代のハイブリッド車はモーターに厚い保証が付けられているため、ハイブリッド車を選ぶハードルが低くなっているのも需要が高い要因です。
同じ車種であっても、ガソリンモデルかハイブリッドモデルかの違いによって買取金額にも差が出てくるでしょう。
ハイブリッド車は購入時や自動車税の支払いのタイミングなど、あらゆる場面で減税措置が受けられます。
いくら減税されるのかは車種やグレードなど車の状態や車の購入時期・燃費基準達成率などによっても異なるため、実際に得する金額は様々です。
例えば、トヨタのアクア(Z/2WD)であればエコカー減税として約22,500円の減税が受けられるなど、減税措置の有無によって数万円の差があります。
購入時や車検時など、車を所有していると税金を支払う機会は多くなります。少しでも減税措置が受けられるのは、私たちドライバーにとって大きな魅力だといえるでしょう。
ハイブリッド車のなかにはコンセントが埋め込まれているモデルもあります。日常的にスマホやゲーム機の充電をしたり、プールや温泉の後に車内でドライヤーを使用したりすることも可能で、とても利便性に優れています。
また万が一の備えとしても利用可能です。ポータブル電源があると災害時にも電気を使用できますが、ポータブル電源は物によっては10万円を超えるものもあり、自宅に備えているという方は少ないのではないでしょうか。
車のモデルによっては、ガソリン満タンの状態だと災害時に必要な電気を数日分供給できるものもあります。もしものときに備えられるという点は、大きな魅力です。
ハイブリッド車は、モーター走行時とても静粛性に優れています。早朝や深夜に閑静な住宅地など走行するときには、車のエンジン音が響き渡ってしまうように感じてしまいがちですが、ハイブリッド車の場合は気にせずに走行可能です。
また、ミニバンなど3列シートの車だと、車内が広い分会話も聞こえにくく感じます。このようなシーンでもハイブリッド車だとエンジン音が会話を遮らないため、より快適に会話ができるでしょう。モーター走行ならではの「ウーン」というような音は聞こえますが、会話をするときや音楽を聴くとき、より快適に過ごせるでしょう。
また、エコカー減税だけでなく、車を入手したときに納税義務が発生する「環境性能割」も減税措置が受けられます。
ハイブリッド車を購入する時の注意点

ハイブリッド車の魅力は豊富にありますが、デメリットがないというわけではありません。とくにガソリン車よりも造りが複雑であることから、万が一の故障時には修理費用が高額になってしまうケースもあります。
ハイブリッド車の注意点を知らずに購入し、後悔しないためにも事前に確認しておくことが重要です。
ここからは、ハイブリッド車を購入する時の注意点について解説します。
同じ車種であっても、ガソリンモデルとハイブリッドモデルの違いで十数万円の車両価格の違いがあります。
例えば、トヨタの人気ミニバンモデル・ヴォクシーのハイブリッド車の新車価格は374万円(HYBRID S-Z・2WD・7人乗り)です。同じ条件でガソリン車を選択すると新車価格は339万円で、差額は35万円になります。
購入時に減税措置があることを考慮しても、初期費用はハイブリッド車の方が高くついてしまうでしょう。ハイブリッド車を選ぶことで、付けたいオプションを我慢することになってしまうと後悔するリスクもあります。
購入時の予算はガソリン車よりも多めに用意しておくことが重要です。
ハイブリッド車はエンジンだけでなく、モーターも搭載している分、より複雑な構造であり、修理費用が高額になるケースがあることに注意が必要です。
タイヤの交換やオイル交換などのメンテナンスでは、ハイブリッド車とガソリン車の違いにそこまで大きな差額は生じません。しかし、ハイブリッドシステムやモーター、バッテリーを修理・交換するとなると、まとまった金額が必要になります。
ハイブリッドシステムやバッテリーに劣化の症状が出てくるのは7年以上使っていたり、10万km以上走行していたりする車です。高額な修理が必要になったときは、車の乗り換えのタイミングと割り切るのもひとつの手段です。
自動車が最も燃料を消費する動きは「停止からの発進」です。ハイブリッド車はこの動きをサポートすることで、燃料の消費を軽減させ、燃費性能向上に貢献しています。
信号の多い市街地では、ガソリンモデルとハイブリッドモデルの燃費の違いが大きく表れますが、停止と発進の少ない高速道路の走行時にはハイブリッド車ならではの燃費の良さは感じにくくなってしまうでしょう。
信号の数も少なく、交通量も少ない地方にお住まいの方や、日常的に高速道路を使用している方は、ガソリンモデルとハイブリッドモデルの燃費の違いを感じにくいことに注意が必要です。





